●日時:平成16年5月27日(木)午後2時から3時52分
●場所:玉造町役場「大研修室」
●あいさつ
●議 事
(1)協議事項
1) 新市の事務所の位置について(継続)
2) 議会議員の定数及び任期の取扱いについて(継続)
3) 一般職の職員の身分の取扱いについて
4) 特別職の職員の身分の取扱いについて
5) 公共的団体等の取扱いについて
6) 新市の名称について(継続)
・新市名称候補選定基準(案)
・新市名称募集要綱(案)
・新市名称候補の選定に係る小委員会の設置(案)
7) 新市建設計画策定に係るアンケートについて
(2)提案事項
1) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
2) 慣行の取扱いについて
3) 介護保険事業の取扱いについて
4) 電算システムの取扱いについて
(3)その他
● 出席委員(35名)
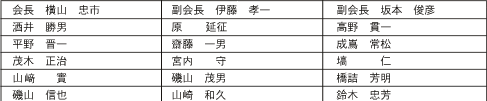 |
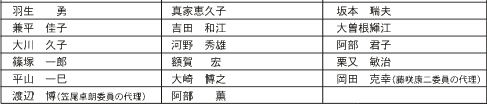 |
●欠席委員(1名)
宮内 勲
●出席顧問
香取 衛 藤島 正孝
○菅谷事務局次長
皆様、大変お待たせをいたしました。定刻になりましたので、ただいまより第4回の行方郡合併協議会の会議を開会させていただきます。
本日は、それぞれ委員の皆様方にはお忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
ちょうど一回りをしまして、当番町ということで、本日の司会をさせていただきます玉造町役場の菅谷でございます。ひとつよろしくお願いをいたします。
まず始めに、当協議会の副会長であります伊藤北浦町長より開会のあいさつをお願いします。
○伊藤副会長
どうも皆さんこんにちは。
本日は、大変お忙しい中、皆様方にご参会いただきまして、大変ご苦労さまでございます。
ただいまより第4回行方郡合併協議会を開催いたします。よろしくお願いいたします。
○菅谷事務局次長
ありがとうございました。
では、会議次第に沿いまして進めさせていただきますが、早速、当協議会の会長であります横山会長よりあいさつをお願いいたします。
○横山会長
本日は、大変お忙しい中、第4回行方郡合併協議会にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、先週でありますけれども、19日の水曜日になりますけれども、合併関連3法案が参議院で可決をされまして、成立をいたしました。この3法案は、新合併特例法と地方自治法、現行合併特例法の改正法でございますが、このうち現行の合併特例法の改正によりまして、いわゆる経過措置が設けられたということでございます。具体的には、皆様方ご承知のとおり、平成17年3月末までに市町村議会の議決を経て都道府県知事に合併を申請し、平成18年3月末までに合併をしたものにつきましては現行の合併特例法の規定が適用されるというものでございます。今後、特例法以外の支援措置の継続についても明らかになってくるものと思われますので、それらを踏まえまして必要な協議を進めてまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
本日の協議事項でございますけれども、前回からの継続協議となります新市の事務所の位置、議会議員の定数及び任期の取り扱いのほか、一般職の職員の身分の取り扱い、特別職の職員の身分の取り扱い、公共的団体等の取り扱い、新市名称の公募の関係、新市建設計画策定にかかわるアンケートについてを予定をいたしております。皆様方には忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。
本日は、まことにご苦労さまでございます。よろしくお願いします。
○菅谷事務局次長
ありがとうございました。
では、早速議題の方に入らせていただきます。
なお、当協議会の合併協議会規約第10条第2項の規定によりまして、横山会長に議長をいたしまして、議事の方をお願いしたいと思います。
それでは、横山会長、よろしくお願いします。
○横山会長
それでは、規約に従いまして議長を務めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
なお、本日の出席委員でございますけれども、35名であります。協議会規約第10条第1項に規定いたします定足数に達していることをご報告申し上げます。
それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきたいと思います。
まず、協議事項の1)でありますけれども、新市の事務所の位置についてを議題といたします。
前回の協議会において、新庁舎の建設をすべきか否かという点についてのご意見をいただきました。意見の一致を見ることができませんでした。それぞれ町に持ち帰りまして、十分検討した上で本日の協議ということであったかと思います。
それでは、委員の皆さんにご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
塙委員さん。
○塙委員
玉造の塙です。
前回の会議の中で、新市の事務所の位置についての中で、要は庁舎を建てるのか、建てないのかというような問題が継続になったのかなというふうに思いますけれども、これ事務所の位置の話なんですか。それとも、建設するとかしないとかの話なのか、そこのところ、まず確認をさせていただきたい。
○横山会長
それでは、前の協議会においては、新しい市庁舎を建てるか否かということから議論をいただきまして、それから、新市の事務所の位置についてと、こう移っていこうと思ったんですが、一番先の新庁舎建設是か非かという状況で意見の食い違いがあったということでございまして、きょうは、新しい市の庁舎を建てた方がいいか、建てない方がいいかをまず皆さんにお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○塙委員
わかりました。
それでは、今、議長からの話のとおり、建てるのか、建てないかということで、玉造町の方でもその後いろいろ検討した結果、一応10年間の特例債が受けられる期間に、建設計画の中に盛り込んでおいた方がいいではないかというような結論に達しておりますので、確認をよろしくお願いをしたいと思います。
○横山会長
ただいま玉造町さんの塙委員さんの方から建設というようなお話がございました。
先般、麻生町さんと北浦町さんは、建設をした方がよろしいというようなご意見であったように思うんですが、もう1回確認をしたいと思います。
それじゃ、北浦さんからお願いします。
○宮内 守委員
ご苦労さまです。北浦の宮内でございます。よろしくお願いします。
ただいま会長さんの方からお話がありましたので、確認の意味で発言をさせていただきたいと思います。
北浦町につきましては、合併の目的を考えますと、前回どおりということで、5年程度後に新庁舎を建てて、新市の新しい執行体制を整えることが大事であるというふうに考えてございます。そういうことでございます。よろしくお願いします。
○横山会長
わかりました。
それでは、麻生町さんの方でお願いをいたします。茂木委員さん、お願いします。
○茂木委員
どうもこんにちは。ご苦労さまでございます。麻生の茂木と申します。
ただいま玉造の塙委員さんの方からお話がございましたように、また、麻生の方でもこの前から話しておりますように、一応将来建てるということで麻生の方も一致しております。
○横山会長
ありがとうございました。
それでは、ただいま3町とも新しい市庁舎を建設するというような状況で建設計画の中に差し込むというようなことで決定をいたしたように思います。
それでは、再度確認をいたします。新しい市庁舎を建設することにご異議ありませんか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでありますので、そのように決定をさせていただきたいと思います。
それとあわせて、新しい市庁舎の建設ということで、その建設までの間に、この事務所の位置ということが出てくるわけであります。事務所の位置をどこにした方がいいか。それから、もう一つは、その設置方式、いわゆる先般皆さんにご議論をいただきました分庁方式がいいとか総合支所方式がいいとかといろいろあったんですね。そういうものを踏まえて、できれば皆さんにご意見をお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
ちなみに、3町の今の現在の役場を使うということですよね。3町の役場を使うということです。そして、その3町の中で、いわゆる公文書を発行するその位置、住所、それをまず皆さんに決めていただきたい。それから、その3町を使う、役場に張りつけるいろいろな方式ですね、それをひとつ皆さんにご議論をいただきたいと思うんですが。
宮内委員さん、お願いします。
○宮内 守委員
事務所の位置は、大変申しわけないんですが、置いていただきまして、現在の庁舎を利用するということの中で、北浦といたしましては、改革という視点から、将来の新庁舎への移行を考慮いたしますと、総合支所方式といわゆる分庁方式といった完全なものに分けるのではないと、分けるにはちょっと無理があるのではないかと。そういうことで、両者の部分を持った混在型になるのかなという選択肢があると思います。ただ、それについては、具体的な形が見えないということもございます。また、そこで、住民サービスの確保と、より効率的な組織や職員の有機的な配置を考慮した一定の形態をモデルケースとして事務局の方から早急に提出していただければ幸いというふうに思っております。
○横山会長
事務局の方でもっと詳しく提示した方がいいというようなお話ございました。
先般の協議会での議論を集約いたしますと、北浦さんが申しました、北浦さんは、混在型みたいな、一緒に合わせたような、それから、麻生町さんは分庁方式という話でしたよね。それから、玉造さんは総合支所方式がいいだろうということでお話があったんですが、その辺は、本日も変わりないですか。
じゃ、お願いします。
○塙委員
今話を聞いていると、混在型というのを事務局の方でちょっと説明をできればというふうに思うんですけれども、よくご理解できないものですから、ちょっと。
○横山会長
混在型という案は、事務局で出しておりません。だから、ちょっと説明できないと思いますね。
○塙委員
それじゃ、北浦さんの方で、もうちょっと具体的に説明が願えればありがたいなというふうに思うんですけれども。
○横山会長
よろしいですか。
お願いします。
○宮内 守委員
いわゆる分庁方式、あるいは総合支所方式につきましては一長一短これあるわけでございまして、住民のいわゆる皆さんから見ると、分庁方式でございますと、本庁機能の下の各課のサービスというんですか、住民とか福祉とか総務とか分かれてしまいます。そういうことで、役所が離れていくと。そういったことについての、住民がそこへ行くまでの負担というか、そういうものがマイナスに挙がるわけでございまして、そういうこと。それからあと、総合支所方式については、一般的に見ると、どこにその改革の評価が出るのか、非常にこういう点もございますので、そういう総合支所のマイナスの面、分庁方式のマイナスの面をどうにか削っていただいて、いわゆる混在型に持っていって、合併して新庁舎ができるまではなるべく住民のサービスが低下しないようにというようなことでお願いしたいというふうな、そういうことでございます。
○横山会長
ありがとうございました。
じゃ、橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
玉造の橋詰ですが、総合支所方式で玉造は申し上げましたんですが、この根拠となるものは、やはり現在既に高齢化、少子化が進んでおりまして、きょうの時点で申し上げますと、50歳を境にして人口の動態が半分半分と。50歳以上が半分、50歳以下が半分というような人口の中で、西暦2050年には今の人口が約半減するだろうと。こうなってくるシミュレーションが現在あります。そういう中で、いたずらに箱物をつくるということよりは、やはりある程度のそういう動態を見据えた中でやっていくと。
それと、現在は、電子決裁、これがかなり進んでおるはずでございます。まだ職員によって、また、地域によって、電子決裁の習熟度、これについては相当各自治体でもばらつきがあるかと思います。しかし、この電子決裁については相当以上のテンポで進んでいるのも現実であります。そうなりますと、やはりある程度むだを省きつつ合理化して、やはり最大の眼目は人件費だということになりますと、総合支所方式であっても、これは、そういう意味の合理化が無理なくできるであろうというような推測ですね。これは、実際の世の中の変化に合わせて行政も対応していかなくてはならないと思いますが、現在のシミュレーションですと、2050年には人口が半減すると。そうしますと、食糧も半分しか食べないと。当然、半分しか要りません。車も今の半分でいいと。だんだんとそういう経済的な意味から相当空きが出てくるだろうというようなことを考えますと、新たに大きなものの箱物というよりは、一応本庁舎は建てても、それなりの動向を見据えるという肝心な時期に日本の国そのものが差しかかっているんではなかろうかと。みんなの意識も相当変化しているのも間違いありません。ということで、抵抗なく今受け入れられるのは総合支所方式ではなかろうかと。これは、やめていく職員に対しまして採用人数を減らしていけば、当然合理化は、人間的には減ってくるわけですし、若い人にも電子決裁化についての習熟度が高まれば、ある程度のところは達成できるんではなかろうかと。そのテンポの早さの問題が勝負だと思うんですが、民間は、大変ドラスチックにやっていますが、行政はそこまでドラスチックにはサービスが極端に低下できませんので、その点、そういうような考えであります。
○横山会長
ありがとうございました。
麻生町さんの方ではないですか。分庁方式、この前のとおりですか。
それじゃ、今、3町とも大幅にこの設置方式が違っているということでございます。それで、混在型、それから、総合支所、分庁方式、これもっと事務局で精査をしていただいて、メリット、デメリットの状況を詳しく精査して、各委員さんの方にご提示が願えればいいと思うんですが、このままでは幾ら協議しても平行線で、何時間やってもだめなんだろうと思いますから、お願いしたいと思います。
それで、きょうこの2点、事務所の位置、それからその方式、これは継続協議にしたいと思うんですが、皆さんどうですか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでありますので、継続協議にしたいと思います。
どうぞ。
○高野委員
今、継続というお話の中で、多分今北浦さんの言った混在型と申しますか、そういういい面を取り扱ってやるというもの、それも非常にすばらしい案だと思います。事務局の方の中で、この次までには混在型というものをメリット、デメリット合わせましてきちんとしたものが出てこないとこれまた審議ができないということなので、会長さんの方からひとつよろしくご指導のほどお願いしたいと、かように思います。
以上です。
○横山会長
今、玉造の議長の方から話がありましたけれども、これは、協議をする前に、大変だろうけれども、一日も早く精査をして、各町の方にお配りを願いたいというふうに思います。そして、各町で多分勉強会をやると思いますので、そして、次の協議会でなるべくだったら結論を出していただきたいというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。
どうぞ。
○羽生委員
麻生の羽生と申します。どうもご苦労さまでございます。
今の事務所の位置ということで、継続というようなことになったようでありますけれども、これ、麻生の方でも、どこの3町も歴史と文化とか風土は全部あるわけですけれども、現在のところは、まだ麻生にも県やそのほかの出先機関の官庁そういうものが数多く残っている観点から、できれば麻生町にこの位置をぜひお願いしたいと。そのように、継続でも結構ですけれども、この時期までにはそのような希望として、やっぱり麻生あたりに置くべきがいいのかなというような考えを皆さんで持っていただければ私もありがたいと思います。
以上です。
○横山会長
じゃ、玉造さん。
○橋詰委員
立場が逆なものですから言わせていただきますが、確かに、風土、文化、それぞれみんな歴史もお持ちだと思います。交通アクセスに関しましては、玉造は、国道
355、 354というように2本入っておりますし、交通の流れからしますと、私は3町の中で一番交通量が多いのは玉造の今の国道2本走っているというところではなかろうかと、そのように思います。それと、鉄道が、これは、玉造町は5つの駅があります、町の中に。やはり、公共的な鉄道ということも玉造に入っておりますし、また、これから百里基地民間共用化、これは、きょうもある総会に私は行ってまいりましたけれども、茨城県知事の方ではこれは積極的に進めるというようなことを言っていますので、そうしますと、百里民間共用化に近い玉造と。水戸にも近い、また筑波にも近いという交通の要所というような意味ではぜひ玉造にと、このように考えておりますので、一応玉造の主張ということは申し上げていただきます。よろしくお願いします。
○横山会長
北浦さん、お願いします。
○原委員
北浦の原でございます。
ただいま麻生さん、玉造さんから自分の町の利点を大変よく説明しておるようでございますが、この3町合併という原点を考えてもらわないと、この合併が成功しないのじゃないかなと。特に、自分の町ばかり強調していたのでは、3町でもお互いに言い分はあります。しかし、合併を完成させるためには、お互いに認めるところは認める、引くところは引く、そういうことを考えて積極的に話し合いしないとうまくいかないと思いますので、各町ともその点をうまく調整して、次回はうまくまとまるようによろしくお願いしたいと思います。
○横山会長
原委員さん、ありがとうございます。
ひとつ、今の意見に集約されていると思うんですよね。これは、お互いに引くところは引く、進むところは進む。そういうことで、次までにいろいろ議論をしていただきたいというふうに思います。ひとつよろしく。
はい。
○磯山信也委員
位置について、玉造さんと麻生町が出たもので、この際だから、北浦さんの意見を聞いておいて継続した方がいいんじゃないですか。
○横山会長
だから、1町ぐらい意思を表示しないところがあった方がいいんですよ。全部聞いてしまうと、三者三様で、またまとめるのが大変だから。いいです。これは、北浦の気高さをよく理解してください。
それでは、次に入りたいと思います。
協議事項の2)でありますけれども、議会議員の定数及び任期の取り扱いについてを議題といたします。
前回の協議会において在任特例を適用する意見が出され、任期については合併の期日とあわせて決定することが確認をされております。ここでは定数についてを議論したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。ご質問等お受けいたします。
茂木委員さん。
○茂木委員
麻生といたしましては、議員の定数を24名というふうにご提案申し上げます。
○横山会長
茂木委員さんから議員さんの定数を24名ということで意見が出ました。
ほかの委員さん方。
はい。
○塙委員
玉造の方も24ということで、この間当町の会議でもそういうふうに決まったんですけれども、なぜ24かというと、2万人から5万人が、26が定数ということですけれども、今回3町が合併すると4万
1,000ぐらいかなというふうに思います。そういうふうな観点から、24名ならば住民にも説明することができるのかなというふうな結論に達したところでございます。少なければいいということもあるけれども、いたずらに少なくすると、住民の意見が反映されないということもございます。そういう意味からも、玉造町でも24ということで決定をしましたので、お諮りを願いたいと思います。
○横山会長
北浦さんの方で。
お願いします、宮内委員さん。
○宮内 守委員
北浦町といたしましても、定数につきましては麻生さん、玉造さん同様24名ということで希望させていただきたいと思います。ただいま塙委員さんの方からお話があったとおりでございます。
ちなみに、北浦町の議会でのアンケートをとりましたところ、26名という人が1人、24名という人が11名、それから、22名という人が5名というようなことでございまして、私ができなかったものですからあれですが、そういうふうなことでございます。よろしくお願いします。
○横山会長
ありがとうございました。
議会議員の定数につきましては、24人ということで意見がまとまったように思います。そのように確認をいたしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでありますので、新市の議会議員の定数については24人といたしたいと思います。
それから、在任特例の期間については、合併の期日とあわせて議論をして決定していきたいと思います。これでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
そのように確認をさせていただきたいと思います。
次に、協議事項の3)でございますけれども、一般職の職員の身分の取り扱いについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
皆さん、ご苦労さまでございます。
前回ご説明をさせていただきました資料をごくごく簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
一般職の職員の身分の取り扱いにつきましては、合併特例法の中に、新市に引き継ぐというように措置しなければならないということと、それから、新市において平等に取り扱わなければならないということが規定されていますということをご説明申し上げたところでございます。そして、それらに基づきまして、調整方針として3つ掲げてございます。1番といたしましては、3町の一般職の職員は、新市の職員として引き継ごうとするということ。それから、2、職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとするということです。これにつきましては、当然3町、今の職員数と、それから、類似の自治体の職員数を比較しますと、ある程度多い数字が出てまいると思いますので、それを定員管理に努めると。そして、定員適正化を図っていくんだというような趣旨で、2番目の調整方針の案でございます。そして、3番目でございますが、職員の職名及び職務の級、給与制度等については、他の自治体の例などを参考に調整し、統一を図るものとするというようなことでございます。
よろしくご協議をお願い申し上げます。
○横山会長
それでは、事務局からの説明が終わりました。
皆さんにご意見をいただきたいと思います。
ご意見ございますか。
(案で賛成です)
○横山会長
ないようでございますので、一般職の職員の身分の取り扱いについては、調整方針案のとおり決定をしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、協議事項の4)でございますけれども、特別職の職員の身分の取り扱いについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、特別職の職員の身分の取り扱いについて、これにつきましても前回お配りをしまして説明を申し上げました資料でございまして、9ページ以降でございます。ポイント、要点を簡潔に申し上げたいと思います。
今回対象としてここに掲げてあります特別職につきましては、一つには常勤の特別職ということで、一般職に属します教育長さんを含みますが、町長、助役、収入役、教育長さんの取り扱いということ、それから、2番目として、議会議員さんの取り扱いということ、それから、3番目といたしまして、地方自治法の中に設置が義務づけられております6つの委員会の取り扱いということで3)が載ってございます。それから、4)といたしまして、そのほか各町の条例に基づきまして設けております委員会の委員等ということで、こちらの方を掲げてございます。
今回の1)から3)については、地方自治法の中に規定、それから、そのほか関係法令がございまして、それに基づき各町が今現在設置をしているものでございまして、新市におきましても同様の取り扱いになるということでございます。
それから、4)につきましては、これは、各町の条例に基づくということでございますので、この設置につきましては、新市において条例をつくりまして設置がされるというような取り扱いになるということでございます。
それら取り扱いを踏まえますと、調整方針の案ということで取りまとめをさせていただきたいと思いますけれども、特別職の職員等については、その設置人数、任期等について、法令等の定めるところに従い調整をする。法令等に定めがない場合は、新市において必要に応じて新たに設置をするというような調整方針でございまして、具体的には1)から4)について、具体の調整が9、10ページに載せてございますので、これにつきましては前回説明をさせていただきましたとおりでございます。
以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
皆さんにご意見を伺いたいと思います。
何かございますか。
(ありません)
○横山会長
ないようでありますので、特別職の職員の身分の取り扱いについては、調整方針案のとおり決定をしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのとおり決定をさせていただきたいと思います。
次に、協議事項5)でありますけれども、公共的団体の取り扱いについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
資料につきましては、前回の資料25ページ以降でございます。よろしくお願いを申し上げます。
公共的団体につきましては、前回申し上げましたように、法人であるか否かを問わずに、公共的活動を営むすべての団体を含むということでございます。そして、この公共的団体の取り扱いについて今回ご協議をいただくということにつきましては、新市の一体化の観点、それから、組織の強化の観点、そういう観点から新市において統合されることが望ましいのではないかというふうに考えられるということでございます。それから、それに関しましては、27ページになりますけれども、合併特例法の16条第8項になりますが、そちらの方に統合整備を図るように努めなければならないという規定がございます。それから、自治体とその団体の関係で申し上げますれば、その下に書いてございます地方自治法の抜粋の中に、公共的団体等の監督という項目が盛り込まれておりまして、必要な調整を図ることができますよという規定があるものでございます。
それらの状況を踏まえまして、調整方針の案といたしましては、公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。(1)といたしまして、3町に共通している団体は、できる限り合併時に統合するように努める。(2)3町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。(3)町に共通している団体で統合に時間を要する団体については、将来統合するように努める。(1)から(3)で、3町に共通しているというようなことで、ここに掲載をさせていただきました。(4)といたしまして、その他の団体については個別に検討し、必要な調整に努めるということで、2町に共通するものもあれば、また1町というものもあります。新市のまちづくりの推進という観点から、その公共的団体に対して必要な調整を図っていくということがまちづくりの上で必要かなというふうに考えておるところでございます。それに基づきまして、今回の調整方案ということでございます。
なお、説明がおくれましたけれども、現況等のところに、主な公共的団体ということで添えてございますが、これだけを対象にするということではなくて、3町にそのほかたくさんの公共的活動を営んでいらっしゃる団体ございますので、それらをすべて対象にいたしまして、これらの調整方針に基づいてこれから調整作業をさせていただければということで今回ご提案を申し上げるということでございます。よろしくご検討をお願いします。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
それでは、皆さんにご意見を伺いたいと思います。
何かございますか。
(発言者なし)
○横山会長
ないようでございますので、公共的団体等の取り扱いにつきましては、調整方針案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をいたしたいと思います。
次に、協議事項の6番でございますけれども、新市の名称についてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、資料の方32ページ以降でございます。
今回、新市の名称につきましては公募方式ということ、それから、小委員会を設置いたしまして、募集作品の中から絞り込みを行うということについて、ご確認を既にいただいているところでございます。それに基づきまして、今回名称の選定基準を提案しているということ、それから、名称の募集要項について、2番目に提案をさせていただきたいということ、それから、3番目といたしまして、小委員会の設置の案という形でご提案申し上げると。3点こちらの項目の中でご協議をいただくものでございます。
まず、1点目の新市名称候補の選定基準の案でございます。
32ページの方をごらんいただきたいと思いますが、既に、麻生、北浦、玉造町の既存の名称については使わないということをご確認いただいておりますので、既存の市の名前、それから、麻生、北浦、玉造の名前を使わないということを前提にしながら、こちらの方、1番に書いてございます、地域が地理的にイメージできる名前、そして、地域の特徴をあらわす名前、地域の歴史、文化にちなんだ名前、4)といたしまして、住民等の理想、願いにちなんだ名前、そして、そのほか新市名としてふさわしい名前という観点から名称の選定をするということでございます。
そして、選定方法につきましては、小委員会が5点を選定いたしまして、その5点という結果の中から協議会が1点を最終決定をするというような選定方法を考えておるということでございます。
そして、33ページをごらんいただきたいと思います。
先ほど申し上げました麻生、北浦、玉造町の名称に係る取り扱いに関して、今の漢字を平仮名とか片仮名に読みかえ、表記を変えるという場合であるとか、それから、そのほかの文字と組み合わせる場合等々考えられると思いますけれども、それらについては無効といたしますという取り扱いの提案でございます。
それから、もう1点、全国に存在する市町村名の取り扱いということで、若干前回説明不足がございましたので補足をさせていただきたいと思いますが、平成12年の地方分権一括法の施行によりまして、これまで名称の変更というものが、都道府県知事の許可制だったものが協議制に改められました。そういう観点からすると、全国的に既にある名称を使う道は開かれたということはあるんですが、実際に、郵便の配送を始めとした住民生活、それから、企業の経済活動の点、それから、これから当地域、商業、観光であるとか、それから、農業においていろいろなブランド化というものも課題として抱えております。また、既存の名称ということになれば、既にその名称を使用している自治体への影響、そういうものも当然考えられるところでございます。そういうことを考えますと、現実的には既存の市町村名というのは使わない、使えないというのが現状なのかなというふうに思われます。
そういうことを踏まえまして、先般の西東京市の合併において総務省が回答した事例、そういうものを踏まえまして取り扱いをさせていただければそういう課題が克服できるのかなということで、こちらの方に書かせていただいてあるところでございますので、そういう観点でごらんをいただきたいというふうに思います。
そして、35ページが新市名称の募集要項ということでございます。ここで見ていただきたいのは、まず、募集方法の中の応募資格でございます。3町にお住まいの方、それから、通勤をされている方、通学をされている方、そして、3町にゆかりのあるというふうに書いてありますが、前回申し上げましたように、出身者と申しますか、これから戻ってくると。地元に戻って頑張りたいんだというような方々を除くということは適当ではないのかなという配慮でこちらの方を設けさせていただいたということを説明させていただきました。
そして、応募方法については、専用の応募はがきを募集のチラシの中に刷り込みまして、郵便局の承認番号を得て、こちらの受取人払いという形のはがきを配付させていただくという専用応募はがき、それから、官製はがきやファクス、eメールからでも応募できますという取り扱いをさせていただきたいということでございます。
それから、必要記入事項については、こちらの方に書いています1)から7)のとおりでございます。
それから、飛びますが、募集期間については、36ページ、4番になりますが、6月15日から7月15日という形で取り扱いをさせていただきたいということ、それから、6番で書いてありますが、麻生町、北浦町合併協議会が実施した名称の募集作品についても、今回の3町の協議会、行方郡合併協議会が実施いたします募集作品に含めて取り扱いをさせていただきたいという内容が6番の取り扱いの提案でございます。
それから、9番目といたしまして、応募作品の中から記念品を贈呈いたしますよということで、1)、2)、3)ということをこちらのところに書かせていただいてあるところでございます。
37ページが、大まかな進め方ということで、予定をこちらの方に載せさせていただいてあります。
それから、38ページが小委員会の設置案ということでございます。名称、そして付託事項につきましては、名称候補の選定にかかわることということで、応募作品からおおむね5点を選定することということでございます。設置につきましては、募集が終わりました7月16日ということで、委員の選任については、現時点の案といたしましては学識経験者の方々にお願いをしたいというような案でございます。
以上、選定基準、募集要項、小委員会の設置についてでございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
新市の名称につきましては、3点ほどお諮りしたい項目がございますので、順にご意見をいただきながら協議をしてまいりたいと思います。
まず最初に、新市名称候補選定基準(案)と新市名称募集要項(案)の2点について、皆さんにご意見を伺いたいと思います。
磯山委員さん、お願いします。
○磯山茂男委員
北浦の磯山でございます。
前回、私ども特別委員会の中で、要望と申しますか、新市の名称について、賞品の件なんですけれども、名付け親賞をとって1名ですけれども、この応募者は相当数、多く出てくるのではないか、同じ名前ですね。それで、そういう中において、3名くらいにあげたらどうだろうというふうな意見があったものですから、この場をおかりして北浦の方の意見としてお願いしたいと思います。
○横山会長
ただいま北浦の磯山委員さんからご要望があったわけでありますけれども、皆さんどうですか。
(発言者あり)
○横山会長
もう1回説明してください。
○磯山茂雄委員
説明不足だったようですみません。
予算につきましてはどうこうすることはありません。この範囲の中で、3町の中で、やはり大体1名くらいずつというか、そんな形にとれればどうかなというふうなことなんです。
○横山会長
そういう意味ですか。
そういうことだそうです。皆さんどうですか。じゃ、そのようにちょっと修正してください、皆さんよろしいそうですから。3名程度でいいでしょう。3名って決めるんですか。ちょっと待ってください、こっちから先に。
(3名でとの声あり)
○横山会長
じゃ、そのように。
じゃ、どうぞ。
○山崎委員
麻生の山崎と申します。
今の名付け親賞の10万円相当を3人でということですか。そうですか。それをちょっと3で割ると割り切れないので、子供が生まれたときに名前つけるの、おじいさん、おばあさん、両親というふうなことで4人がいいんじゃないか、そうしたら割り切れるんじゃないかと思いますので。
○横山会長
じゃ、宮内委員さん。
○宮内 守委員
ただいま磯山委員さんがお話ししたのは、例えばですけれども、ある名前が決定されると、その名前が一番多かったと。それが、各町にそれぞれ旧麻生町、北浦町、玉造町でいたという場合には、その各町から1人ずつ名付け親賞ということでやる。ですから、3人ということですので、4人になるとどういうふうになるのか私もわかりませんが、そういうことで3人ということでございます。よろしくお願いします。
○横山会長
じゃ、そのように決定をさせていただきたいと思います、皆さん賛成なようですから。
○茂木委員
ちょっと確認したいと思いまして。多分、名付け親賞で10万円の該当のやつがかなり出ると思います、20件も30件も。その中から3人、各町村で1人ずつと、抽せんで。50通の中から最初に引いたら麻生町、その次北浦、その次玉造とぴったりしてくれればいいけれども、最初に玉造、また玉造、また玉造とやったときには今度……。
(発言者あり)
○茂木委員
町村ごとに分けていくと。町村ごとに分けておいてね。心配したものですから……。
○横山会長
それは大丈夫です。
じゃ、ほかにないですよね。
まだあるんですか。
はい。
○橋詰委員
これ大体、世帯数からいうと、1万 2,000世帯ぐらいですかね、3町で。どの程度のこれ、事務方では投票の結果、出るのかなと。ただいまの話ですと、はがきを前提にして言っているようですが、インターネットでも可能だということになっていますので、はがき来たものだけから抽せんということはこれおかしな話ですから、それは転記しなくてはならんという手間は、それはやるわけですね。それと、重複した投票ですね、はがきとインターネットとか、そういうもので両方と。これはチェックするわけですね、必ず。それと、玉造へ勤務する者とか、麻生へ勤務する者とかいう方の実在を、それはどのようにして根拠を探すのかと、細かくいえばそういう心配もあるわけですよ。そこら辺、どの程度今まで1万
2,000世帯でやる場合は、どの程度の票というのがあるのか、参考にちょっとお伺いしてみた。
○横山会長
じゃ、麻生と北浦のやった部分から逆算すればわかるわ。
はい。
○江寺事務局次長
推測でもおかしな話になると思いますので、2町でやったときにおおむね 1,000だと思っていただければと思います。ほかの協議会と比べますと、多分若干割合的には少なかったのかなというふうには思っていますけれども、実際に、実数としてはそのぐらいだと思っていただければ。
○横山会長
それでは、事務局の方でそつなくやるそうでありますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、新市名称候補選定基準(案)並びに新市名称募集要項(案)につきましては、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
次に、新市名称候補の選定にかかわる小委員会の設置(案)について、ご意見を伺いたいと思います。
ご意見ございますか。
どうぞ。
○塙委員
小委員会につきましては、玉造の方では学識経験者にお願いをした方がいいんじゃないかというふうな決定をしました。その中で、小委員会、学識経験者にお願いをし、最後に協議会でということなので、ふだんは学識経験者にお願いはした方がいいのではないかというようなお話はしました。
以上でございます。
○横山会長
先般、北浦の委員さんから、議員さんも小委員会にどうして入れないんですかというご質問がございましたけれども、それは、どうでしょう。よろしいですか。
それじゃ、麻生さんも。
(結構です)
○横山会長
玉造さん案でね。
それでは、新市名称候補の選定にかかわる小委員会の設置(案)につきましては、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。
ここで、暫時の間休憩をいたしたいと思います。
3時10分まで休憩といたしますので、よろしくお願いいたします。
(休憩)
○横山会長
それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きたいと思います。
協議事項の7番でありますけれども、新市建設計画策定にかかわるアンケートについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○森坂計画班長
事務局の森坂です。よろしくお願いします。
それでは、資料39ページからとなってございますが、新しい市の合併建設計画というのを合併後10年間の計画をつくるわけですが、その計画をつくるに当たりまして、住民の住民アンケートということで実施をしたいというふうに考えてございます。既に、麻生町、そして北浦町につきましては、同じような内容でアンケートを実施しておりましたので、今回は玉造町のみの実施ということになってございます。玉造町の全世帯を対象としまして、アンケートの方、実施します。郵送で直接送付をいたしまして、返信用の封筒で返信をしていただくというようなことでございます。そして、この協議会で承認をいただければ、6月1日から約2週間、6月13日までの間でアンケートの方を実施しまして、その後集計の作業に入っていきたいなというふうに考えてございます。
アンケートの内容でございますが、資料40ページからとなってございますけれども、A4版6ページの構成でございまして、それぞれ選択方式というような形で簡単に記載できるような内容になってございます。合併する際のまちづくりの将来像、そして、それぞれ社会基盤の整備や生活環境の整備など、それぞれの項目ごとのアンケートということで内容になってございます。最後に、自由の提案ということで、自由表記の欄を設けてございます。
以上のような形でアンケートを実施したいということでご提案を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
それでは、皆さんにご意見を伺いたいと思います。
何かございますか。
じゃ、橋詰さん、お願いします。
○橋詰委員
前回、問10の問題で、問10の12項は、別の文言に切りかえるというふうに聞いていたんですが、どうなんでしょうか、これ。
○横山会長
事務局に説明をさせたいと思います。ちょっと、少々お待ちください。
○森坂計画班長
大変失礼をいたしました。問10の12項のふれあいランド、天王崎、北浦荘周辺の湖岸部におけるレクリエーション開発という部分につきましては、それぞれ天王崎、麻生町とか、北浦荘の北浦町とかというふうな表記を省きまして、霞ヶ浦、北浦湖岸部におけるレクリエーション開発ということで訂正をさせていただきたいと思います。
○横山会長
ただいまのご説明でよろしいでしょうか。
ほかにございますか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、異議がないようでありますので、新市建設計画策定にかかわるアンケートにつきましては、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、提案事項に移らせていただきたいと思います。
提案事項につきましては、一括して説明をし、最後に皆さんに質問を受けるというような形にしたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、事務局から次回の協議事項ということで今回提案をさせていただきます。
本日お配りをいたしましたA4縦の資料でございます。
まず、1ページをごらんいただきたいと思います。
農業委員会委員の定数及び任期の取り扱いについてということで、今回の協定項目につきましては、合併特例法の中に在任特例の規定がございますので、その在任特例を使うのかどうかということについてのご協議ということでございます。
内容的なもの、説明をまずさせていただきたいと思います。
1、農業委員の任期等の取り扱いということで、中段のところになりますが、原則といたしましては、町の廃止に伴いまして、すべての委員、農業委員については選挙による委員、それから、選任による委員がございますが、両者とも失職をするというのが原則でございます。ただし、合併特例法による特例措置の規定がございます。選挙による委員のうち合併後の新市の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、10から80人の範囲で、合併後1年以内で協議により定める期間在任することができるというものでございます。
なお書きしてございますが、選任による農業委員につきましては、合併特例法による特例措置の規定は設けられておりません。
米印の方をちょっと確認いただきたいんですが、「上記は、新設合併で合併市町村に一つの農業委員会を置く場合です」ということでございます。なお、農業委員会等に関する法律3条第2項におきまして、市町村の区域を2以上の区域に分けて農業委員会を置くことができる規定がございます。次の2ページの中段の部分がそれに該当するわけでございますけれども、その区域の面積ですから、新しい市の面積が2万
4,000ヘクタールを超える市町村、またはその新しい市の農地の面積が 7,000ヘクタールを超える市町村につきましては2つ以上の区域に分けて農業委員会を置くことができるということになりますが、今回の3町合併によりましては面積要件に該当がされませんで、これを適用することできないということになりますので、今回の農業委員会の設置につきましては一つの農業委員会とするというような形になるところでございます。
2番に、現況等ということで、現在の各町の農業委員さんたちの定数、そして、減員数をこちらの方に載せさせていただいてございます。それぞれ麻生、北浦、玉造でこのような数になってございます。現在数で申し上げますと、麻生町が20、北浦町が22、玉造町が20ということで、選挙、選任合わせまして、3町で62名いらっしゃるということでございます。
なお、先ほど在任特例ということを申し上げました、対象になります選挙による議員さんの数につきましてはこちらの方にございますが、現在47名いらっしゃるということでございます。
その下が、区域の面積、そして、農地面積、基準農業者数ということでございます。参考にごらんいただきたいということでございます。
続きまして、2ページでございますが、先ほど現況の最初のところでちょっと申し上げました合併特例法による特例措置の規定が、こちらの方、2ページの一番最初に載ってございますので、後ほど必要に応じてごらんをいただきたいということでございます。
そのほか、中段以降は、農業委員会等に関する法律の抜粋ということで、関係するところを載せてございます。3ページ、4ページにまたがりまして、選挙による委員の定数の上限の考え方、それから、選挙の単位の問題、そして、34ページにいきますと、境界変更の場合の特例ということで、これは、複数置く場合ということだと思いますけれども、載ってございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。
5ページにつきましては、1年前からの合併事例の主なもの、代表的なものという形で載せさせていただいております。こちらの方で、原則どおりにしたのが2つということでございまして、ほとんどの自治体で在任特例を採用しておるというような状況でございます。期間についてはそれぞれということでございまして、後ほどごらんをいただきたいと思います。
そういうようなことを踏まえまして、今後の協定項目の中では、冒頭申し上げましたように、在任特例を使うのか、使わないのかということをご協議いただくというものでございます。
なお、今回ご提案を申し上げるわけでございますけれども、農業委員会の事務を現在の3町で行っている事務から一つの事務という形で移行する観点から、各町の農業委員会に円滑に事務を移行するためにどういう形がいいのかということについても整理をお願いして、その考え方を踏まえまして、この協議会の中でご協議をいただきたいと、そういうことで考えておりますので、場合によって、農業委員会さんの方の整理が次回までに間に合わないことも場合によって考えられるかと思いますが、その場合にはその次の会へ持ち越させていただくということで、今回の提案ということでご理解をいただきたいというふうに思います。
○永峰総務班長
続きまして、事務局の永峰と申します。
提案事項の2番といたしまして、慣行の取り扱いをご説明申し上げたいと思います。
まず、現況といたしまして、お手元の6ページの資料にございますように、町章、町民憲章、町の花、町の木、町の鳥の制定状況が記してございます。町章においては、それぞれの意味を込めてそれぞれ制定されているというところでございます。また、町民憲章においても、まちづくりを進める憲章として、ごらんのようにそれぞれ制定がなされております。そして、町の木、町の花、町の鳥がそれぞれ制定されており、一部同じ内容のものもございますが、それぞれの町において、それぞれの考え方によりこのように制定されているということでご理解をいただきたいと思います。
このような中で、新市においての調整方針でありますけれども、調整方針の案に記してありますように、市章、市民憲章、市の花、木、鳥等は、新市において調整をするということでご提案でございます。考え方といたしましては、新しい市が発足後、検討組織なりそういう組織を設けることや、住民の意向をそれぞれ反映させながら制定をしていくということでの調整になろうかと思われます。
なお、参考といたしまして、7ページ以降に先進事例を掲載してございますので、こちらをご参考にごらん願いたいと思います。
以上、慣行の取り扱いについてのご説明とさせていただきます。
○阿部書記
事務局書記の阿部でございます。よろしくお願いいたします。
資料の方、9ページをごらんいただきます。
提案事項3)、協定項目21番、介護保険事業の取り扱いについてご説明申し上げます。
まず最初に、介護保険制度について若干ご説明いたします。
資料の方は、13ページをお開き願います。
介護保険制度でございますけれども、社会の共同連帯の理念に基づき運営するものであり、65歳以上の高齢者全員と40歳以上の医療保険加入者はすべて加入することとされております。被保険者の部分でございますが、介護保険においては、被保険者を第1号被保険者と第2号被保険者に区分しております。第1号被保険者につきましては、65歳以上のすべての方が対象となっております。第2号被保険者におきましては、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象となっております。保険料の算定でございますけれども、第1号被保険者におかれましては、市町村ごとに算定された所得段階別保険料となっております。第2号被保険者におかれましては、全国一律の単価に基づいて算定され、医療保険料と一括して納付しております。この介護保険事業の取り扱いについては、町村が算定し、保険料を決定する第1号被保険者についての調整をするものでございます。
それでは、資料の方、9ページにお戻りいただきまして、3町の現況でございます。
平成16年4月1日現在の被保険者人口、第1号被保険者数でございますけれども、麻生町 4,111人、北浦町 2,720人、玉造町 3,356人となってございます。続きまして、平成16年4月1日現在の施設入所者数でございますけれども、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群でございまして、その合計でございますが、麻生町が
102人、北浦町が78人、玉造町が70人となっております。以下、高齢者人口比はごらんのとおりとなっております。
続きまして、10ページでございます。
保険料及び納付方法でございますけれども、まず、保険料でございますが、平成15年から平成17年度までの第2期市町村介護保険事業計画に基づいた基準額により算出した保険料でございます。ごらんのとおり、北浦町、玉造町におきましては同一でございます。麻生町におきましては、基準額であります第3段階の基準額に若干差異がございまして、第1段階から第5段階まですべて若干の差異がございます。
続きまして、納付方法でございます。第1号被保険者の納付方法には、年金年額18万円以上の方を対象とする特別徴収、それから、年金年額18万円未満の方を対象とする普通徴収とございます。この特別徴収は、老齢年金や退職年金から天引きされるシステムとなっております。普通徴収は、納付書で個別に納めるシステムでございます。第2号被保険者の納付方法でございますけれども、これは、医療保険料と介護保険料を合わせて一括徴収するシステムでございます。この納付方法につきましては、3町ともに同一でございます。
続きまして、納期でございます。納期につきましては、麻生町が本算定方式ということで、第1期が7月からということでございます。北浦町、玉造町におきましてはそれぞれ暫定方式を採用しておりまして、第1期が4月、第2期が6月、第3期から本算定ということでございます。第5期につきましては、北浦町が12月、玉造町が11月と若干の差異がございます。
なお、北浦町におきましては、年金の支給額と同じ偶数月が納期となっております。
続きまして、11ページをごらんいただきます。
認定審査でございますけれども、これにつきましては、申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、また、その範囲を審査、判定するものでございまして、その組織としまして認定審査会がございます。これは、3町ともに鹿行地方広域市町村圏事務組合介護認定審査会に委託しておりまして、同一でございます。
続きまして、市町村特別給付でございますが、これは、介護保険法に定める標準サービス以外のサービスについて、市町村が独自に行う介護保険対象のサービスでございます。これにつきましては、ごらんのとおり、麻生町、北浦町につきましては実施しておりません。12ページにも書いてございますけれども、実施してございません。玉造町のみの制度でございまして、紙おむつ等支給サービス、それから、移送サービスの2つを玉造町のみが実施しております。
なお、紙おむつ等支給サービスに関しましては、麻生町、北浦町それぞれ介護保険の中では実施しておりませんけれども、この米印に書いてありますように、高齢福祉対策で類似事業を実施しているということでございます。
続きまして、居宅介護支援事業所でございますけれども、これにつきましては、北浦町、玉造町に、それぞれ北浦町居宅介護支援事業所、玉造町に玉造町居宅介護支援事業所とそれぞれ設置されております。麻生町におきましては設置されておりませんが、こちらの米印にありますように、麻生町社会福祉協議会居宅介護支援事業所、朝霞荘、それから、白十字会、水郷医師会ということで、それぞれの事業所で同一のサービスを提供しているということでございます。
それでは、9ページにお戻りいただきまして、協定項目21番、介護保険事業の取り扱いについての調整方針案でございますけれども、1)保険料については、第3期介護保険事業計画に基づき、平成18年度から統一する。2)納期については、合併時に北浦町の制度をもとに統一する。3)認定審査については、現行どおりとする。4)市町村特別給付については、合併時に玉造町の制度をもとに統一する。5)居宅介護支援事業所については、合併時に新市の事業所を設置する。
以上、提案いたします。よろしくお願いいたします。
続きまして、19ページをごらんいただきます。
提案事項4)でございます。協定項目23番、電算システムの取り扱いについてご説明いたします。
現在、事務処理の迅速化や円滑化、あるいは正確さが求められる時代となっておりますが、効率的な行政事務を執行する上で、電算事務の整備、構築というものは大変重要でございます。特に、住民サービスに直結する事務については、ほとんどの業務に電算システムが導入されている状況でございます。合併における電算システムの統合、あるいはシステムのネットワーク化は非常に重要な問題でございまして、合併と同時に住民サービスの低下を招かないようなシステムを統合することが求められております。
資料19ページの方なんですけれども、3町の電算システムの現況でございますが、ごらんのとおり、電算業務を住民記録系と住民記録系以外の2つに大きく分けてございます。こちらの表のシステム名称の右側の欄に、丸、四角、三角の印がございます。これは、右下の米印にありますように、電算会社をそれぞれ示しております。空欄につきましては、現在システムが稼働していないものを指しております。それから、(単)とございますけれども、これについては単独処理業務ということでございますが、この単独処理というのは、パソコン1台、あるいは小さい規模のネットワークで業務を処理しているシステム、あるいは一括して電算会社に委託して業務を処理しているような、そういった形態のものでございます。
それから、19ページ、左側の住民記録系でございますけれども、これは、住民記録を基本に、住民票、印鑑証明の交付、税金の課税、徴収、国民健康保険や老人医療の管理等で、主に窓口業務などの住民サービスに大きくかかわる分野を処理する業務ということで、これは、合併と同時に円滑な運用が求められているところでございます。
右側でございますけれども、住民記録系以外でございますが、これは内部的な業務でございまして、主な業務システムとしましては、役場内の会計処理で行う財務会計システムや職員の給与計算等をする給与計算システム等でございます。この住民記録系以外のシステムについては、健康管理システムや下水道負担金システムのように、システムの形態、いわゆる電算会社が異なっている業務がございまして、これらについては、今後担当課、あるいは分科会等で十分な調整が必要でございます。
以上のような現況を踏まえまして、協定項目23番の電算システムの取り扱いについての調整方針案でございますけれども、電算システム業務については、合併時に電算システムを統合し、住民サービスの低下を招かないよう努める。ただし、単独処理業務において差異のあるシステムについては、新市において調整する。
以上提案いたします。よろしくお願いいたします。
○横山会長
ただいま1)から4)まで4項目にわたって提案事項を説明いたしました。
皆さんにご質問等があったならばお願いをいたしたいと思います。
塙委員さん、お願いします。
○塙委員
ちょっと確認をさせてもらいたいんですけれども、農業委員会の任期の取り扱いなんですけれども、原則的には合併時に失職ということなんですけれども、特例措置によりまして、選挙による方は特例、続けられると。それで、選任による委員については失職そのままということでよろしいのかどうか。
○横山会長
それじゃ、事務局より説明をお願いします。
○江寺事務局次長
今の塙委員からありましたとおりでございます。失職して、新たに選任をし直していただくという手続になろうかと思います。よろしくお願いいたします。
○横山会長 よろしいですか。
じゃ、酒井委員さん、お願いします。
○酒井委員
麻生の議長の酒井です。
確認しておきたいんですが、いわゆる議会とか農協とか共済とかの推薦の委員さん、その人は失職するということですが、そこでまた新たに選ばれればいいんでしょうけれども、今度は、新市の農業委員さんの推薦枠によっては、失職する人と、また留任できる人とが出てくると思うんですが、その辺のところは、定数はどのぐらいになるんですか。新市のいわゆる農業委員さん、いわゆる議会推薦とか農協、共済の推薦枠というのは、人数が、今、麻生、北浦、玉造各町村で持っているはずですが、それが新市でどれだけになるのか、それをちょっとお伺いしたいと思います。
○横山会長
それじゃ、事務局でわかっている範囲で答えてください。
○江寺事務局次長
説明がちょっと足らなかったので失礼いたしました。
資料の方をちょっとごらんいただきたいんですが、4ページをごらんいただきたいと思います。4ページの上から3行目の(選任による委員)ということで、ちょっと読んでみますと、第12条、市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならないということで、ここに、今ご質問がありました農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事各1名、それから、当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者5人以内ということで、こちらの方が法律で決まっておりますので、これをそのまま準用していただきながら選任の作業をしていただくということでお願いをしたいと思います。
○横山会長
そうすると、何人かよくちょっと……。漢字をよく読むからわからなくなってしまう。数字だけ言えばいい。
○江寺事務局次長
失礼しました。そうしますと、農協と共済で合わせまして2、それから、議会推薦が5人以内ということでございますので、最大7ということになると思います。
○横山会長
よろしいですか。
ほかにございますか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、提案事項の説明につきましては以上のとおりとさせていただきます。
委員の皆様には、次回まで十分検討していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
次に、議題の3でございますけれども、事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それから、事務局の方で、その他ということで2点ほどご説明を申し上げたいと思います。
1点は、前回、委員さんの方からこういう資料をということで、一応きょう基金の残高の15年末の見込み、それから、起債残高の15年末の見込み、それから、この程度でよかったかどうか、ちょっとうちの方で少し確認をとらせていただければということもあったんですが、主要施設の整備の状況ということで、それぞれA4が2枚、裏表になっておりますけれども、裏表で2枚、2ページ、それから、A3版1ページということで、合わせまして3ページをお配りをさせていただいてございますので、参考にしていただきたいと思います。
それから、もう1点は、次回第5回の協議会の日程でございますが、1回目の協議会でご説明を申し上げました6月10日ということで、6月10日、木曜日になりますが、午後2時から北浦町役場の大会議室ということで開催させていただきたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。
○横山会長
議題につきましては以上でございます。
顧問の先生方が、きょうは両先生お見えになっております。先生方から何かございますか。
(ありません)
○横山会長
香取先生、何かありますか。
(特にありません)
○横山会長
それでは、皆様方におかれましては、長時間にわたりまして慎重なるご審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
進行役を事務局の方にお返しをいたしたいと思います。ご苦労さまでした。
○菅谷事務局次長
長時間にわたりまして……。
○横山会長
ちょっと待ってください。
それじゃ、質問。じゃ、お願いします。
○大曽根委員
玉造の大曽根でございます。
伺わせていただきたいことがありまして、時間外で申しわけありません。
合併協議会も第4回を迎えまして、議論も白熱を増してまいりました。皆さん慎重審議、その回を増すごとに、会議の内容も重要性を増してまいりました。事務局の皆様には、会議録としまして記録がされていることと思いますが、その会議録の確認というか、承認というのはどのようになされておられるのかお伺いしたいと思いまして、お願いをいたします。
○横山会長
ただいまの質問に対しまして、お答えを願いたいと思います。
○江寺事務局次長
会議録でございますけれども、うちの方で常に閲覧をできるようにしてございます。それが1点でございます。それから、ホームページの方に会議録の方を載せさせていただいてございますので、恐縮ではございますが、もし何かございますれば、事務局の方へ何なりとご連絡をいただければありがたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○横山会長
どうぞ、大曽根委員さん、お願いします。
○大曽根委員
私素人なので、このようなことをお願いしてはどうかと思うんですけれども、このような重要な会議の会議録となりますと、やはりどなたかが承認というか、署名をして確認をするという方が方法としましては確かなものではないかと思うのですが、ホームページや合併協議会の報告書を見ますれば、それなりの会議の内容の流れについては知ることができますけれども、発言の細部にわたっての確認ということは難しいのではないかと思います。それにつきまして、きちんと会議録として詳細に記録されたものを発言した中でどなたか代表として確認するということも必要なことではなかろうかと、私素人ではございますが、思っておりますが、いかがでございましょうか。
○横山会長
ただいまの質問に対しまして、お答えをお願いいたしたいと思います。
○江寺事務局次長
それでは、会議運営規程の中にその旨盛り込んでいないということでございますので、次回その点を追加でというか、提案をさせていただいて、その中でご審議をいただくということにしてはいかがと思いますけれども、会長、いかがでしょうか。
○横山会長
ただいま次回の協議会で提案をして、それで、皆さんにご協議をいただいて、決定がなされればそのような状況にしてまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。
ほかにはございませんか。
磯山委員さん。
○磯山信也委員
麻生の磯山でございます。
本日の協議及び提案にはちょっと関係ないことなのでありますけれども、その他でございますので、ちょっとお伺いをいたしたいと思います。
例の合併特例法が一部改正になりました。それに伴いまして、今回も県の方から列席されているので、県の方にちょっとお伺いしたいんですが、先ほど個人的には少しお伺いしたんですが、国がこういうふうに動きました。我々の目指している合併は、まず金がありきではございませんが、合併に伴う合併特例法に基づく財政支援措置は継続されるわけでございますが、合併特例法に基づかない県の財政支援措置があるわけでございます。国の動きに関しまして、今、茨城県はどういう動きが始まったのか。それをとらえて実際に動き始めたのか。これからどんなふうに動いていくとすれば動いていくのか。その辺をご質問させていただきたいと思います。
○横山会長
それじゃ、県の方でお答えをお願いいたしたいと思います。
○岡田委員(藤咲委員代理)
それでは、お答えしてまいりたいと思います。
冒頭、会長さんの方から、5月19日参議院を通過したということでございまして、これに先立ちまして、先立つといいますか、一昨年の話なんですけれども、県議会の中で、やっぱり国の動向という部分のご質問がございました。国は、そういうことで今継続する方向でありますよというふうなご回答をしたほかに、知事に対して、県のじゃ支援措置はどうするんだというようなご質問があったわけでございます。そのときの県知事の回答は、国がそういうような方向性を示せば、県としては支援の継続する方向で対応していきたいと、こういうようなご回答をしたことがございます。そういうことで、それを受けまして、実は、それぞれの協議会さん、いわゆる合併を進めている協議会さんに対する支援というのは、県の合併支援プランという、そういうプランがございます。その中に、人的な支援とか、それから、財政的な支援というのが盛り込まれております。そこが、今現在の支援プランを持っている内容は、17年3月までに合併した市町村まで対象ですよということをうたっていますので、これが、1年間国の方の動向が延びるわけでございますので、ここの部分の規定を変えるというふうな作業を今からしようかなと、こう思っております。つまり、県といたしましては、国の動向を踏まえまして、県の財政的な支援は継続する方向で取りまとめていきたいと、こういう考えでございます。
以上でございます。
○磯山信也委員
その決定の時期は、今のところ未定ですか。
○横山会長 どうぞ。
○岡田委員(藤咲委員代理)
これは、あくまで事務的な今お話をしましたので、最終的には議会関係でもご了解をいただかないとできませんので、基本的には事務局サイド、いわゆる執行部サイドとしては、県知事も含めてそういう方向であるということでございます。
○横山会長
ほかにありますか。
(発言者なし)
○横山会長
それじゃ、ないようでありますので、事務局にお返しをいたしたいと思います。
○菅谷事務局次長
長時間にわたりまして、慎重なるご審議ありがとうございました。
以上をもちまして、当協議会の会議はすべて終了をいたしました。
それでは、最後に、閉会の言葉を当協議会の副会長でもあります玉造町長の坂本副会長にお願いします。
○坂本副会長
本日は、長時間にわたり慎重協議をご苦労さまでございました。
本日は、何か天候の方も不順で、この会場蒸し暑かったかと思いますが、本当にご苦労さまでございました。
先ほど話し合ったとおり、国の法定期限が緩和されたというか、そういう形が出ているので、早く県の方でもこういう形をしっかりしたものを見せていかないと、やはり期限がこの一番重要ポイントというか、そういう形で進まなくてはならないわけですから、そういう点でも、今から皆さんともそういう形で、この期限を注目しながらそういう形で進行していきたいと思います。
本日は、長時間にわたりましてご苦労さまでございました。
これにて第4回合併協議会の協議会を終了させていただきます。
本日はご苦労さまでございました。
どうもありがとうございました。