●日時:平成16年5月12日(水)午後2時から4時6分
●場所:レイクエコー「大研修室」
●あいさつ
●議 事
(1)協議事項
1) 新市の事務所の位置について
2) 財産の取扱いについて
3) 議会議員の定数及び任期の取扱いについて
4) 新市建設計画の策定方針(案)について
(2)提案事項
1) 一般職の職員の身分の取扱いについて
2) 特別職の職員の身分の取扱いについて
3) 公共的団体等の取扱いについて
4) 新市の名称について(継続)
・新市名称候補選定基準(案)
・新市名称募集要項(案)
・新市名称候補の選定に係る小委員会の設置(案)
5)新市建設計画策定に係るアンケートについて
(3)その他
● 出席委員(32名)
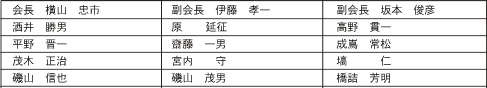 |
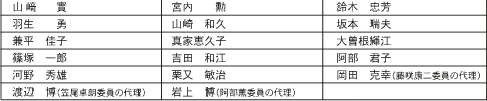 |
●欠席委員(1名)
大川 久子
●出席顧問
香取 衛
○羽生事務局長
それでは、大変お待たせをいたしました。ただいまより第3回の行方郡合併協議会を進めさせていただきたいと思います。
本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございました。本日の司会を務めさせていただきます事務局の羽生でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
始めに、副会長でございます坂本玉造町長さんより開会のごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○坂本副会長
皆さん、改めましてこんにちは。
本日は、行方郡合併協議会の第3回目の協議会をご案内申し上げたところ、皆さんお忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。
これより第3回の協議会を始めたいと思います。よろしくお願いします。
○羽生事務局長
それでは、会長でございます横山麻生町長よりごあいさつをお願いいたします。
○横山会長
本日は、大変お忙しい中、第3回行方郡合併協議会にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
また、厳しい開催スケジュールにもかかわらず、ご理解をいただいておりますことにつきましても改めて心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。
さて、当合併協議会の進め方につきましては、前回の協議会でお話をさせていただきましたように、提案がありました次の協議会において決定をしていただくようお願いをいたしておるところでございます。ただし、委員の皆様方の意見が食い違う場合におきましては継続協議といたしたいというふうに思っております。議論を尽くしていただきたいというふうに考えているところでございます。
また、協議会へ提案いたします調整方針の案につきましても、必要なところは伊藤副会長、そして坂本副会長とも調整をいたしまして、お互いに納得できる内容であるよう努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
本日協議をしていただく財産の取り扱いについても、これまでの各町の経緯等を踏まえまして基金の取り扱いにかかわります内容を盛り込ませていただいたところでございます。
可能な限り委員の皆さんの総意による協議でありたいというふうに考えておりますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いを申し上げたいと存じます。
本日の協議事項でございますけれども、新市の事務所の位置、財産の取り扱い、議会議員の定数及び任期の取り扱い、新市建設計画の策定方針(案)を予定をいたしております。
皆様方には忌憚のないご意見を賜りまして、円滑な協議ができますようよろしくお願いを申し上げまして、私のあいさつにかえる次第でございます。
本日は委員の皆さん、まことにご苦労さまでございます。よろしくお願いいたします。
○羽生事務局長
ありがとうございました。
それでは、早速議事に移らせていただきたいと存じます。規約第10条第2項の規定によりまして横山会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと存じます。会長、よろしくお願い申し上げます。
○横山会長
それでは、規約に従いまして議長を務めさせていただきますので、ご協力のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思います。
なお、本日の出席委員でございますけれども、32名でございます。協議会規約第10条第1項の規定によります定足数に達しておりますことをご報告申し上げたいと思います。
それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきたいと思います。
まず、協議事項の1)、新市の事務所の位置についてを議題といたします。
資料につきましては、前回説明をいたしましたが、ここで改めて事務局から説明をお願いいたしたいと思います。
事務局、よろしくお願いいたします。
○江寺事務局次長
事務局の江寺でございます。よろしくお願い申し上げます。
前回お配りをさせていただきました資料でございますので、ごくごく簡単におさらいの意味で説明をさせていただきます。
事務所の位置につきましては、最終的にはどこにするんだということ、具体的にご決定をいただくということになりますけれども、その前段といたしまして、事務所、新しい庁舎をつくるのかどうかということ、それからつくるとすれば、それまでの暫定的な条例上の事務所の位置をいずれにするのかということ、そしてつくらないとすれば、最初から現在の庁舎のどの庁舎になるのかということをご決定いただくということになろうかと思います。
なお、事務所の設置形態につきましては、前回の資料の1の2ページの方に具体的な方式といたしまして3方式、本庁方式、分庁方式、総合支所方式を挙げさせていただいたところでございます。
それから、3ページの方に検討シートということで、おおむねの検討の流れというのを考えればこういう形になるのかなということを書かせていただきましたけれども、おおむねは冒頭申し上げましたように新しい庁舎をつくるのかつくらないのか、つくるとすれば、それまでの事務所の位置をどこにするのかということをご決定いただくということ。つくらないとすれば、どこに事務所位置を選ぶのかということをご決定いただくということでお願いをできればというふうに考えております。
なお、ある委員さんの方から、新庁舎の場所・位置をこの協議会の中で具体にもう決めてしまうのかというようなご質問が寄せられたところでございますけれども、基本的には、今申し上げましたようにつくるのかつくらないのか、そしてつくるまでの間の暫定的な事務所の位置をどこにするのかという方向でご議論をいただければということで考えております。
正式には、新市の中でこれは時間をかけて決めていくような内容なのかなというふうにも思いますが、また皆様方のご意見をいただきながら、その点ご協議いただければというふうに考えております。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
事務所の位置を決定したいということでございます。
まず、この新庁舎を建設すべきか否かという点から協議に入りたいというふうに思います。いわゆる新しい新庁舎を建てるのか建てないのかを皆さんと議論をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
宮内委員さん。
○宮内守委員
どうもご苦労さまでございます。
今、会長さんの方からお話ありました新庁舎を建設すべきか否かということでございますが、北浦町の合併調査特別委員会の中の議論の集約といたしましては、速やかになるべく早く新庁舎を建設してということでございます。それはどういうことかといいますと、やはり今回の合併の目的というか、なぜ合併をするんだろうということの原点に返りますと、やはり節約というか効率的な行財政ということの集約のためにということでございますので、速やかに庁舎を建てて、そして移行していくということがいいのではないかということで北浦町の方では議会の方で集約をさせていただいたところでございますので、ご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○横山会長
ありがとうございました。
ただいま北浦の宮内委員さんの方からご意見が出ました。
ほかにありませんか。
玉造の橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
玉造の方では、本庁方式ということよりは総合支所方式、これの方がよろしいんではないかと。と申しますのは、住民にとりまして本庁舎であるということになると、どうしても距離的な問題、また住民サービスからすれば今までの庁舎を利用して、今までのなじみのところで十分用が足せるんであれば、地理的に遠くなるところへ行くよりははるかによろしいんではないかと。また、庁舎間の連絡も、今、ペーパーレスの時代でございまして、パソコン、電子メール、そういうもの等で玉造町も四千五、六百万の予算で庁舎間を連絡しているところでありますので、住民サービスもそういうものを利用することによって低下をすることなくできるんではなかろうかと。
まして今のご時世ですから、民間においては本社機能というものをむしろ廃止して、やはり現場というところに密接したところへ重点的に配備していかなければ、本来の住民に対する福祉・サービスが劣るんではなかろうかというような観点から、合併特例債についてもそういうようなものよりはもうちょっと身近なものに振りかえていった方が得ではなかろうかと、そういうような考え方から、総合支所方式ということが玉造町としては、今の段階はですよ、これは将来的にはわかりませんが、ましてその大きな一つの理由は、これ人口が4万人規模ですから、本来の合併規模になりますと10万人規模ぐらいになればまた話は別でしょうが、4万人規模でやるのであれば、今の庁舎をそれぞれ活用して運営していった方が本来のサービスの低下にはつながらないだろうと、こういう理由もあります。
以上であります。
○横山会長
ありがとうございました。
玉造町の橋詰委員さんからのご意見でございました。
ほかにございますか。
宮内委員さん、お願いします。
○宮内勲委員
北浦町の区長会長という代表で来ているわけですけれども、区長会長の声ではありません、私個人の考えですけれども、やはり合併となっては、本庁というシンボルになるものはいずれにしても必要かと思います。今というわけにはこれはなかなかいかないかもしれませんが、本庁は必要だということです。先ほど玉造さんの方から総合支所という方式がありましたが、その移行期においてそのような総合支所、当然なるかと思うんです。
2番の分庁方式は、これ住民にとって大変な暇と労力が必要になってくるかと思うんですが、例えば北浦の支所で受け付けられるものが麻生まで行かなくてはならないとか玉造へ行かなければできないとかいうような住民に不十分なことが出てくるんじゃないかというような懸念がするわけですが、いかがなものでしょうか。
以上です。
○横山会長
ありがとうございました。
ほかに麻生の委員さん方。
茂木委員さん、お願いします。
○茂木委員
麻生の茂木と申します。ご苦労さまでございます。
私としては、やはり分庁方式ということで考えております。
あと住民サービスである町民課とかこの問題に関しましては、やはり各分庁へ設置し、また、ただいまちょっと話がございましたように住民サービスというようなことも確かに低下するかと思いますけれども、やはり今は車社会であり、その辺はそんなに心配なされなくても大丈夫かなというように考えております。
また、将来はやはり本庁を建設いたしまして、将来は新市の建設計画の中にどこへ本庁をつくるかということはこれから計画して、新市の庁舎計画の中で決定した方がよろしいかと思います。
以上です。
○横山会長
ありがとうございました。
これは意見がかなり分かれているというようなことでございます。
協議会の執行部といたしましては、皆さんの意見をきょう初めて聞いたわけでございますけれども、この新しい市庁舎、これを建設するかしないかをまず議論しなくちゃいけない。それで、仮にしないとなれば、3町の今の役場の中でその事務所の位置、いわゆる代表を1つ選んで、そこで事務所の位置を決める、確定すると。建設をするということになれば、建設するまでの間、この3町の中から1町の事務所の位置を確定するということになろうかと思います。
ですから、これ議論の初めで、するかしないかということで今つまずいちゃったわけなんですが、これは次の段階には進めません。ですから、どうでしょうね、事務局で何かお話ありますか。ないですか、特別は。
じゃ宮内さん。
○宮内守委員
先ほど会長さんからお話あったように、新庁舎を建設するか否かというお話だったものですから、庁舎の方式までというお話ではなかったんですが、玉造、麻生の方から、建てる建てないを飛び越して分庁だとか総合支所だとかというお話があったんですが、今、改めて会長さんの方から説明があったように建てるか建てないかという話で私先ほどしたんですが、方式という話になれば、うちの方もそういう議論も一緒にセットでお話はしてありますので、それなりにお伝え、北浦町の意見もしなきゃならないのかなとは思っておりますが、建てるか建てないかというのは、やはり、先ほど申しましたようになぜこれ合併するのかという原点ですね、そういうことをご理解いただいて、住民サービスが低下するというお話もありましたが、図面を見ていただいてもわかるように3町合併すると役場庁舎は全部端々ですね。どれくらい庁舎建設費がかかるか、いろんな資料とかあるかと思いますが、職員の定数の問題も絡まってくると思いますが、やはり新庁舎がどのくらいかかる、職員の数を減らす、議員、いろんなものが減ると言っているわけですが、そういう中で庁舎を建てるコストを整理して、やはり新庁舎建てるべきと、早期にですね。そして、その間は、我々とすれば、いわゆるこれ合併というのは節約目的ですから、いろいろ知恵を働かせていかなきゃならないのかなと思いますが、節約を住民に向けてあれするのには、その間は分庁方式という中で、底辺のサービスはそれなりに窓口サービスできると思うんですね、それはいろいろ検討しなきゃならないところあると思いますが、そういうふうに北浦では建てる計画で進んだ方がいいんではないかということで再度申し上げておきます。
○横山会長
ありがとうございました。
会長の方から皆さんにちょっと提言をいたしますけれども、この合併の特例法なるその合併支援措置ですか、これを利用するのには、この協議会で市庁舎を建設するかしないかをまず決めてもらわないと、この建設計画の中に取り入れられないという1つの課題がございます。
この建設をするかしないか、これは大きな問題なんですけれども、その建設をするかしないか、じゃするのにはどこの位置がいいのか、いつごろがいいのかというのが、これ新しい市が誕生してから新しい執行部で多分我々の意向、この協議会の意向を取り入れてくれながら建設に向かって委員会等をつくってやると思うんですよね。ですから、やるかやらないか、そしてこの合併の特例を使うか使わないかということもそこに踏まえて建設計画に入れるということなので、これやるところとやらないところができちゃうと議論がかみ合わない。ですから、これは玉造町さんではあれですか、合併特別委員会の集約等々やってきたんですか。
それじゃ、これは最初からなんですけれども継続審議にしたいと思います。継続にしないと、ここで結論は出ないと思いますので、継続審議ということで次の段階でその決定をしてまいりたいというふうに思いますので、これは3町とも真剣によく、いわゆる事務局側にいろいろな質問をしながらその勉強をして決定をしていただいていきたいというように思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
続きまして、その新庁舎の建てるか建てないかが決まらないと新しい事務所の位置、いわゆる3町の事務所の位置というものがなかなか議論に入りづらいということなので、これも継続審議にしたいというように思います。ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。
これにつきまして、事務局から何かつけ加えることございますか。
もっと私が説明したより、あなた方の方がより詳しく説明ができると思いますので、これ大事なことですから、ひとつ3町の委員の皆さんによくわかるように説明をお願いいたしたいと思います。
○江寺事務局次長
それでは、今、会長さんの方から説明ということでありましたが、基本的には資料のとおりがまず1つ、ご説明のポイントでございます。
それから、いろいろ今、庁舎建設についてご議論がありました。それについては、先ほど合併の目的が何なのかというお話があった、それがまず1つのポイントだと思います。
それから、それを踏まえて、また住民サービスという点をどうするのかということも当然出てくるんだろうと思います。これから住民の方々にいろいろ行政サービスを提供していくというあり方がまたこれまでのあり方とは若干我々も違っていかないとならないのかなという我々行政サイドの思いもございますけれども、基本はやはり3町の代表でありますこの委員の方々にその点を踏まえてご検討いただくということになるのかなというふうに思いますので、その点をまた考えていただいてということをお願いしたいと思います。
それから、あともう1点は、合併特例債の問題が出てまいりました。庁舎をつくるのにかなりの費用がかかるということも当然考えられることであります。ただ1点、これはよくご審議をいただきたいというのが、庁舎の今の建設年次、経過年数が今どれだけであって、例えば既存の庁舎をこれからどの程度、何年間使えるのか、何十年間使えるのかということもまた一つポイントになってこようかなというふうにも思っております。
それらの点、合併の目的、それから住民サービス、そして庁舎のこれからどのぐらい使っていくのか、使えるのかということも踏まえて考えていただきたいなというふうに思っております。
ちなみに、前にもお話をさせていただきましたけれども、庁舎建設についての補助事業というのはございませんので、唯一他から支援を受けられるとすれば合併特例債があるよというようなことでございます。ただ、合併特例債で建設するという場合でも、かなりの年数をかけて各自治体検討されておりますので、この協議会で例えばつくるという結論を出しても、2年、3年ででき上がるものでは多分ないであろうなというふうに思いますので、それらの周辺の協議会、新しく合併をしてできた合併市町村の状況もそういう状況がありますので、それらも参考になさっていただきたいなというふうに考えております。よろしくお願い申し上げます。
あと事務局の方へこういう資料欲しいということありますれば、会長からもありましたように我々でできるだけの資料整理、提出させていただきますので、その点は何なりとご指示いただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○横山会長
ただいま事務局より説明をいたしましたけれども、これに対して何か聞きたいことありますか、せっかくの機会ですから。この次の協議会で何とか目鼻をつけたいと思いますので、わからない点があったらどんどん聞いてください。
どうぞ。
○大曽根委員
玉造の大曽根と申します。
質問をさせていただきたいのですけれども、私、ちょっと素人なものですから理解不足なところがありまして申しわけないのですが、ただいま会長さんの方から合併特例債のことについて、庁舎を建てるというような計画が立てられないと合併特例債の中に組み入れられないとか、いただけないような趣旨のことのように私は聞いたんですけれども、建てるというようなことを前提にしないと特例債の方はいただけないということで理解してよろしいんでしょうか。
○横山会長
建設計画に組み入れられないということで、これも事務局からもう一回よく説明してください。
○江寺事務局次長
会長が今申し上げましたのは、協議会の中でこれから建設計画というのをつくってまいります。その建設計画の内容についてはこの協議会の中で協議していただいた内容になるわけですけれども、建設計画の中に盛り込まれなかった事業については合併特例債の対象となりませんので、そういう趣旨で会長が今の発言をしたということでございます。ですから、この場で建てないということになれば建設計画の中にその文言は入りませんので。
ただ、全然建てられないということではなくて、合併後に変更をということもできますが、そういうのもなかなか現実的ではないのかなというふうに思いますので、会長が申し上げましたようにこの協議会でつくるのかつくらないのか、つくらないということの結論がもし出たとすれば、合併特例債を使うこと、なかなか厳しくなっていくのかなということだと思います。
以上でございます。
○横山会長
よろしいですか。
ほかにありますか。
齋藤委員さん、お願いします。
○齋藤委員
北浦の齋藤ですけれども、ただいまのお話の中で、説明の中で、二、三年の短期では庁舎建設ですね、無理だろうというような話もありました。早期といった場合に明確な時期ですか、それはどのぐらいが目安になるのかな。それがやはり今から出てくる設置方式、総合支所あるいは分庁方式、それのたたき台にもなるのかなと思いますので、ご説明をいただきたいんですけれども。
○横山会長
それで今の齋藤委員さんの質問でありますけれども、会長の方からちょっと1点だけ。合併の特例債は10年、皆さんもご承知のようにね。10年たったら終わります。いろいろこの協議会で計画をしたものを10年の間ずっと市になってからもやってもらうということだろうと思います。そして、当然、役所の市長、職員の削減もこのぐらいだということになっていこうと思います。10年間が非常に厳しい。引いても進んでも地獄と言われておりますけれども、この厳しい状況を乗り越えなくちゃいけないということだろうと思います。あとの細かい数字的な点は事務局より説明をさせますので、事務局、よろしくお願いします。
○羽生事務局長
建設計画の中に盛り込んだとして、建設がじゃいつごろなんだというような質問の趣旨かなと思いますけれども、今、会長が言われましたように10年という建設計画の期間、定めがございますので、その中でと考えた方が今の段階ではいいのかなというふうに考えますけれども、それ以上の細かい詰めについては、新市になってから、いろいろな審議会なりの中で具体的に詰めていかなきゃならないのかなというふうに考えます。したがいまして、今の段階では、その建設計画10年の中でというふうに考えておかざるを得ないのかなというふうに感じています。
○横山会長
齋藤さん、よろしいですか。
ほかにございますか。
磯山委員さん、お願いします。
○磯山信也委員
ただいまこの新しい庁舎につきましては継続審議ということで会長の方からあったわけでございますが、私もこの委員の1人といたしまして、新庁舎をまず第一番につくるべきかつくらないべきかについて私の意見を述べさせてもらいます。
私は、この3町が対等で合併をすることは基本的に決まっておるわけでございますし、当然ながら新庁舎はつくっていかなければならないと。ただし北浦さんの方から早急にというお話がありましたけれども、これはやはり早急にやることはいかがなものか。特例債の10年の間にやればいいんじゃないかと。その前段としては分庁方式でいくのが3町にとっても一番いい姿ではないかなと、私はそのように思います。
それから、玉造さんにおきましても、この現在の3つの庁舎の地図を見てもらってもわかるとおり交通体系そのものも今この3町をめぐる基幹道路もかかわっておりますし、合併は将来のためにやるものでございますから、そういう将来にわたります考えをご理解いただけたらなと私は思います。
それで、継続審議にはなりましたけれども、第一番にこの新庁舎をつくるかつくらないかの決定をしていかなければ次へ進めないと思うんですよ。それで来年の3月がタイムリミットでございますし、ここは早急じゃなくて合併特例債を受けられる範囲内で、また新たな機関を設けて検討するとしても、つくるということはここで決めるべきだと思います。継続審議になりましたけれども、次回までにはそういう点も含めてご検討をお互いにした方がいいんじゃないかなと、私の意見でございます。
以上です。
○横山会長
ありがとうございました。
ほかに。
橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
当面ですね、この西東京市、これは最近になって合併したまちだと思いますが、これは東京の保谷市と田無市、これが合併しまして西東京市になったと。それにつきましては、当面新市庁舎の建設は行わないと。でもなおかつ合併特例法は受けているわけですよ。ですから、この問題は後にもうちょっと譲って、それでも合併はできるわけだと思いますよ。ですから私はこの方式でやっていって、当面の問題です。それは前例として保谷市も田無市もそれで合併できているわけですから、西東京市という市に、ですから、それで私は十分だと思います。それで田無市は田無庁舎、保谷市は保谷庁舎というようにしまして、都市整備部とか教育委員会は保谷庁舎に配置したと。要するにこれは2つの行政体が1つになったにしても、これは新庁舎をつくらなかった。まして今度、行方3町の方が保谷・田無よりは地域的な面では広域ですよ。エリア的には広いです。距離的な間隔もあると思います。玉造なども南北に長いものですから、やはり住民のそれなりの同意を得るとか、新しい経過の中でこれは煮詰めてやっていただければ、一番住民に対して、拙速する必要は私ないと思います。これは課題として残していいと思うんですね。これは合併について私は差し支えないと思います。
それと、玉造の場合は、LAN工事が終わりまして、それぞれ各庁舎間は全部パソコンで連絡が行っています。そういうようなことで、麻生さんも北浦さんもどれほどそういうのが進んでいるかわかりませんが、そういうことが、1つのまちになれば、ますますそれは緊密になって十分可能だと思いますね。ですからその点で、今決定しなくて継続審議で私はそれでよろしいんではないかと思います。
○横山会長
つまりですね、橋詰委員さん、継続審議で、次の段階でもずっと継続でいくということでよろしいんじゃないですかという意見ですか。
○橋詰委員
そうですね。
新しくまた、これで合併できないというわけじゃないと思います。これは必須条件とは言い切れない思います。
○横山会長
理論的にはそうですよ。理論的にはそうですが……
○橋詰委員
前例があるんですから。
○横山会長
理論的にはそうですが、3町で心を一つにしないと、ばらばらではゴールインには達せないということですから、ひとつ、今度協議会がございますから、玉造町さんでもう一回特別委員会でよく審議していただいて、ひとつ議長さん、よろしくお願いします。
○高野委員
玉造町の議長を務めさせていただいています高野でございます。
今、麻生、北浦、玉造、るる建設に関しての意見が出ましたわけでありますが、すべてそれが全部そろわなければこうだという、今、橋詰委員の方から話でありますけれども、これは継続ということになりましたので、玉造町も皆様方の意向を尊重しながら、次のこの合併協議会までには腹を決めてこうしたいということでしてまいりたいと思いまして、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。
○横山会長
大変ありがとうございます。よろしくお願いをいたしたいと思います。
では、宮内さんだけ、1人ね、お願いします。
○宮内守委員
たびたび、すみません。北浦、早急というから、あしたあさってつくってちょうだいという、そういうふうに思われているかもしれませんが、そうではなくて、前5年くらいの間にというようなお話でございます。
それからあともう一つは、何回も言って申しわけないんですけれども、やはり行政というか、それはむだが多いというのが住民の目線ですね。その目線に立ってやはりこの合併をしていくということであれば、やはりそこら辺を理解していただいて、庁舎の問題も含めて議論していただきたいというふうに。
それから、私のところへ何でもちょうだい、何でもちょうだいといったら、全く今までと同じことですから、やはり犠牲も払いながらこの合併の課題をやっていかなければ成功しない、合併してよかったと住民の人に思われない。そういうように思いますので、その点もやはり、それぞれ思いあると思いますが、ご理解いただいて議論していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○横山会長
ありがとうございました。
大変皆さんにご議論をいただきました。そして、結果的には継続協議ということに決定をさせていただきました。この次の協議会では、さらに前進した議論をしたいというように思いますので、よろしくご協力のほどをお願い申し上げたいと思います。
続きまして、協議事項の2)でありますけれども、財産の取り扱いについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
続きまして、財産の取り扱いについて、簡単にまたご説明を申し上げます。
資料につきましては、前回お配りをしました資料の5ページになってございます。
調整方針の案でございますけれども、3町の所有する財産及び債務はすべて新市に引き継ぐというもの、それから基金については再編・統合を行い、新市において必要な基金を創設する。なお施設整備等に係る特定の目的に基金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするような調整方針でございます。
趣旨については、前回ちょっとご説明を申し上げましたので、説明は省かせていただきます。
なお、この下に3町の財産の概要ということを書いてございますけれども、これはあくまでも14年末の数字であるということ、それから、調整方針でご議論いただくのは3町が持っている財産、結局合併の日の前日に持っているものをみんなで持ち寄るのか、それとも各町で自由に処分してしまうのかと、端的に言うとそういうようなご議論になるのかなというふうに思います。この数字については変わりますということを前提にして、参考までに現在の財産の額がこういう残高になっていますよということでこちらの方は見ていただければよろしいのかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○横山会長
ただいま事務局の方から簡単にご説明をいたしました。
これにつきまして、皆さんのご意見を伺いたいと思います。
ございますか。
これは、調整方針の案がございます。前にやった5ページですね。これ、調整方針(案)のとおり決定してよろしいでしょうか。まだですか。
大曽根さん。
○大曽根委員
玉造の大曽根です。
決定というお言葉が出てきましたものですから、その前にちょっと、玉造町としてお願いしたいことを会長さんにお伺いしたいのですけれども、これまで玉造町においては極力いろいろな建物などを建てずに、長期的展望に立ちまして健全財政に努めてきたと私ども住民は聞いております。今回の財産等の資料を見ましても、玉造町は2町に比べまして公共的な施設などが大変古いように思いますが、新たな整備計画があることは聞いておりまして、施設の整備等につきましては大変おくれているように私自身も思っておるのですけれども、ここで今回確認させていただきたいことがあるのですが、調整方針(案)の2の「なお、施設整備等に係る特定の目的基金については、現行のとおり新市に引き継ぐ」となっておりますけれども、玉造町でこれまで統合幼稚園や中学校建設、文化財等整備のための基金は合併後もそれらの整備のために使われるということで理解してよろしいでしょうか。会長さん、ご回答をお願いしたいと思います。
○横山会長
ありがとうございました。
先般、町長さん方で協議をいたしました。これについて、今、大曽根さんが申しましたこと、事務局より説明させますので、よろしくお願いします。
事務局より説明してあげてください。
○羽生事務局長
事務局よりお答えしたいと思いますけれども、基金の中に、ごらんいただきたいと思いますけれども、10ページをお開きいただきたいと思います。
10ページの中に、上から4行目をごらんいただきたいと思いますけれども、学校施設整備基金、北浦町で残高が3億 7,211万 7,000円、さらにそれから5行ほど飛びますけれども、同じ北浦町さんでふれあいと活力に満ちたふるさと町づくり基金、さらに四、五行飛びますけれども、玉造町さんで玉造町文化振興基金1億
6,509万 2,000円ですか。それにその次の行の玉造町公共施設整備基金12億 6,861万 1,000円、これらについては、さっきお尋ねにもありましたとおり、このなお書き以降に言っていますのは、まさしく今申し上げました4つの基金については現行のとおり、その目的のとおり新市に引き継ぐんだと、そういうことでこのなお書き以降書いてありますので、よろしくお願いしたいと思います。
○横山会長 ちょっとつけ加えますけれども、新市に引き継ぐということは、玉造町さんがつくった基金でありますから玉造町のために使うということです。これご理解ください。新市が使っちゃうわけでありません。そのとおりです。そういうことでありますので。
○大曽根委員
ただいまのことで、玉造町のふるさと事業基金はその中に入っておりませんでしょうか。今はなかったものですから。
○横山会長
事務局より今説明をさせます。
○羽生事務局長
先ほど4つの基金の例は申し上げましたけれども、今のふるさと事業基金が施設整備基金であるかどうかというのがまだきちんと確認をとれていませんので、その辺を例として申し上げたものでありまして、今後さらにその辺はきちんと詰めていきたいなというふうに考えています。
先ほど申し上げました4つについては、なお書き以降の特定の目的の基金だよと、そういうものがあるよと。それについては新市にその目的に沿って引き継ぐんだよと、そういう例で申し上げましたので、今の該当の質問の部分がその中に含まれるかどうかというのはこれから検討してまいりたいというふうに考えます。
○大曽根委員
そうしますと外されるという可能性もあるということですか。
会長さん、いかがでございましょう。
○横山会長
目的をこれからよく玉造の町長さんと詰めまして、それが前に申し上げたような基金であれば、当然新市に引き継いでも玉造町のふるさと事業に使うということになろうと思います。ですから、そこはちょっとまだ事務局でわからないということでありますので、それは猶予していただきたいと思います。
○大曽根委員
なるべく、町長さんの方から申し入れがあるとは思いますので、よろしくお願いを申します。
○横山会長 わかりました。
もう一つ、はいどうぞ。
○大曽根委員
そのほかにもう1点お伺いしたいことがあるのですけれども、今の財産の取り扱いとはちょっと違うのかもしれませんが、玉造町には百里の自衛隊が近くにあるために騒音等の迷惑により周辺の地域住民のための道路や施設などの生活環境整備がされております。私自身も百里基地に大変近いところに住んでいるためにジェット機が飛ぶたびに騒音に悩まされているのが現状でありますが、今後騒音を受けている地域の迷惑料的なものとして防衛庁より入ってくるお金については、合併後もそれらの地域に使用されるものかどうか確認をさせていただきたいのですが、お願いをいたします。
○横山会長
それは、大曽根さん、当然の話で、あれは距離と今までの長い百里基地と玉造町さんの協議の結果、これはちゃんと線引きがしてあります。ですから、そのお金を例えば北浦の方の鉾田境のまた使うなんてことはございません。ですから、心配しないでこれは大丈夫です。
○大曽根委員
それは心配ないのですけれども、そちらにそのお金があるのだから、予算はそちらに回さないでこちらで使おうという、そういうことがなされるとちょっと心配なんですよ。そこを確認させていただきたいのですが。
○横山会長
それは新しい市長さんに聞いてください。それはわかりませんので、ひとつそこの辺はちょっとご勘弁を願いたいというように思います。
ほかにございますか。
(発言者なし)
○横山会長
先ほども申しましたけれども、財産の取扱いについては調整方針(案)のとおり決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでございますので、そのように決定をさせていただきたいと思います。
時間が大分たちましたので、ここで3時まで休憩をいたします。よろしくお願いします。
(休憩)
○横山会長
それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きたいと思います。
協議事項の3)でありますけれども、議会議員の定数及び任期の取り扱いについてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、きょうお配りした資料の14ページ以降でございます。ご協議いただく内容につきましては2点ございますという話をしていただきました。1点は合併特例法に基づく特例措置を使うのか使わないのか、特例措置につきましては定数特例と在任特例がありますという話をさせていただきました。
なお、在任特例をもしとるという場合ですが、まだ合併の期日が決まっておりませんので、この在任の期間につきましては法定協議会で議会の1年間のスケジュール、そして在任特例をとる趣旨ですね、議員さん方がこういうためにどれだけの期間、どれだけの期間と申しますよりも、いつまで、こういうスケジュールの中でこれとこれとこれを自分たちがやるんだということの中でご決定いただくのかなという、そういうような審議をされている協議会が最近は多いようでございます。
それからもう1点は、新市の条例定数につきましてご議論をいただくということでお話を申し上げたところでございます。参考までに県内の類似団体の条例定数を記載してあるところでございます。それを参考にしながら新市の定数、地方自治法の中に新市の人口に基づく上限数が決まっておりますので、それもあわせて念頭に置いていただいてご協議いただきたいということであります。よろしくご協力お願いいたします。
○横山会長
それでは、事務局からの説明が終わりました。
この協定項目では、合併特例法に規定する特例の取り扱いについて、あわせて新市議会の定数を幾つにするかということでございます。ご協議をいただくことになろうと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、皆さんにご意見を承りたいと思います。
この件につきましては、これ議員さんの身分のことでありますから、これは合併特例特別議会でいろいろ審議をしていただいたというふうに私ども理解をいたしているところでございます。それをひとつお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。
橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
玉造の場合は、ここにおります高野議長の提案もありまして、いろいろ揉めました。50日以内に選挙をやるということを強く主張されたんですが、ほかの議員さんにもいろいろ話しましたところ、難航した結果、在任特例2年間以内ということで一応玉造町の場合は合意を得たということを報告します。
定数は26以内ということでありました。
○横山会長
ありがとうございました。
2年以内と26人以内では法律どおりですが、結構です。
じゃ、磯山委員さん、お願いします。
○磯山茂男委員
北浦の磯山でございます。
ただいま玉造さんからご報告ありましたように北浦でも在任特例を適用したいという結論になりました。それは、我々議員が自ら新市のスムーズな橋渡しの役割を担うことも一つの責任であるというふうに結論づけて、北浦では在任特例を採択というふうにご報告します。
それと定数ですけれども、隣の潮来市さんがあるわけですけれども、全体で24というような数字が出されているわけですけれども、今回いろいろな、15ページに載っておりますけれども、形態の3番あるいは4番、5番についても20名というふうな数字も出ているわけでございますけれども、北浦でもきちんとした数字は自分たちのことですから出しませんでしたけれども、20ないし24でいこうというふうな話が出ました。よろしくお願いします。
○横山会長
ありがとうございました。
それでは、麻生町さんの方でお願いします。
○茂木委員
今、麻生の方でというような話でございます。
麻生の方も一応在任特例を使うということで、一応2年以内というような話は前に決めてあります。
それと議員定数に関しましては、やはり今、北浦さんの方からお話がございましたようにいろんな意見ございますので、20人から24名以内でもう1回継続審議させていただいて、もう少し審議したいと思います。
○横山会長
ありがとうございました。
それでは、3町とも各議会の代表さんの方からお話がございました。
ひとつもう1回、各町さんで協議をしていただいて、定数についてはきちんとした数字をすり合わせをしたいというふうに思います。それから、在任特例については合併の日取りがまだ決まっておりませんので、その合併の日取りが決まると同時にその在任特例の方も決定をしていきたいというふうに思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたしたいと思います。
それでは、次回まで継続協議といたしますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
次に、協議事項の4でございますけれども、新市建設計画策定方針(案)についてを議題といたします。
事務局より説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。
○江寺事務局次長
資料につきましては21ページから23ページになってございます。
前回も説明を申し上げましたが、策定方針ということで書いてございますけれども、作成する内容、概要ということで読みかえていただいた方がわかりやすいのかなというふうに思います。内容的には、「基本方針」、新しい市の基本方針とそれを実現するための「まちづくり計画」、具体的にはこういう事業を行っていくんだよということ、それから「公共的施設の統合整備」、そして「財政計画」の4つの柱となりますということを申し上げたところでございます。
それから、計画の期間につきましては、17年から26年ということで10年間の期間についての計画をここに掲げるものですということを説明を申し上げたものでございます。よろしくご検討をお願いします。
○横山会長
事務局からの説明が終わりました。
それでは、委員の皆さんからご意見を伺いたいと思います。
何かございますか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、新市建設計画策定方針(案)につきましては原案のとおり決定をさせていただいてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでございますので、そのように決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、提案事項に移らせていただきたいと思います。
提案事項につきましては、一括説明をし、最後に委員の皆様方からご質問を受けるということにしたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、資料の方、きょうお配りをさせていただきました第3回協議会の提案事項資料の方をごらんいただきたいと思います。
提案事項につきましては、5つほどご用意をさせていただいております。一般職の身分の取り扱い、特別職の身分の取り扱い、公共的団体等の取り扱い、新市の名称について、前回、公募方式をご決定いただきましたので選定基準、募集要項、そして小委員会設置に係る案でございます。そして、5つ目が新市建設計画の策定にかかわりますアンケートの実施についてのご協議でございます。よろしくお願い申し上げます。
まず、1ページの方からごらんをいただきたいと思います。
まず、一般職の職員の身分の取り扱いについてでございます。
調整方針載せてございますが、最初に、恐縮でございます、4ページの方をごらんいただきたいと思います。この調整項目につきましては、合併特例法の中に1つ重要な条項が載ってございますが、こちらの方を申し上げてからご説明をしたいと思います。
合併特例法の第9条でございます。「合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際、現にその職にある合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」そして、第2項といたしまして「合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分の取扱いに関しては、職員すべてに通じて公正に処理しなければならない」というふうに規定をされております。
したがいまして、現在3町にある一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぎなさいというのがこの第9条の第1項でございます。そして、第2項については、職員は公平でありますよと、そのように処偶してくださいというのがこの法律でございます。
これをもとに今回、ご協議と申しますかご確認をいただくという内容でございます。
それでは、1ページの方へお戻りいただきたいと思います。
ただいまのものを受けまして、今の3町の職員、一般職の職員の状況はどのようになっているかというのがこの資料の中段以降でございます。
まず、1といたしまして、職員の定数及び実員数ということで、16年4月1日現在でございますけれども、職員の定数、これは定数条例に基づく数字でございます。それぞれこのような数字で
209、 142、 171という定数に対しまして、実員数で 187、 139、 141というような職員数になってございます。
資料の方、お進みいただきまして2ページをごらんいただきたいと思います。
その今申し上げました職員ですね、一般行政職、それから技能労務職、教育職ということで分けた場合にどのような内訳になるかというのが2番の表でございます。
そして、3番の表につきましては、職員につきましては1級から8級という形で級が分類されておりまして、なおかつそこに主事から課長さんまでいろいろなポストが分かれておるということになってございます。それぞれ級、職に対する人数、3町別々にこちらの方に記入をしてございます。
ただ、この級につきましては、次の4の給与でご説明をちょっと申し上げますけれども、給料表にこれは該当するものでございますので、級が大きくなれば大きくなるだけ、また給料が高くなると申しますか、そういうような形になってございますけれども、また、この表の中でポストの設置、職の設置についても若干3町で違いがあるというふうに思います。例えば7級のところを見ていただきますと、麻生町につきましては課長職ということで載せてございますけれども、北浦、玉造さんにつきましては課長補佐以上の職ということで取り扱いされているようでございます。そんな違いがございますので、また後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
そして、3ページが給与でございますけれども、一般行政職の給料表につきましては、先ほどの表にもありました8級制をとってございます。それから技能労務職につきましては同様の技能労務職給料表ということで、3町で同様の給料の取り扱いでございます。そして、教育職につきましては、麻生町が教育職の給料表を設定してございますが、北浦、玉造町さんにつきましては一般行政職の給料表という形でございます。
それから、初任給の格付ということで、行政職の大卒、短大卒、高卒別の初任給の一覧を載せさせていただきました。大卒の格付が若干違っている点でございます。
それから、3)に手当を記載させていただいてございます。手当の種類というのは、こちらに書いてございますようにおおむね同じということでございますけれども、その中で管理職手当のパーセンテージの設定、3町とも課長、課長補佐という区分けもございましたけれども、それぞれの数字のところでございますが若干異なってございます。扶養、住居、通勤については3町同様のようでございます。それから、特殊勤務手当につきましては、その特殊勤務手当の中にいろいろな手当が設けられております。水道の業務手当だとか税務の従事手当だとか感染症の防疫、それからもろもろの手当がございます。それの種類が若干違っているものでございます。
そのほか、この中でございますと、管理職員特別勤務手当であるとか期末勤勉手当の役職階級別の加算割合等が若干違っているようでございます。それらのことを今後新市の中で調整をするということになろうかと思います。
その下は、一応給料ですね、おおむねの格差の目安になりますラスパイレス指数ということで、これにつきましては、職員の数等、給与の平均的なものを国のものと比較して数字で指標としてあらわしてある表ということでございますので、こちらの方も後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
それから、ちょっと参考のところに当協議会の構成市町村で構成する組合ということで書かせていただいてございます。ちょっとこれ参考までということで書いてございますが、これは合併協定項目に一部事務組合の取り扱いがございます。環境美化組合は3町で構成していますので、3町が合併すると一部事務組合という形がなくなりますので、一般的には新市に引き継ぐというやり方になろうかと思います。その他で、一部事務組合のまた別のところと一緒になるというのもあるのかもしれませんけれども、引き継ぐとなれば、その職員さん方の身分の取り扱いについても当然出てくるのかなというふうに思います。ほかの協議会において一般職の身分取り扱い方に含めている場合もございますが、まだ当協議会におきましては一部事務組合の取り扱いについてご協議いただいておりませんので、こちらの身分の取り扱いについてはその協定項目に譲りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上、そのような形で職員数それから職種の設置等、それから級等違いがありますよということで説明を申し上げまして、調整方針の案でございます。
まず、1でございますが、3町の一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐものとする。
2といたしまして、職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
そして、3番といたしまして、職員の職名及び職務の級、給与制度等については、他の自治体の例などを参考に調整し、統一を図るものとするというような調整方針でございます。
資料をお進みいただきまして、4ページが先ほど申し上げました合併特例法の抜粋と地方自治法上、一般職と特別職が、このように規定されているということの説明ということでこちらの方で載せさせていただきましたので、ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、特別職は法律上に規定されておりまして、それ以外の者が一般職だよということを言っておりますので、そういうようなものだということで説明書きを見ていただきたいというふうに思います。
それから、6ページから8ページにつきましては、他の合併事例における調整方針の内容でございますが、内容的にはただいまご提案を申し上げました調整方針とほぼ同じなのかなというふうに思います。
そのほか参考のところに載せさせていただきました一部事務組合等についても規定されているものがあるというような内容かと思います。
続きまして、9ページをごらんいただきたいと思います。特別職の職員の身分の取り扱いについてでございます。
特別職の身分の取り扱いについては、ただいま説明いたしました一般職の方に特に引き継ぐ等の規定は当然ございませんので、すべて新設合併でございますので職は失うというような形になるというのが原則でございます。この中で、合併特例法に新設合併において特例措置が盛り込まれているのが議会の議員の方の身分の取り扱い、そして農業委員会の選挙による委員さん方の身分の取り扱いについて若干の特例措置が設けられてございますので、そちらにつきましては別途の協定項目の中で取り扱いを協議させていただくというような内容になってございます。
まず、こちらの現況等の表を見ていただきたいんですが、まず常勤の特別職として、1)でございます。教育長さんにつきましては一般職という形でございますが、通常の一般職とは異なりますのでこちらの方に載せさせていただいています。それから、議会議員さん方の関係、そして3)に行政委員会というふうに書いてございます。こちらの3)につきまして後ほどご説明申し上げますが、地方自治法の中でこの委員会については設けなければならないというように規定をされている委員会でございます。それがこちらの方に6つ書いてございまして、最後の※の公平委員会につきましては共同設置という形で処理をいたしておるという内容になっています。
10ページをごらんいただきたいと思います。
そのほか各町の条例に基づきまして各種委員会等を設けてございます。これらについてこちらの方に載せさせていただいてございます。それがおおむねその現況の表ということですので、後ほどこちらの方ごらんをいただきたいというふうに思います。
今、ご説明を申し上げましたが、4つの大きなくくりがございますけれども、それらに対します調整方針の案でございますが、特別職の職員等については、その設置人数、任期等について法令等の定めるところに従い調整をするということ、それから法令等の定めがない場合は新市において必要に応じて新たに設置をするということでございます。
個別に調整の具体的内容をごらんいただきますと、まず常勤の特別職でございますが、常勤の特別職の設置等についての法令の定めるところによるということで、報酬の額は、現行報酬額をもとに合併時までに調整をするというような内容になってございます。
それから、2)の議会議員でございますが、これにつきましては別途協議のとおりということで、別途の協定項目でございます。報酬の額については、現行報酬額をもとに合併時までに調整をするというような内容でございます。
それから、先ほど申し上げました地方自治法に規定する行政委員会でございますが、その委員の数、任期は法令の定めるところによるということ、それから報酬の額は現行報酬額をもとに合併時までに調整をするという内容でございます。
そして、10ページのその他の主な特別職、各種審議会等でございます。その他の条例で定める特別職については、現在3町とも設置されており、新市において引き続き設置する必要があるものは原則として統合し設置をするということ。2町または1町のみに設置されているものは、その必要性を判断して新市において設置をする。委員数、任期、報酬額等は現行の制度をもとに調整をするというような内容でございます。
続きまして、13ページをごらんいただきたいと思います。
先ほど法律で定めるところによるというようなことでご説明申し上げましたけれども、若干その部分で補足説明でございます。新設合併ということで、市長さん、首長さんの取り扱いですけれども、合併日の前日に町長さんが失職されますので、新しい市長さんについては合併の日から50日以内に選挙により選出するということでございます。
2番に書いてありますのは、その不在期間どうするのかということで、新市誕生から新市の市長さんが選出されるまでの期間については、職務執行者というものを選んで、その方が、通常言っている職務代理者的な形になりますけれども、市長業務をつかさどるであろうということになります。ですから、新市が誕生して必要な条例であるとか、新市が誕生して必要な暫定的な予算であるとか、そういうものにつきましてはこの職務執行者の方が最初に取り扱いをされるというような形になるということでございます。
そして、助役さんにつきましては、新市長さんが選出をされてから、議会の同意を得て選任されるというような取り扱いになっています。
そして、収入役さんにつきましては、正式に選任されるまでの間、代理の方を選ぶという取り扱いになっております。
それから、教育長さんの取り扱いについて、これも前日に失職しますが、これは合併したとき最初の教育長さんについては、教育委員会の委員さんが議会の同意を得て任命されるわけですけれども、それまでの間、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の規定によりまして、臨時に選任されました教育委員さん方の互選により決められるという取り扱いになるというようなことでございます。
その下に教育委員会、その他の行政委員会の委員さんの取り扱いが載ってございますけれども、暫定的な取り扱いは規定されていないものがございます。監査委員さんなどについては、議会で新市長招集の最初の議会において条例で委員数を定めて選任されるまでの間、不在というような取り扱いになるよというような暫定的な取り扱い、の規定はされていないということでございます。
後ほどこれらについてはごらんをいただければということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
そして、14ページから19ページにつきましては、その取り扱いに関する根拠法令の抜粋になってございますので、必要に応じて後ほどごらんをいただければというふうに思います。
20ページから24ページが先進事例の取り扱い、調整方針ということでこちらの方に載せさせていただきました。こちらの方も参考にしながらご検討をいただきたいというふうに思います。
続きまして、25ページをごらんいただきたいと思います。
公共的団体の取り扱いについてでございます。
まず、1番の留意事項を先に説明させていただきたいと思いますが、公共的団体とは、農業協同組合、森林組合、その他の協同組合、商工会等の産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団体等の公共的活動を営むすべての団体を含み、法人であるか否かを問わず、地方自治法
157条の公共的団体等とその範囲を同じくするものですということでございます。
そして、(2)の方に、合併特例法第16条第8項では、合併後において、いつまでも合併前の市町村の単位で各種の公共的団体等が存在することは、合併による新市の一体性の速やかな確立の面からも好ましくないという観点から、その区域内の公共的団体等はその統合整備を図るよう努めなければならないとしていますということに規定がなっております。
また、合併関係市町村からも統合のための助言等を十分行うというのがありますし、組織の強化の点からも相互の調整を図ることが重要であると考えられますということで、これにつきましては、地方自治法の
157条の中に、「地方公共団体の長は、区域内の公共的団体等の活動を総合調整をする」というように規定をされていることでございます。
その下に現況ということで、主な公共的団体で3町に共通するものを主なものということで載せさせていただきましたので、そちらについては後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
それらを踏まえまして、調整方針の案でございますが、公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
(1)として、3町に共通している団体はできる限り合併時に統合するよう調整に努める。
3町に共通している団体で実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。
(3)で、3町に共通している団体で、統合に時間を要する団体には、将来統合するよう調整に努める。
(4)その他の団体については、個別に検討し必要な調整に努めるということで、ここについてはあくまでも新市の一体化を速やかに図るという側面、それから新市のまちづくりを円滑に、そして均衡よく新市の発展を図るという側面から公共的団体の統合を図っていきましょうというようなことで、こちらの調整方針を記載してございますので、そういう観点でごらんをいただきたいかなというふうに思います。
27ページにつきましては、先ほども申し上げました公共的団体とはということの行政実例、そして先ほどご説明申し上げました合併特例法の規定の抜粋、そして地方自治法の規定の抜粋、そして公共的団体の大きなものといたしまして社会福祉協議会、商工会というのを、一例ということでございますけれども、根拠法令と申しますか関係法令の方を抜粋で掲載させていただきました。後ほどごらんをいただきたいと思います。
29ページから31ページにつきましては、先進事例における取り扱いについてでございます調整方針を載せさせていただきました。
今回、こちらの調整資料の冒頭、公共的団体等の取り扱いその1というふうに書かせていただいてあります。先進事例においては、一般的な公共的団体の中に土地開発公社であるとか、三セクであるとか、公益法人についてもこちらの方で協議をしておる事例がございます。3町におきましても、北浦の土地開発公社と玉造町の開発公社さんございます。ただ、ちょっと目的が違う団体ではございますが、その辺の協議がまた進みまして、また協議会の方にお諮りする必要がある場合には、またそちらの方で提案をしていただきたいということで、「その1」というふうに書かせていただいたということをあらかじめご理解いただきたいというふうに思います。
ということで、先進事例の方を参考までにまたごらんいただきたいというふうに思います。
続きまして、32ページをごらんいただきたいと思います。
前回、公募方式をご決定いただきましたということで、今回、その関連についての議案でございます。
まず、新市名称候補の選定基準でございます。こちらの方を読み上げる形で説明をさせていただきます。
1、新市名称候補選定基準。
新しい市の名称は、漢字、平仮名及び片仮名で表記された読み書きが容易な名前で、既存の市名にないもの及び麻生・北浦・玉造の文字を使用していないものの中から、次の条件の1つ以上に該当する名前とするということで、1)から5)ございます。
1)地域が地理的にイメージできる名前。
2)地域の特徴をあらわす名前。
3)地域の歴史・文化にちなんだ名前。
4)住民等の理想・願いにちなんだ名前。
5)その他新市名としてふさわしい名前。
5項目でございます。
2、選定方法でございます。
新市名称候補は、募集作品の中からおおむね5点を小委員会において選定をする。
新市名称候補の中から、協議会において新市名称を決定するという流れでございます。
3、応募作品の修正。
応募作品をそのまま採用することが困難な場合には、必要に応じて、作品の趣旨を著しく損なわない範囲で修正することができるものとする。
4、選定に当たっての留意事項。
得票数(応募数)については、選定の際の参考にとどめることとするというものでございます。
別紙の方にただいま申し上げました既存名称の取り扱いについての詳細の取り扱いについて、こちらの方に書かせていただいてございます。
1番の現在の麻生、北浦、玉造の名称に係る取り扱いということで、1)番、現在の名前を異なる表記にするものはだめですよということで、平仮名、片仮名にするものはだめだということでございます。
2)番、現在の名称を別の読み方にするものも無効でありますということでございます。
3)で、現在の名称を別の漢字に置きかえて現在の3町の名称と同じに読ませるものも無効でありますということです。
4)現在の3町の名前を新市の名称の一部につけるものも無効ですという取り扱いでございます。
そして、2番、全国に存在する市町村の名称の取り扱いということで、これは西東京市の合併の際、総務省への照会に基づきます回答でございます。基本的に全国に同一または類似する名前があると思いますけれども、同じ表記をする場合については、読み方が違ってもだめだというのがアでございます。
それから、異なる表記で同じ読み方をするものにつきましては○です。差し支えありませんというような取り扱いでございます。
それから、同一または類似の「町村」が存在する、今回市制をとることになりますので、今回は市の名前を決めることになります。同じ名前を町村が使っている場合にそれが可能かどうかというような事例でございますが、これは構わないというようなことでございます。そのほか2)、5)まで載っておりますので、これにつきましてはそういうような総務省の回答でありますということでごらんをいただきたいというふうに思います。
35ページをごらんいただきたいと思います。
新市名称(候補)募集要項の方でございます。
1、公募の目的。
合併による新しいまちづくりに係る住民参加の推進を図ることでございます。
2、公募の方法。
(1)応募資格。
ア、3町に現在住所地を有する者。
イ、3町に現在勤務地を有する者。
ウ、3町に現在通学している者。
エ、その他3町に両親、兄弟姉妹、親戚を有するなど3町にゆかりのある者ということでございます。
応募資格、範囲につきましてはご議論のあるところかなというふうに思いますが、ある程度地元に住む方で決めていただくということが適当であろうという趣旨でこのような範囲にしてございます。
それからもう1点、住所がない、現在住んでいないという方であっても、例えば、今、大学に行っている、例えば、大学を卒業して今東京に就職しているけれども将来は地元に戻って地元のために何かしたいんだ、働くんだ、農業をやるんだ、商業をやるんだという方がいれば、そういう方についても除くということは適当ではないのかなという判断がここのエでございますので、案につきましてはそういう趣旨で書かせていただいてございますので、また次回の協議の中でご議論をいただきたいというふうに思います。
(2)応募方法につきましては、専用応募はがき、官製はがき、ファクス、eメールということで、専用の応募はがきにつきましては合併協議会だよりなり名称募集のチラシを各戸配布する中に、こちらの負担で応募郵便料を負担するような形のはがきを加えさせていただくというようなものを考えておるということでございます。
(3)応募先でございますが、郵送、ファクス、eメールがそのとおりでございまして、エ、その他ということで、持参であれば各町の企画担当課でも受け付けますよというものでございます。
(4)必要記入事項でございますけれども、応募に当たっては、次の事項をすべて記入していただきたいというものでございまして、必要記入事項に漏れがある場合、やむを得ず無効とする場合がありますということで、これはなぜかといいますと、次に書いてあります市の名称の意味・理由について、名称だけ書かれても意味がわからないで、それをいい悪いという判断がなかなかつきにくいという部分がございます。そういうことで、名称を書いてあっても、その意味・理由というものをやはり書いていただきたい。それにつきましても含めて小委員会、協議会の中で選定の判断材料にしていただくということが適当だろうという判断に基づきましてこういうような記載をさせていただいてございます。1から7まででございますので、よろしくお願いします。
ただ、電話番号につきましては、携帯しかないとかいろいろな事情もあると思いますので、こちらはできる限りということで書いてございます。
そして、(5)応募に関する留意事項でございます。
先ほどの選定資料にありましたように漢字、平仮名、片仮名でということ、それから3町の名前、既存の市名については無効でありますということ、それから3町の名前を異なる表記にした、別の読み方にした、そういうものは無効にしていただきたいというものでございます。
36ページをごらんいただきたいと思います。
募集の周知ということでございますが、広報紙それから協議会ホームページに掲載させていただきます。それから、先ほど申し上げました広報紙の中に専用応募はがきをとじ込みまして配布させていただくというような流れを考えてございます。
募集期間につきましては、平成16年6月15日から7月15日までの31日間、郵送による消印有効ということでございます。
この応募結果、決定結果の公表につきましては、ホームページ、広報紙で公表をいたします。
6番について、こちらもまたご議論あるところだと思いますけれども、麻生町・北浦町合併協議会が実施した名称募集に係る応募作品の取り扱いということで、2町が実施した名称募集に係る応募作品については、今回、行方郡合併協議会が実施する名称募集の応募作品に含めるものとするということでございます。
こちらについては、先ほどの選定基準で言えば地理的イメージとか、いろいろ2町と3町で違うというご議論もまたあろうかなというふうに思いますが、例えば住民の理想、願いを名称案にしたものであれば、それは2町であっても3町であっても変わりないのかなというふうにも思いますし、応募作品につきましてはそういう観点から決定させていただきたいというものでございます。
それから、7番、応募作品についてでございますけれども、その一切の権利は当行方郡合併協議会に帰属させていただきますという内容でございます。
新市名称の決定方法、先ほど説明の中で申し上げました5候補を小委員会で選定させていただきまして、最終的に合併協議会が決定をするというものでございます。
記念品の贈呈でございます。応募された名称の中から次の賞を決定し、記念品を贈呈するというもので、1、2、3でございます。
以上が募集要項の案でございまして、その右隣、37ページにおおむねのスケジュールということでご理解をいただきたいところでございますが、名称の募集につきまして、事務局で集計をさせていただきます。小委員会の選定作業を行いまして協議会で決定をいただくというような流れになってございます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、38ページをごらんいただきたいと思います。
新市名称候補選定に係る小委員会の設置ということで、その案でございます。
1、小委員会の設置概要ということで、(1)名称につきましては、新市名称候補選定小委員会、2番、付託事項といたしましては、新市名称候補の選定に関することということで、具体的には、応募作品の中からおおむね5点を選定することという内容でございます。設置時期につきましては、名称募集が終了いたしました平成16年7月16日ということでございます。
そして、2番、小委員会委員の選任ということで、各町選出の学識経験者、一般住民代表の方ということで、こちらの方、小委員会の選定委員ということでお願いをできればよろしいのかなということでのご提案でございます。
続きまして、建設計画のアンケートに係る部分でございますが、担当の森坂より説明いたしますので、よろしくお願いします。
○森坂計画班長
合併協議会の事務局森坂です。よろしくお願いします。
先ほど新市の合併建設計画にかかわります策定方針ということで決定いただきました。早速新市の合併建設計画の策定の作業に入るわけなんですが、それの調整方針につきまして進めてまいります。
資料の39ページになってございますが、提案事項の5ということで、今回、新市の合併建設計画に係る住民アンケートの実施についてということでご提案申し上げます。
新市の合併建設計画を策定するためのアンケート調査ということで、新しいまちづくりのためのアンケート調査、住民にとってどういったものが要望があるのか、あるいは希望があるか、新しいまちづくりの将来像についてどういったイメージを描いているのかと、そういった希望につきましてアンケートの調査をし、その計画の中に住民の意向を反映していきたいというふうに考えてございます。
そして、調査の区域ということでございますが、これは玉造町ということで、既に北浦町、そして麻生町におきましては、新しいまちづくりについての将来像や、あるいは合併する際にどういったような要望があるのか、希望があるのかというようなアンケートを2町の協議会のときに実施をしてございまして、内容的に全く同じ内容となってしまいますので、今回は玉造町のみの対象ということでアンケートの方を実施させていただきたいということでございます。
そういうわけで、調査対象としましては玉造町の全世帯、今現在 4,022世帯でございますが、それらの全体を対象としまして実施をしていきたいということでございます。そして、今回、時間もそれほどございませんので、直接それぞれの世帯に事務局の方から郵送で配布をし、なお回収につきましても郵送によっての回収ということで調査をしたいという考えでございます。
調査の方法ですが、先ほど言いましたように次の40ページからの中にアンケートの内容が載ってございますけれども、最初に性別、年齢、住所等を聞きまして、そのほか合併の際のまちづくりの将来像、そして合併する際のまちづくりの事業ということで、個別に社会基盤の整備あるいは生活環境の整備、保健・医療・福祉、教育・文化、産業の振興、そして連携・交流促進、行財政の効率化ということで、7項目に分けましてのアンケートという内容になってございます。そして、最終的には意見・アイディア提案ということになっております。
調査の時期なんでございますが、今回、提案事項ということで、 次回の5月27日に第4回の協議会が予定されているわけなんですが、その協議会の中で了解が得られれば6月1日から6月13日ということで約2週間の調査期間をもってこのアンケート調査を実施したいというふうに考えてございます。
後ろの方1枚めくっていただきまして、「アンケート調査のお願い」ということで書いてございます。そして、下に「ご記入にあたって」ということで4項目ほど書いてございますが、世帯主の方にアンケートの方は送ります。回答者は、世帯の中で中学生以上の方であればどなたでも結構ですということで、また、家族の中で相談をして回答をしていただいても結構ですというような内容となってございます。
それから、設問ごとに回答欄の方へ選択した項目の番号等を記入してくださいということであります。
そして、先ほど言いましたように13日までに提出をしていただくということでございます。
そして、41ページから、それぞれ設問の内容が載ってございます。最初にあなたご自身のことをお答えくださいということで問1から問4までございます。
そして、問5から、項目としましては、あなたは、新市が将来どんなイメージの市となっていけばよいと思われますか。次の中から3つまで選択してくださいということで、9つほど項目ございまして、その中から3つを選択していただくというような調査の内容となってございます。
42ページ以降は、同じように項目としまして、あなたは「社会基盤の整備」を考えたときに、新市においては次のどのような事業に重点を置くべきだと考えますかということで、同じように選択ということで3つほど選択をしていただくというような形で、問7が「生活基盤の整備」、問8が「保健・医療・福祉の充実」、問9が「教育・文化の充実」、そして44ページ、問10が「産業の振興」、そして問11としまして「連携・交流の促進」、問12としまして「行財政の効率化」につきましての問いでございます。
そして、問13としまして、あなたが望む具体的な事業提案があれば記入してくださいということで、自由標記欄を取り入れてございます。
以上がアンケートの内容でございます。よろしくお願いいたします。
○横山会長
ただいま事務局の方から、次回の合併協議会でご協議をいただく事項について提案をし、そしてご説明をいたしました。
これにつきまして、委員の皆さんにご質問等がございますれば承りたいと思います。よろしくお願いします。
宮内委員さん、お願いします。
○宮内守委員
新市名称候補選定に係る小委員会の設置(案)ということでございますが、これは小委員会委員の選任ということで各町選出の学識経験者4名ということになっておりますけれども、私、親から人に迷惑をかけるなと言われているわけでして、これは学識経験者だけということでありますが、だめだというようなことではないんですけれども、どういう根拠でこういうふうになったのか、あるいは議員に資格があるのかと、そういうこともありますので、その辺の選任の候補の内容、どうに考えているのでしょうか、お伺いしたいと思います。
○横山会長
それでは事務局より説明をお願いします。
○江寺事務局次長
事務局において、今お話ありましたように各協議会においていろいろな小委員会の設置の委員構成をとっております。おおむね3つ考えられていまして、学識経験者だけというような委員構成の協議会、そして学識経験者に議員さんと行政関係を含めたというのがもう一つ、それから学識経験者と議員さんだけのもの、3つ確かに考えられるというふうに思います。
我々が今回提案させていただきましたのは、これは議員さん方も当然住民の代表でございますが、今回合併協議会の中で特に住民の代表という形でこの委員にご就任いただいた方々に広く住民のまた声を聞いていただいて、末端までいろいろ聞いていただいて、隣のおじいさん、おばあちゃんにも聞いていただいて、その意見を反映していただいて、それ議員さんができないとかということではなくて、せっかくこういう機会に学識経験として就任された方々に、名称決定に当たって苦労ではありますけれどもご尽力いただければ非常にありがたいなということで、今回、案という形でご提案をさせていただいたものでございますので、こういう趣旨だということでご理解をいただければありがたいと思います。
○横山会長 よろしいですか。
もう1回、じゃ宮内委員。
○宮内守委員
今、事務局から提案があったわけですが、4名を選定すればよいのではないかというふうに私は思うものでございます。
何か今の説明に納得するだけのものはないということです。
○横山会長 はないと。
ほかにありますか。
橋詰委員さん、お願いします。
○橋詰委員
行財政改革の一環でこれは合併するのが趣旨だと思うんですが、その中で、今度の会議で事務局に調べていただきたいのは、この職員給与のほかに手当というのがありますが、この手当に関しましては各種手当がある。それで勤勉手当というのがありますね。この勤勉手当はどういう趣旨だか知りませんが相当前からある制度。これは漏れなく職員全員に各町がついているのかどうか、これをちょっと調べておいていただきたい。これ全員がついているのであれば、これは給与の一部だと思うんですね。ならば最初から給与にしちゃってという考えもあると思うんです。これ勤勉手当というのは全員についているのではないかと私思うんですね。これ一応調べていただきたいと思います。勤勉手当ですよ。
それとこの、先ほど調整内容というのがいろいろ書いてありますね、この24ページの下に横書きでびっちり書いてあるんですけれども、非常に読みづらい。字の間が密着しまして、ちょっと注意しないと字の行が次の字にかかってわかりづらいんですけれども、これ前の説明の案内も同じような書き方ですので。これつくっている方が別々だと思うんですね、作成している人が。次のページは行間なり字間が違うので、これも同じように統一していただければ読みやすくなるんじゃないかな。特に他町の調整内容ですか、わかりづらい。それはお願いしたいと思います。
それともう一つは、今度の16年度の予算出てきたわけですけれども、16年度の予算の中で、各町の基金の残高、これは予算の中で全部わかっていると思うんですが、それと町債債務残高、それと公共的施設がいつ完成したか、これを一応設備とともに公共的設備、それを参考のためにつくっていただきたいと思います。これらも16年度の予算ですから大体はわかると思いますね。それらを参考にいただきたいと思いますので、お願いをしたいと思います。
○横山会長
ただいまのお願いについて、執行部、お答えをお願いします。
事務局からお願いします。
○羽生事務局長
今、要望をいろいろ聞きましたが、次回の協議会までに資料を用意することでよろしくお願いします。
○横山会長
ほかにございますか。
茂木委員さん、お願いします。
○茂木委員
個人的な意見を申します。
新市の募集ということで募集要項が配布され、住民参加でというような決定をなされたわけでございますが、私個人的には、漢字の行方市か平仮名のなめかた市かというふうに考えております。本来ならばこれで決定しちゃえば、経費のむだ遣い、時間のむだ遣いというようなことも考えまして、私個人的な意見でございます。
それともう一つ、個人的な意見として新市の事務所の位置について、多分このままいくと継続審議になると思います。私の個人的な意見で、新市の事務所の位置について麻生が一番人口が多いので麻生に事務所を置いていただきたいというのが個人の意見。
それとあと、これから出てくると思いますが議会を例えば玉造町に議会を置く、農業委員会を北浦町に置くといようなことで、ただ新市の事務所の位置だけではなく、議会、また農業委員会、その面も含めて、これから各持ち帰って協議させていただければスムーズに進むのかなという私個人的に思いますので、この辺、私個人的な意見でございますが、終わります。
○横山会長
ありがとうございました。承っておくそうですから。
ほかにありますか。
どうぞ。
○高野委員
これ質問じゃないですが、こういうこの文章の中でちょっと削除といいますかね、公共団体等の取り扱いの中で婦人会という文言が入っておりますので、それを使っていくのかなということでございます。
○横山会長
お願いします。
○羽生事務局長
不適切だったかと思いますので、次回に改めたいと思います。
○横山会長 次回までに直すそうでありますので、お願いします。
ほかにありますか。
(発言者なし)
○横山会長 それでは、提案事項につきましては以上とさせていただきたいと思います。
大変皆様方には長時間にわたりましてご協力をいただきましたことを厚く御礼を申し上げたいと思います。
これで進行役を事務局に渡したいと思いますので、よろしくお願いします。
○羽生事務局長 ありがとうございました。
それでは、副会長でございます伊藤北浦町長さんより閉会のあいさつをお願いいたします。
○伊藤副会長 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また長時間にわたり慎重な審議、まことにありがとうございます。きょうは特に白熱したご意見が出まして非常にうれしく思っているところでございます。次回もよろしくお願いをいたします。
これにて第3回行方郡合併協議会を閉会といたします。
大変ご苦労さまでした。