●場所:北浦町役場「大会議室」
●あいさつ
●議 事
(1)報告事項
1) 合併の方式について
2) 合併の期日について
3) 新市の名称について
4) 合併協定項目(案)について
5) 行政制度の調整方針(案)について
6) 同 分科会規程について
(2)提案事項
1) 新市の事務所の位置について
2) 財産の取扱いについて
3) 議会議員の定数及び任期の取扱いについて
4) 新市建設計画の策定方針(案)について
●その他
● 出席委員(35名)
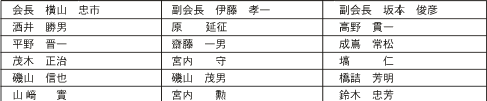 |
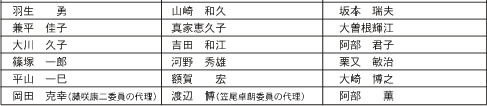 |
● 欠席委員(1名)
磯山 信也
●出席顧問
藤島 正孝
○一條事務局次長 大変お待たせいたしました。
本日は、悪天候の中、また、大変お忙しい中、まことにありがとうございます。本日の司会を務めます、事務局の一條でございます。よろしくお願いします。
始めに、伊藤副会長より、開会の言葉をお願いしたいと思います。
○伊藤副会長
ご紹介をいただきました北浦町長の伊藤でございます。本日は、公私ともども大変お忙しい中、第2回行方郡合併協議会ということになりましてご参集いただきまして、大変ご苦労さまでございます。第1回目におかれましては、玉造町において、総合的な合併の協議をいただいたところでございます。これから、2回、3回と続くわけでございます。これから各論に入り、皆様方の貴重なご意見をいただきながら、この協議会がスムーズにいきますように、ご協力のほどお願い申し上げます。
ただいまから、第2回の行方郡合併協議会を開催します。よろしくお願い申し上げます。
○一條事務局次長
それでは、横山会長よりごあいさつをお願いいたします。
○横山会長
本日は、大変お忙しい中、第2回行方郡合併協議会にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
当協議会は、2週間に一度のペースで開催するスケジュールということになってございます。皆様方には大変ご負担になろうかと思いますけれども、行方地域の将来がかかった、極めて重要な協議会でございますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
また、今回の第2回協議会から、実質的な協議が始まるわけでございます。それぞれの地域の実情を踏まえながらも、行方3町全体の発展につながるような議論を行いまして、住民の方々にも合併への理解が得られる協議であるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
さて、本日の協議事項でございますけれども、合併の方式のほか、合併の期日、名称の取り扱い、合併協定項目(案)、行政制度の調整方針(案)を予定いたしております。皆様方には、円滑で、実り多い協議ができますよう、よろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
本日は、大変ご苦労さまでございます。
○一條事務局次長 ありがとうございました。
それでは、早速議事に移りたいと存じます。合併協議会規約第10条第2項の規定により、横山会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと存じます。会長、よろしくお願いいたします。
○横山会長
それでは、規約に従いまして、議長を務めさせていただきますので、ご協力のほど、よろしくお願いをいたします。
なお、本日の出席委員は35名でございます。協議会規約第10条第1項に規定いたします定足数に達しておりますので、ご報告を申し上げます。
それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきたいと思います。
まず、協議事項の1番でございますけれども、合併の方式についてを議題といたします。合併方式については、新設合併か、編入合併のいずれかを選択することになります。また、市制施行が可能でありますので、それを目指していくということになろうかと思いますが、その点も含めて、ご協議をお願いいたしたいと思います。
それでは、皆さんにご意見をお願いいたしたいと思います。
最初に、新設合併か、編入合併か、いずれかを選択しなければならないということでありますから、委員の皆様方にご忌憚のないご意見をいただきたいと思います。
宮内委員。
○宮内(守)委員
北浦の宮内と申します。よろしくお願いいたします。
第1点目の合併の方式につきまして、実は、北浦町で先般会議をいたしまして、一応新設合併というような形でお願いしたいということでございます。ご意見を申します。
○横山会長 ほかにご意見はございませんか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでございますので、合併の方式につきましては、調整方針(案)のとおり、新設合併とし、市制施行を目指すということで、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでありますので、そのように決定をさせていただきたいと思います。
次に、協議事項の2番でありますけれども、合併の期日についてを議題といたします。今回の提案につきましては、期日を検討していただくために、前提となる考え方、方向性を確認していただきたいという提案であります。したがいまして、具体的にいつにするのかについては、国や県の支援措置にかかります経過措置の状況等も見ながら、改めて後日協議をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、委員の皆さんにご意見を承りたいと思います。
合併の期日はこれからさきの協議で結構ですが、方針を皆さんにこの前、第1回目のときに提案してありますね。
では、事務局より説明をさせますので、よろしくお願いいたしたいと思います。では、事務局で説明をしてください。
○江寺事務局次長
事務局の江寺でございます。皆様ご苦労さまでございます。よろしくお願い申し上げます。
第1回の協議会におきましてお配りをいたしました資料の39ページをごらんいただきたいと思います。ただいま、会長の方から説明がありましたように、合併の期日については、これからの協議の進捗状況、そしてただいま国会で議論をされております合併特例法の経過措置、そして国によりますそのほかの支援策、また県の支援策がございますので、それらを踏まえまして、改めて具体的な期日についてはご協議をいただくということがよろしいのかなというふうに考えております。したがいまして、今回第2回の協議会におきましては、合併の期日をこれから議論していただく中で、どういう方向でこれから合併協議を行っていくのか、その中の期日についてはどのように考えていくのかという前提条件、方向性ということをご確認いただきたいということでございます。したがいまして、この調整方針(案)に書いてありますように、現時点での判断としては、今のところで決まっております合併特例法による特例措置を受けるんだというようなご確認をいただきたい。そして、具体的期日については、先ほど来会長からもありましたように、協議の状況、それから各種支援措置、それらの経過措置がどうなるのかということを踏まえて、具体的に決めていくということになろうかと思います。
ちなみに、今、議論されております国会につきましては、6月半ばまでの会期ということでございますので、その後に改めてご協議をお願いするということになろうかというふうに、事務局の方では考えております。ということで、そういう観点から、本日のご議論をいただきたいということでございます。
よろしくお願いを申し上げます。
○横山会長
ただいまの事務局の説明でありますけれども、この調整方針(案)ですけれども、これを見ていただきたいと思います。これで議論をしていただきたい。
橋詰委員。
○橋詰委員 玉造の橋詰です。
合併特例法の日にちが延期になる、ならないの論議もあるでしょうけれども、各種財政支援その他の支援策を伴う法定協議会が合併特例法の恩典を受けられる範囲の中で、日にちは変化するかもわかりませんが、合併特例法の有効期限の中で、延期になる、またはならなかった場合は、その範囲の中で特例法を受けるという前提で合併を進めていくという、この今の提案で私はよろしいと思います。合併特例法の恩典を受けられないということになったのでは、せっかくの法定協議会ももったいないものですから、特例法を受ける、財政支援を含めた各種支援を受ける体制の中での合併、これを前提とした協議会ということでお願いしたい、こう思います。
○横山会長 ただいま、橋詰委員の方からございましたけれども、ほかにありますか。
茂木委員。
○茂木委員 麻生の茂木です。
ただいま、橋詰委員の方から、特例法が受けられる範囲ということで、私も大賛成でございます。ご提案差し上げます。一応17年の3月31日までというふうにここにも書いてあるわけでございますが、できれば、予算の関係、またいろいろな事務の関係ありますので、ご提案させていただきたいと思いますけれども、できれば17年の2月1日ということでご提案させていただきたいと思いますので、よろしくご協議お願いしたいと思います。
○横山会長
茂木委員、期日の設定の具体的な日にちはこの次の協議でしていただいて、国会が、いわゆる特例措置が受けられる17年の3月31日までに合併をしましょうということの大まかな期日の設定ということで、皆さんよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○横山会長
それでは、そのようにご理解をしていただきたいと思います。
もう一回申します。現時点では、確実に各種特例措置や財政支援措置が受けられる平成17年3月31日までの合併を目標とすること。具体的期日につきましては、今後の協議の進捗状況や各種支援措置にかかわる経過措置の状況等を踏まえて、改めて協議をし、決定をしていくということで、よろしいでしょうか。
○坂本副会長
これに関して、ちょっと確認をしたいんですが、私は玉造町長の坂本なんですが、初めての協議会で、麻生、北浦もそういうふうにすり合わせをしているというか、そういうふうに感じたんですが、財政措置が受けられる日が6月、そのころまでにはちゃんとした答えが出るのかどうか、それをぜひ県の方にお聞きしたいんですが。
○横山会長 それでは、県の方でお願いします。
○岡田委員(藤咲委員代理)
先ほど、事務局が6月ごろ国の云々というお話をしましたが、合併特例法は17年の3月までに基本的に合併していなければいけないというのが今の法律なんです。ところが、今、非常に全国的に合併の動きがありまして、なかなかこれに間に合わない部分も見受けられるということで、国の方では、17年の3月31日までに各市町村間、ここですと3つの町村ですけれども、この議決を経て、3月31日までに県の方に合併の申請をしていただければ1年延びて18年の3月まで、今の合併特例法の優遇措置を継続しましょうという、こういう案を今出しているところなんです。それが今議論をしていますので、その結論が出るのが、国会の動きの結論が出るのが、6月中旬ごろというのが、今の予測です。そういうことで、先ほど事務局の方で、とりあえず17年の云々というのがあっても、具体的に決めていきましょうかというのが、ご説明あった内容かなと、こう理解しております。
○横山会長
国会の方で決定したわけではございません。きょうの協議会は、やはり合併の特例措置が受けられる期日を設定しておくのが妥当な状況だと思います。したがって、先ほど会長の方からお話し申し上げたとおりでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○横山会長
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。決定をさせていただきます。
次に、協議事項の3でありますけれども、新市の名称についてを議題といたします。
今回は、新市の名称の決定方法をどの方法にするのか、あわせて既存の、麻生、北浦、玉造の名称を選択肢として認めるかどうかについて、ご協議をいただきたいと思います。
それでは、皆さんにご意見を承りたいと思います。
橋詰委員。
○橋詰委員
新市の名称の決定方法の幾つかの選択肢があるかと思いますが、玉造は、北浦、麻生さんと一緒になるということで、初めての協議会でこのような席であれなんですが、個人的には、行方郡の今3町ですので、行方郡の行方がよろしいかなと思いますけれども、これは3町同時に公募方式で全戸配布ということで、真っ白な条件でこれはやっていただいた方がよろしいのではないか。と申しますのは、各3町それぞれの方々に対する合併に対する意識の啓蒙、そういうものも大切ではなかろうかというようなことを考えますと、公募方式でよろしいのではなかろうか。ただ、公募方式でも、一番の上位に立ったものが決定されるということではありません。これはあくまでも、ごらんのとおり小委員会でそれぞれ検討、協議しまして、それでまたこの協議会で全体に諮るということの経緯の手順をするものですから、それがよろしいのではなかろうかというように思っております。そのようなことです。
○横山会長 ほかにご意見はございませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
○横山会長
それでは、もう一点だけ、その公募方式とする場合に、麻生、北浦、玉造という、今の名前も有効としますか、それとも有効としないで、除いて、新たな公募でやっていった方がいいですか、それを皆さんにお諮りしたいと思います。これは大事なことなんです。
齋藤委員。
○齋藤委員
北浦の齋藤ですけれども、先ほど会長の方からも話がありましたように、既存の麻生、玉造、北浦、この名称を除いた公募というようなことがいいんじゃないかと思います。
○横山会長 皆さん、どうですか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、異議なしということで、新市の名称の決定方法につきましては、公募方式とすること、既存の3町の名称については、新市名称の候補として使用しないことを決定してよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。
次に、協議事項4でありますけれども、合併協定項目(案)についてを議題といたします。
合併協定項目につきましては、今後協議会において協議をし、最終的には合併協定書としてとりまとめ、3町で調印をすることになる事項であります。したがいまして、合併の方式などの合併に関する基本的事項及び合併特例法に特例措置が盛り込まれている事項の取り扱いをどうするのか、あわせて3町の事務事業等で差異が大きいものを協定項目として取り上げて協議していくということになろうかと思います。
それでは、ご意見をお願いいたしたいと思います。44ページです。
○橋詰委員
大体この24項目、25項目、建設計画まで入れると25番まであるかなと思うんですが、これは協議の最中に不足している協議事項がもし出てくれば、その時点で追加または除くというようなものも出るかもわかりませんが、とにかく特例法の期限の範囲内でやっていく段階で、追加するものは追加していくということで、現在の段階ではこれでよろしいのではなかろうか。そういう前提つきですが、それでどうでしょうか。
○横山会長
ただいま、橋詰委員からお話がございましたけれども、ほかの皆さんありますか。
(「なし」の声あり)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、合併協定項目につきましては、原案のとおり決定をしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、協議事項5行政制度の調整方針(案)についてを議題といたします。
この行政制度の調整方針(案)につきましては、各町が行っている事務事業を一元化する際の基本的な考え方を整理していくことにより、円滑に調整を進めようとするものでありまして、他の合併協議会におきましても早い時期に協議をしているものでございます。
それでは、委員の皆さんにご意見を承りたいと思います。
(「事務局で朗読してや」の声あり)
○横山会長 朗読してください。
○江寺事務局次長
それでは、行政制度等の調整方針(案)ということで、前回お配りしました資料の48ページをごらんいただきたいと思います。こちらの調整方針(案)につきまして、ただいま朗読をさせていただきます。
(資料朗読)
○横山会長
ただいま行政制度等の調整方針(案)について、事務局で朗読をいたしました。これについて、皆さん何かご意見がございますか。
磯山委員。
○磯山茂男委員
北浦の磯山でございます。
文書のとおりだと思いますけれども、あくまで住民の立場に立ったというか、ラインの部分についてよく考えて行っていくことが一番大切だなというふうに思っております。
○横山会長 ほかにございますか。
(「ありません」の声あり)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、行政制度等の調整方針(案)につきましては、事務局案のとおり決定をさせていただいてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○横山会長
異議なしということでございますので、そのように決定をさせていただきたいと思います。
続きまして、提案事項に移らせていただきたいと思います。
提案事項につきましては、一括して説明をし、最後に質問を受ける形にしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、事務局で配付をお願いいたします。
(資料配付)
○横山会長
それでは、配付が終わりましたので、事務局より説明をお願いいたします。
○江寺事務局次長
それでは、資料に従いまして説明をさせていただきます。
まず、最初は新市の事務所の位置についてでございます。この資料の選択肢の欄に、既存庁舎のいずれかの位置、もしくはその他ということで、新しい事務所を建設するのであればそれらの位置かなということを書いてございますが、まず、留意事項でございます。留意事項の1番目といたしまして、事務所の位置は住民の利用に最も便利であるように、地理的な位置や交通の事情、他の官公署との関係等を考慮して定める必要がありますということでございます。
ちょっと飛ばしていただきますが、2ページの方をごらんいただきたいと思います。2ページの下に、根拠法令として、地方自治法の抜粋が載っております。事務所の位置の設定または変更ということで、第4条に、地方公共団体は、事務所の位置を定め又は変更しようとする場合は、条例でこれを定めるということで、事務所の位置については条例で定めなければならないということをいっておりまして、その下、第2項に、前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、云々ということで、今、ご説明を申し上げたフレーズが、最初の留意事項の1番の最初のページに入ってございます。
資料、お戻りいただきたいと思います。恐縮でございます。
また一方で、交通手段の発達や、情報化社会の構築により、既存の庁舎を活用し、機能的、効果的に役割分担を図る等の視点も大切になってきていますということでございまして、これはこのフレーズそのままということではなくて、昭和の大合併から年数が過ぎまして、交通体系の変化であるとか、いろいろな面で役場の位置、庁舎の位置というもののあり方も変わってきているだろうというふうに思われますので、それらも含めまして、これからご検討いただきたいなということをここで言っている部分でございます。
そして、(2)番でございます。既存の庁舎を利用するのか又は新設するのか、既存庁舎を利用するのであれば、その規模や住民サービス等の観点から、どのような設置方式をとるかなどについて、あらかじめ想定して定める必要がありますということでございます。
なお、新設する場合であっても、完成するまでは既存の庁舎を利用することになりますので、設置方式やその間の事務所の位置について決定する必要がありますということでございます。
ここで、設置方式ということ、今、出てまいりましたけれども、それが3番の方に載ってございます。これにつきましては、恐縮でございますが、その先の1−2ページの方をごらんいただきながら、説明を聞いていただきたいというふうに思います。
まず、本庁方式でございます。これについては、もう説明不要な内容かと思いますが、3町の組織を一つの庁舎、本庁に集約いたしまして、本庁以外の庁舎については、出張所、支所という形で、直接住民に関係のある、証明書であるとか、住民票の発行であるとか、そういうものを行うというような形でございます。メリットといたしましては、事務の効率化が図られるということ、それから新市誕生の印象が強いというようなメリットがございます。反面、現在の3町の庁舎を見た場合に、いずれかの庁舎にすべての行政機能を集約するということはできるのかな、少し厳しいのかなというふうに考えられますので、その場合には、庁舎を新しく建てるか、もしくは大規模な増築が必要になってくるのかなということで、費用等かなりかかってくるものだろうというふうに考えられます。
そして、2番というのは分庁方式の例でございますが、これにつきましては、3町の従来の庁舎を分庁という形で位置づけをしまして、行政機能を、例えばその課ごとに割り振るというやり方でございます。ここで申しますと、本庁機能ということで、例えば総務、企画、環境、水道、議会がA庁舎、それからB庁舎に福祉、産業経済、下水道、教育委員会、C庁舎に住民、税務、保健、建設というものを置く。そして、この本庁機能が配置されない機能が幾つも出てまいります。例えばA庁舎であれば、福祉だとか、住民だとか、税務とか、そういうものが配置されません。そういう分野の中で、例えば、本庁方式と同じように、住民に身近なサービスというものについては、出張所なのか、支所機能なのか、その辺はわかりませんが、一定のサービスを行う部門、そういう窓口部門を配置するというようなやり方でございます。これにつきましては、メリットといたしましては、既存庁舎の利用ということでございますので、改修費用等が少ないというメリットがございます。ただし、デメリットといたしまして、この本庁機能、各業務を庁舎ごとに分散させる形になりますので、住民への十分な周知が必要になるということが挙げられるということでございます。
そして、3番目が、総合支所方式でございます。これにつきましては、例えば総務、企画、財政等の管理部門、そして議会であるとか、そういう事務局部門、それらを除きまして、その他の行政機能を現在の3つの庁舎にそのまま置くというようなやり方でございます。メリットといたしましては、現状に一番近いという形で、新市への移行が容易であるというところが挙げられますが、デメリットといたしましては、人件費の削減効果という点でなかなか効率化が生かされないということ、それから新市の一体感、一体性という点でいうと、なかなか難しい面があるのかなというふうに考えられます。
いずれにいたしましても、このような事務所の設置方式、どのような方式にするのかということも、これから事務所の位置をご検討いただく中で、重要なポイントになってまいろうかなというふうに考えております。
恐れ入ります、1ページの方へお戻りいただきたいと思います。
ちょっと飛ばしましたので、2番の主な検討事項でございます。留意事項のところでご説明を申し上げた内容の繰り返しになろうかと思いますが、まず、新庁舎を建設するのか否か、建設する場合の位置、時期をどのようにするのかということが1点挙げられると思います。そのほか、建設しないとした場合、どのような事務所の設置方式をとるのか、その際の事務所の位置、これは条例上の事務所の位置ということになります。先ほど、地方自治法の中で、事務所の位置を定めなければならないというお話をさせていただきました。これを受けての部分でございます。そして、3番といたしまして、建設するとした場合においても、建設までの間の事務所の設置方式、位置、そういうものを検討する必要があるということでございます。
続きまして、2ページへお進みいただきたいと思います。現在の庁舎の現況を書かせていただいてございます。まず、(1)番に所在、面積等ということで、所在地、敷地の面積、駐車台数の主な概要ということ、それから交通機関、主要道路を書かせていただいてあります。そこのほか、建物の状況ということで、構造、それから床面積、そして備考の欄につきましては、建築年次をこちらの方に掲載をさせていただきました。そして、3番目につきましては、主な官公署の状況でございます。後ほどごらんをいただきたいと思います。
2ページの下、先ほど地方自治法の説明をさせていただきました。その下に、参考までに、支所と出張所ということが出てまいりましたが、位置づけがどのような位置づけになるのかということで、若干触れさせていただいてございます。支所につきましては、一定程度の行政事務を行うということを前提にしております。出張所につきましては、その行政事務の一部ということで、証明書の発行、住民票等の発行ということに、ある意味では限定されるというのが、一般的な取り扱いということになろうかなというふうに思います。
次に、3ページの方へお進みをいただきたいと思います。
今回はあくまでも提案でございますので、次回以降ご協議をいただくということになると思いますが、あくまでもこれは参考でございますけれども、先ほど主な検討事項を申し上げましたが、それに基づいて、このような検討シートをつくってみましたので、また、ご検討される際の参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、4ページでございます。3町の管内図ということで、白黒で若干見にくいところもあるかと思いますが、3町の形がこういう形になってございまして、その中に、現在の3つの役場がどこの位置にあるのかということを、こちらの表でごらんをいただきたいというふうに思います。よろしくお願いを申し上げます。
それでは、続きまして5ページ、財産の取り扱いの方へ移らせていただきます。
財産の取り扱いにつきまして、まず調整方針の方からごらんをいただきたいと思います。調整方針の案の1番といたしましては、3町の所有する財産及び債務はすべて新市に引き継ぐものとする。そして、2番目といたしまして、基金については、再編統合を行い、新市において必要な基金を創設する。
なお、施設整備等にかかる特定の目的の基金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするということでございまして、これにつきましては、各町で一定の施設整備等を目的として、その資金積み立てをしている基金があろうかと思います。それにつきましては、そのように新市に引き継ぐというような趣旨でございます。
続きまして、財産の概要ということで、一般会計、特別会計、それから公営企業会計に分けて、こちらの方掲載をさせていただいてございます。あくまでもこれは14年度末ということでございまして、15年度決算、まだ決算が済んでおりませんので、14年度末の数字がこちらの方に載っているということでございます。
若干簡単にご説明申し上げますが、主な財産につきましては、公有財産、それから物件、基金ということで分けてございます。その中、土地、建物になっておりますが、まず、行政財産につきましては、まず公用財産であります。これは役場等がここに該当するのかというふうに思いますが、それぞれこのような土地面積、建物の面積ということでございます。
それから、公共用財産につきましては、学校であるとか、幼稚園等、そういうものを指しているものでございます。土地、建物、それぞれこのような状況でございます。
普通財産につきましては、今、申し上げました公用財産、公共用財産以外の財産というようなことでございます。数字につきましては、こちらの方をごらんいただきたいというふうに思います。
そして、2)の方、有価証券・出資による権利ということで、それぞれ内訳が8ページ以下にまた載ってございますので、これにつきましても、後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
そして、3番目が物件ということで、車両等をこちらの方に載せてございます。これにつきましても、9ページに内訳がございますので、後ほどごらんをいただきたいというふうに思います。
そして、4番が基金でございます。10ページに内訳等載ってございますので、後ほどごらんをいただきたいというふうに思いますが、先ほど特になお書きのところに、施設整備ということが出てまいりましたが、この中で、内訳の方、10ページの資料で見ますと、例えば北浦町の学校施設整備基金などもそれに該当するのかな、それから玉造町の公共施設整備基金等もこれに該当するのかなというふうに考えられるんだろうというふうに思います。
それから、債務でございますが、債務については、地方債、それから債務負担行為でございます。地方債につきましては、借金という形で考えていただければいいのかなというふうに思いますが、それぞれ一般会計、特別会計でこのような額になっております。
なお、特別会計につきましては、下水道等の会計に伴う事業債ということでございます。
それから、債務負担行為の額がその下に載っております。これから継続して債務という形で、これからも負担する額ということでご理解をいただければいいのかなというふうに思います。
なお、簡単な、ただいま申し上げました用語の解説が、12ページの下段のところに載ってございますので、また改めてごらんをいただきたいというふうに思います。また、用語として非常に紛らわしい用語でございます。もし、何かご質問等ございましたら、後ほどの質疑でも結構でございますし、事務局の方に何なりとご質問をいただければありがたいというふうに思います。
13ページへお進みいただきたいと思います。
先進事例における取り扱いということで、こちらの方に事例を載せさせていただきました。15年4月1日以降の合併事例の中の幾つかということでございますが、この調整方針、先進事例におきまして、一つには、すべての協議会において、現行の財産についてはすべて新しい市、町に引き継ぐというような調整方針を決定しておるということでございます。
それから、もう1点、2点ございます。1点については、財産区が所有する財産がございますれば、その取り扱いについて調整をするということ、それから、そのほか基金であるとか、そういうものについても、必要に応じて調整方針、数は少ないのでございますけれども、盛り込んでいるところがございます。後ほどまたごらんをいただきたいというふうに思います。
続きまして、駆け足になりますが、14ページの方をごらんいただきたいと思います。議会議員の定数及び任期の取り扱いについてでございます。これにつきましては、新設合併と編入合併で取り扱いに若干の差異がございますが、先ほど新設合併ということでご決定をいただきました。したがいまして、新設合併に係る場合の取り扱いについて今回ご協議をいただくということで、そのような資料になってございます。
この議会議員の定数、任期につきましては、2点ご議論をいただきたいというふうに考えております。選択肢の中に、(1)、(2)というふうに書いてございます。1点目につきましては、合併特例法に基づく特例措置の適用の有無ということについて、ご協議をいただきたいというものでございます。原則どおり、合併時に設置選挙を行うというやり方がまずあります。それから、2番目に定数特例を適用するやり方があります。それから在任特例を適用するやり方がございます。これについては、後ほどご説明申し上げますが、その3つになろうかと思いますけれども、いずれかをこの協議会の中でご決定をいただくということになるわけでございます。そして、もう一点が、新しい町、新市の議会議員の条例定数についてご協議をいただくというものでございます。これにつきましては、後ほどご説明申し上げますが、地方自治法の中に、人口規模によりまして上限値が決まってございます。それらをもとに、合併する前にご協議をいただいて、各3町の議決を事前に受けていただくというような手続になるというものでございます。
それでは、内容等について、若干説明させていただきます。
まず、1番の議会議員の定数及び任期の取り扱いということで、先ほど原則どおりがまずございますということをお話し申し上げました。今の3町の廃止と同時に議員さん方の身分は原則的には失職という形になりますので、合併の日から50日以内に、地方自治法の上限、91条第2項にその上限数が載ってございます。91条の抜粋が16ページの上に載ってございますので、若干確認を願いたいというふうに思いますが、91条第2項第5号におきまして、人口5万未満の市及び人口2万人以上の町村の上限数については、26人というふうに定められております。これをもとに、新しい市の議会議員の定数を定めていただく、それによって設置選挙を行うというのが原則の方法でございます。
そして、もう一つ、合併特例法第6条の定数特例を適用というやり方がございます。それにつきましては、ただいまの設置選挙と同じように、50日以内に選挙を行うというところまでは同じでございますが、市町村ができまして最初に行う設置選挙に限りまして、先ほど地方自治法91条第2項の上限数を26人と申し上げましたが、この2倍、52人の範囲内で定数を定めて選挙を行うことができます。繰り返しになりますが、これは設置選挙のみに適用という形になりますので、その後行われる一般選挙につきましては、最初の26の範囲内で定めた条例定数に戻るというものでございます。
そして、合併特例法の7条に在任特例という特例が設けられてございます。これにつきましては、合併前に3町の協議によりまして、合併後2年を越えない範囲内で定める期間、2年でも構いません、1年でも構いません、1カ月でも構いませんということになると思いますけれども、そういう形で、引き続き新市の議会議員として在任ができるということになります。したがいまして、設置選挙については、これを行わないというような形になるものでございます。
そのことが、こちらで説明しているかと思いますが、17ページに一つの例示という形で書いてございます。この表につきましては、あくまでも制度の内容をわかりやすくするために一つの例として期日等、仮に記載したものでございますので、あらかじめ誤解のないようにご了解をいただきたいというふうに思います。こちらの表を見ていただきますと、原則どおりがこのような形になりますと、26人の範囲内で設置選挙を行い、その後の一般選挙も同じ形でということでございます。定数特例につきましては、最初の設置選挙に限り26の2倍の52人の範囲内で定数を定めることができまして、その後に行う一般選挙につきましては26になるという形になります。それから、在任特例につきましては、合併後2年の範囲、最大2年ということで、引き続き現在の議員さん方が在任をし、2年を越えない範囲で定めた期間の経過後においては、一般選挙を、それについては先ほどの地方自治法の91条第2項の上限数の範囲内の定数で行うということでございます。その3つから選択していただくという形になるということでございます。
恐縮でございます、14ページにお戻りをいただきたいと思います。中段に、3町の議会議員の定数、任期が載っております。ご案内のとおりでございますので、ごらんいただくだけにしていただければというふうに思います。
それから、2番、新市議会議員の条例定数についてということで、市町村の設置を伴う配置分合をしようとする場合、新設合併の場合、合併前に合併関係市町村で協議し、議会の議決を経て、新市の議会議員の定数を定めなければならないというふうになってございます。したがいまして、この協議会でご協議いただきまして、3町の議会で議決をお願いするというものになるということでございます。
それから、一つの議会の定数については、先ほどの上限の数、それから、参考までに15ページの上段に、県内の市で、人口がある程度類似する市の条例定数をこちらに掲載をさせていただきましたので、こちらについても参考にしていただきたいというふうに思います。
これが今回ご協議いただく2点の説明でございます。
18ページの方をごらんいただきたいと思います。18ページの方に、15年4月以降の合併事例でどんな取り扱いがなされているのかということで、全部ではございませんが、例として、こちらの方に載せさせていただいてございますので、後ほどまたごらんをいただきたいというふうに思います。
議会議員の定数及び任期の取り扱いにつきましては、以上でございます。
続きまして、建設計画の策定方針について説明を申し上げます。担当を計画担当の森坂の方にかわりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○横山会長
1時間たちましたので、ここで休憩を取りたいと思います。
(休憩)
○横山会長
それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きたいと思います。
事務局より説明をお願いします。
○森坂計画班長
事務局の森坂です。よろしくお願いします。
資料の方、提案事項4)ということで、21ページからとなってございます。新市建設計画の策定方針(案)についてということでございますが、まず初めに、資料23ページ、最後のページをごらんになっていただきたいと思います。新市の建設計画の位置づけでございますが、新市建設計画の法的役割としましては、合併特例法の第5条第2項で、市町村建設計画は合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならないということで、規定がございます。この建設計画の作成に当たりましては、4項目ほど、作成する事項ということで、同じく合併特例法の第5条第1項で、規定がございます。
1つ目としましては、合併市町村の建設の基本方針、2つ目としまして、合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項、3つ目としまして、公共的施設の統合整備に関する事項、4つ目としまして、合併市町村の財政計画ということでございます。
また、市町村建設計画は、合併協議会が作成し、変更するものであり、合併特例法に基づく財政措置を受けるためには、この計画の作成が前提となってございます。
次に、新市の建設計画の位置づけでございますが、合併市町村の将来に対するまちづくりのビジョンを示し、いわばマスタープランとしての役割を果たす重要な建設計画ということでございます。
2つ目としましては、当該計画に基づいて合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進し、地域全体のレベルアップを実現するものでして、ハード面の整備とあわせまして、ソフト面の事業にも配慮をしまして、真に新市の建設に資する事業を選び、合理的で健全な財政運営に裏づけられた計画とすべきものですということでございます。
3つ目としまして、市町村の総合計画は地方自治法の規定に基づき策定するもので、その意義は、市町村が将来を見通した長期にわたる経営の基本を確立するとともに、個性と魅力にあふれたまちづくりを進めるための基本となるものでございます。さらに、その役割として、市町村が発展するために長期的な視野のもとに施策の選択、優先順位の決定を行うなど、計画的な行政運営の指針となるものでございます。
以上のようなことで、新市の建設計画は、3町の現在の総合計画の理念等に基づきまして、基本方針等を策定していきます。
以上が新市建設計画の位置づけでございます。
資料を1枚戻っていただきまして、22ページになります。新市の建設計画の策定手順(案)でございますが、まず、基本となります策定方針の決定ということで、今回提案となってございます新市建設の策定方針の決定を、まずしていただきます。
そして、その策定方針に基づきまして、計画の原案を作成し、協議を行います。その原案を住民説明会の開催ということで、それぞれ住民の方にご説明をしまして、それには茨城県での事前協議ということで協議を行いまして、原案の加除修正を行いまして、計画原案の協議及び決定ということで、この協議会の中で計画原案の決定をさせていただきます。そして、それをもとに、茨城県へ正式協議をし、最終的に協議会において計画の決定というものになってございます。
さらに、最終的に、できました計画を住民の方に報告ということで、説明をさせていただくという形になってまいります。
以上が、新市建設計画の策定手順(案)でございます。
以上のことを踏まえまして、提案事項としまして、新市建設計画の策定方針(案)でございますが、新市建設計画は、新市のまちづくりの方向性を示すマスタープランとして、3町の実情にあわせて策定します。市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)に基づき、その策定方針とします。
1つ目としまして、計画の趣旨、本計画は、麻生町、北浦町、玉造町の合併後の新しいまちづくりを進めるために基本方針を定め、その実現により、3町の速やかな一体化、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図ろうとするものであります。
2番目としまして、計画の構成、本計画は、新市のまちづくりを推進するための基本方針、基本方針を実現するためのまちづくり計画、公共的施設の統合整備、及び財政計画を中心とした構成とします。
3つ目としまして、計画の期間でありますが、本計画における基本方針は、将来を見据えた長期的視点に立つものとし、まちづくり計画、公共的施設の統合整備及び財政計画は、平成17年度から平成26年度までの10年間について定めるものです。
次に、4番としまして、その他、財政計画の策定に当たっては、地方交付税、国や県の補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることなく、健全に財政を運営するよう十分留意するものであります。
以上が、新市建設計画の策定方針(案)でございます。
よろしくお願いします。
○横山会長
それでは、ただいま提案事項1から4、1ページから23ページまで、ご説明をいたしたわけでありますけれども、ここで、皆さんにご質問をいただきたいと思います。どうぞ、どんどん聞いてください。
第3回の合併協議会で、提案します。そして、皆さんに結論を出していただきたいというふうに思いますので、わからない点がありましたら、どうぞ、今日、聞いていただきたいと思います。
宮内委員。
○宮内(守)委員
新市の事務所の位置についてということで、今、ご説明があったわけですが、この事務所の位置については、次回決定したいというお話ですが、まず、そうですか、お聞きしたいと思います。
○横山会長
第3回目の協議会で協議をしたいと思います。それは、合意になれば決めてもらうということで、お願いしたいと思います。
○宮内(守)委員
3町の協議会になって2回目ですか。これは麻生、北浦のことをいっては大変恐縮、この問題については何回か、それぞれの思い、いろいろあったんだと思いますが、1回では決まらなかった経過はあるようですが、私としては慎重にこの次に自分の意見を持って臨みたいと思いますが、いろいろな事務所の位置だけでなくて、関連して、方式、設置方式、こういうものも関連してくるのかなと思っているんですが、ひとつ事務局の方にお聞きしたいんですけれども、2ページの方の主な官公署の状況の中で、北浦町は真っ白なんですけれども、これはミスではないんですね。そこを確認したいんですが。
○江寺事務局次長
ここの住民生活に密接に関係のするものということで、代表的なものを書かせていただきました。例えば、麻生の欄を見ていただいても、実はレイク・エコーなど載っておりませんで、そういう趣旨でございます。ご理解いただきたいというふうに思います。
○宮内(守)委員
ここに何か一つ書き込んでもらえれば、いいんですが。
○江寺事務局次長
回答ではないんですけれども、他の合併協議会の事例ですと、事務所の位置というのは当然1回ではなかなか決まらないのかなと思っています。うちの方で、事務局としては、皆さんに議論をいただきながら、その都度必要な資料を提示させていただきながらということで考えておりますので、その辺はまた協議の進捗状況を踏まえまして、事務局の方でもなるべくわかりやすい資料、なるべく検討が進みやすい資料ということで作成させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○横山会長 齋藤委員。
○齋藤委員
北浦の齋藤ですけれども、3町での新しい枠組みでのスタートということなんですけれども、そういう経緯を踏まえて、住民の皆さんへのアンケートですね。新市建設計画についてのアンケートをとるというようなことは考えているんでしょうか。
○横山会長 事務局の方でお答えを願います。
○江寺事務局次長
事務局内部で今、整理している段階のレベルのお話ということでお聞きいただきたいんですが、アンケートについては既に麻生、北浦町については実施をしているということでございます。以前に実施したアンケート以上のアンケートがあるのかというと、なかなかあれ以上ということも非常に難しいのかなというふうに思っております。ただ、玉造町さんについては、まだ我々住民の方々の意向をうかがっておりませんので、その点については何かしら、アンケートなり、何なり、実施する必要があるのかなというふうに考えておるところでございます。3町の合併協議については、2町の時代については町の広報紙を通じて合併協議の内容をお知らせしておりましたけれども、今回から住民の方々への周知ということにつきましては、合併協議会の方で協議会だよりを毎月1回発行するということを考えております。また、建設計画等においても、いろいろな形でまた説明なり意見を聞くということを実施してまいりたいというふうに思っております。今の、現状の考え方というのは、そういうような状況でございます。
○横山会長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○横山会長 ほかにありますか。
橋詰委員。
○橋詰委員
橋詰なんですが、玉造の場合は全く白紙の状態で入らせていただきましたので、今のアンケートの話につきましても門外漢で、ちんぷんかんぷんでわからないということであります。また、この主な官公署の状況につきましても、これは合併とは全く無関係というふうに私は、玉造の方では考えております。
それで、次回の提案理由の件なんですが、新市の事務所の位置についてという案件と、新市建設計画の策定方針、これは分離してやるというのも一つの方法でしょうが、これは事と次第によっては連動してくる問題もあるかと思います。ご承知のとおり、玉造の場合は、絶対的な条件で玉造の議会が通ったわけではありませんので、やはり地域周辺に対する配慮というのと連動してこの事務所ということも考えなければならないという部分もありますので、そこら辺については、この個別進行ということに限らず、今度の提案の中で連動するものはその中で分離しないで連動して協議していただきたい、こういうようなところもあるものですから、この席で申し上げて、次回のことでしょうけれども、お願いをしたい、こう思っております。
○横山会長
ただいま、玉造の橋詰委員からお話がございました。それで、皆さんにお願いをしておきたいと思います。これは、三町三様、いろいろ考え方が違うと思います。しかしながら、これはお互いに話をして、議論をして、そして一つの方向性を見つけるという大事な会議でありますので、そこをお互いに、自分の町はこうだから、こうだということではなくて、ひとつ大局的な考えの中で議論をしていってほしいというふうに思います。ですから、それが決まらなかったら継続協議にしますから、だから、どんどん皆さんの意見を聞きたい。真剣にやりましょう。ひとつお願いをいたしたいと思います。
ほかにありますか。
○山崎和久委員
建物の現状、役場の現状というところで、麻生町、北浦町、玉造町の役場の面積と構造等が載っているんですが、RC2Fはわかるんですけれども、RCとSRCというのはどういう意味なのか、説明してもらいたいんですが。
○横山会長
では、事務局の方で説明をしていただきます。
○江寺事務局次長
RCについては鉄筋コンクリートでございます。それから、SRCについては鉄骨鉄筋コンクリート造りだというふうな呼び方だと思いますので、よろしくお願いいたします。
○横山会長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○横山会長 ほかにありますか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、ないようでございますので、提案事項の説明につきましては、以上のとおりとさせていただきます。
委員の皆様には、次回まで十分に検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
次に、議題の3でありますけれども、その他について、事務局から説明をお願いいたしたいと思います。
○江寺事務局次長
それでは、議題のその他について、1点ほどご連絡をさせていただきます。次回第3回協議会の日程でございます。前回お配りした日程表と同じ日程で開催をしたいと思います。5月12日水曜日、午後1時30分から、麻生町のレイク・エコーで開催の予定でございます。繰り返しになりますが、5月12日水曜日午後1時30分から、麻生町のレイク・エコーでございます。皆様、よろしくお願いを申し上げます。開催通知をあわせて後ほどお配りしますので、よろしくお願いします。
○横山会長
それでは、皆様方から、その他でありますか。
○塙委員
1時半というのは非常に忙しい、2時ぐらいにしてもらえれば非常に助かるんじゃないでしょうか。
○横山会長
開始時間を、ではそのようにさせていただきたいと思います。2時からということでこれから設定をしますので、2時でいいですか。
(「はい」の声あり)
○横山会長
では、そのようにします。
訂正して出し直します。
ほかにはその他でないですか。
(発言者なし)
○横山会長
それでは、議題につきましては以上でございます。
藤島県会議員の先生、何かございますか。
(「特にありません」の声あり)
○横山会長
ないということでございます。
それでは、委員の皆様方には長時間にわたりましてご協力をまことにありがとうございました。進行役を事務局に返させていただきます。ありがとうございました。
○一條事務局次長
それでは、坂本副会長より、閉会の言葉をお願いしたいと思います。
○坂本副会長
本日は行方郡行方合併協議会の第2回の協議会、雨の中ご苦労さまでございました。これで終了させていただきます。本日はご苦労さまでございます。