仠応強丗嬍憿挰栶応乽戝夛媍幒乿
仠埾忷忬岎晅
仠埾堳摍偺徯夘
仠偁偄偝偮
仠媍丂帠
丂乮侾乯曬崘帠崁
丂丂丂侾乯丂峴曽孲崌暪嫤媍夛婯栺偵偮偄偰
丂丂丂俀乯丂摨丂姴帠夛婯掱偵偮偄偰
丂丂丂俁乯丂摨丂帠柋嬊婯掱偵偮偄偰
丂丂丂係乯丂摨丂嵿柋婯掱偵偮偄偰
丂丂丂俆乯丂摨丂愱栧晹夛婯掱偵偮偄偰
丂丂丂俇乯丂摨丂暘壢夛婯掱偵偮偄偰
丂乮俀乯彸擣帠崁
丂丂丂侾乯丂暯惉侾俆擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼偵偮偄偰
丂乮俁乯嫤媍帠崁
丂丂丂侾乯丂峴曽孲崌暪嫤媍夛埾堳摍偺曬廣媦傃旓梡曎彏偵娭偡傞婯掱乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俀乯丂丂摨丂夛媍塣塩婯掱乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俁乯丂丂摨丂夛媍朤挳婯掱乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂係乯丂丂摨丂彫埾堳夛婯掱乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俆乯暯惉侾俇擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛帠嬈寁夋乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俇乯暯惉侾俇擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俈乯峴曽孲崌暪嫤媍夛偺僗働僕儏乕儖乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俉乯峴曽孲崌暪嫤媍夛娔嵏埾堳偺慖擟偵偮偄偰
丂乮係乯採埬帠崁
丂丂丂侾乯丂崌暪偺曽幃偵偮偄偰
丂丂丂俀乯丂崌暪偺婜擔偵偮偄偰
丂丂丂俁乯丂怴巗偺柤徧偵偮偄偰
丂丂丂係乯丂崌暪嫤掕崁栚乮埬乯偵偮偄偰
丂丂丂俆乯丂峴惌惂搙偺挷惍曽恓乮埬乯偵偮偄偰
仠 弌惾埾堳乮俁俇柤乯
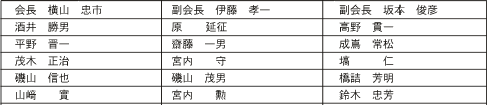 |
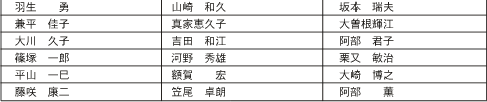 |
仠 寚惾埾堳乮側偟乯
仠弌惾屭栤
崄庢丂塹丂丂丂丂丂丂丂丂摗搰丂惓岶
仜悰扟帠柋嬊師挿
掕崗偪傚偭偲慜偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄奆偝傫偵偼戝曄偍懸偨偣傪偄偨偟傑偟偰丄偨偩偄傑傛傝戞侾夞偺峴曽孲崌暪嫤媍夛偺夛崌傪奐嵜偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂杮擔偼偦傟偧傟奆偝傫曽偵偼偍朲偟偄拞偛弌惾傪帓傝傑偟偰丄傑偙偲偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅巹偼摉崌暪嫤媍夛偺帠柋嬊師挿傪嬄偣偮偐偭偰偍傝傑偡嬍憿挰栶応偺婇夋壽偺悰扟偱偛偞偄傑偡丅傂偲偮傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅奐夛挰偲偄偆偙偲偱杮擔偺巌夛恑峴傪柋傔偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅壗暘偵傕傆側傟側晹暘偑偁傞偐偲巚偄傑偡偗傟偳傕丄偛嫤椡偺傎偳傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟傑偡丅
丂傑偨丄杮擔偼夛媍師戞偵増偭偰恑傔偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅偦偺慜偵丄夛挿丄暃夛挿偺慖擟偵偮偒傑偟偰偺偛曬崘傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂夛挿媦傃暃夛挿偵偮偒傑偟偰偼丄峴曽孲崌暪嫤媍夛婯懃戞俇忦戞侾崁偺婯掕偵傛傝傑偟偰丄俁挰偺挿偑嫤媍偟偰慖擟偡傞婯掕偲側偭偰偍傝傑偡丅愭斒丄俁挰偺挿偵偍廤傑傝偄偨偩偒傑偟偰嫤媍傪偄偨偟傑偟偨寢壥丄夛挿偵偼墶嶳杻惗挰挿丄偦偟偰暃夛挿偵偼埳摗杒塝挰挿丄摨偠偔嶁杮嬍憿挰挿偑偦傟偧傟慖擟偝傟偨偙偲傪丄傑偢傕偭偰偛曬崘傪偄偨偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂夛媍師戞偵傛傝傑偡偲丄師偵埾忷忬偺岎晅偲偄偆傆偆側偙偲偵側傞傢偗偱偛偞偄傑偡偑丄嫤媍傪奐嵜偡傞偵摉偨傝傑偟偰丄夛挿傛傝偙偺嫤媍夛偺朤挳摍偵偮偒傑偟偰奆條曽偵偍帎傝偄偨偟偨偄帠崁偑偛偞偄傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟傑偡丅
丂偦傟偱偼夛挿丄偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄戝曄杮擔偼偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偡丅
丂偁偄偝偮摍偵偮偒傑偟偰偼屻傎偳偝偣偰偄偨偩偔偲偄偆偙偲偵偄偨偟傑偟偰丄帠柋揑側揰偱偍婅偄傪偟偨偄帠崁偑偛偞偄傑偡丅偦傟偼朤挳偺審偱偛偞偄傑偟偰丄嫤媍夛偺夛媍偺朤挳偺庢傝埖偄偵偮偒傑偟偰偼丄杮擔偺嫤媍帠崁偺拞偱奆條曽偵偛嫤媍傪偄偨偩偔偲偄偆偙偲偵側偭偰偍傝傑偡偑丄嫤媍夛偺嫤媍撪梕偵偮偒傑偟偰峀偔廧柉偺奆偝傫偵岞奐偟偰傑偄傝偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡偺偱丄夛媍偺朻摢偐傜朤挳傪擣傔傞偲偄偆偙偲偵偮偒傑偟偰偛椆夝傪偄偨偩偒偨偄偲偄偆傕偺偱偛偞偄傑偡丅奆偝傫丄偄偐偑偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅堎媍側偟偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡偺偱丄夛媍偺朻摢偐傜朤挳傪擣傔傞偲偄偆偙偲偵偟偰傑偄傝偨偄偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
丂偦傟偱偼巌夛幰丄偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿
偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂偦傟偱偼丄夛挿偐傜埾忷忬偺岎晅傪偄偨偟偨偄偲懚偠傑偡丅杮棃偱偁傟偽埾堳偺奆條堦恖堦恖偵懳偟傑偟偰夛挿偺曽傛傝埾忷忬傪搉偡傋偒偲偙傠偱偛偞偄傑偡偑丄帪娫偺搒崌忋丄俁挰偦傟偧傟埾堳偺戙昞偺曽偵埾忷忬傪岎晅偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅偦偺懠偺埾堳偺奆條曽偵偼戝曄嫲弅偱偛偞偄傑偡偑丄偦傟偧傟偺偍庤尦偵攝晅偝傟偰偄傑偡惵偄晻摏偺拞偵埾忷忬偑摨晻傪偝傟偰偍傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偙傟偐傜奺挰俁柤偺戙昞偺偍柤慜傪偍屇傃偟傑偡偺偱丄墶嶳夛挿傛傝埾忷忬偺岎晅傪偍庴偗婅偄偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢弶傔偵丄杻惗挰偺嶳嶈泬條丄慜傊弌傑偟偰埾忷忬偺岎晅傪偍婅偄偟傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮埾忷忬岎晅乯
仜悰扟帠柋嬊師挿丂懕偒傑偟偰丄杒塝挰偺媨撪孧條丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮埾忷忬岎晅乯
仜悰扟帠柋嬊師挿丂懕偒傑偟偰丄嬍憿挰偺楅栘拤朏條丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮埾忷忬岎晅乯
仜悰扟帠柋嬊師挿
埲忋傪傕偪傑偟偰埾忷忬偺岎晅傪廔傢傜偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂師偵擖傞慜偱丄偙偙偱奆條偺偍庤尦偵攝晅傪偄偨偟傑偟偨帒椏傪偛妋擣偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄偙偺傛偆側僆儗儞僕怓偺僼傽僀儖偱杮擔偺戞侾夞峴曽孲崌暪嫤媍夛夛媍師戞偲偄偆傛偆側偙偲偱傕偭偰侾嶜偺偮偯傝偑攝晅偵側偭偰偍傝傑偡丅偦偟偰丄愭傎偳戙昞偱俁柤埾忷忬偺岎晅傪庴偗偨傢偗偱偛偞偄傑偡偑丄偦偺懠偺曽偵偮偄偰偼悈怓偺晻摏偺拞偵偦傟偧傟埾忷忬偑擖偭偰偄傞偐偲巚偄傑偡丅側偍丄傂偲偮帒椏偵偮偒傑偟偰偼丄俙俁偺偪傚偭偲暘岤偄昞巻偱峴惌惂搙摍偺尰嫷挷嵏媦傃挷嵏曽恓偲偄偆宍偱傕偭偰侾嶜丄寁俁揰偦傟偧傟偺埾堳偝傫偵攝晅偵側偭偰偄傞偐偲巚偄傑偡丅偛妋擣偺傎偳傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄埾堳媦傃屭栤偺奆偝傫偺偛徯夘傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲懚偠傑偡丅傑偙偲偵嫲弅偲偼懚偠傑偡偑丄杮棃偼帺屓徯夘宍幃傕偁偭偨偐偲偼巚偄傑偡偑丄巹偺曽偱偦傟偧傟偺偍柤慜傪偍屇傃偟丄徯夘偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂夛挿丄杻惗挰挿丄墶嶳拤巗條偱偡丅
仜墶嶳夛挿丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂暃夛挿丄杒塝挰挿丄埳摗岶堦條偱偡丅
仜埳摗暃夛挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔暃夛挿丄嬍憿挰挿丄嶁杮弐旻條偱偡丅
仜嶁杮暃夛挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰媍夛媍挿丄庰堜彑抝條偱偡丅
仜庰堜埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰媍夛暃媍挿丄暯栰怶堦偝傫偱偡丅
仜暯栰埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰媍夛媍堳丄栁栘惓帯條偱偡丅
仜栁栘埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰媍夛媍堳丄堥嶳怣栫條偱偡丅
仜堥嶳乮怣乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰傛傝偺埾堳偱偛偞偄傑偡嶳嶈泬條偱偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔塇惗桬條偱偡丅
仜塇惗埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔寭暯壚巕條偱偡丅
仜寭暯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔戝愳媣巕條偱偡丅
仜戝愳埾堳丂戝愳偱偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰廂擖栶丄幝捤堦榊條偱偡丅
仜幝捤埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杻惗挰嫵堢挿丄暯嶳堦枻條偱偡丅
仜暯嶳埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰媍夛媍挿丄尨墑惇條偱偡丅
仜尨埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰媍夛暃媍挿丄釼摗堦抝條偱偡丅
仜釼摗埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰媍夛媍堳丄媨撪庣條偱偡丅
仜媨撪乮庣乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰媍夛媍堳丄堥嶳栁抝條偱偡丅
仜堥嶳乮栁乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰偺慖弌偱偛偞偄傑偡媨撪孧條偱偡丅
仜媨撪乮孧乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔嶳嶈榓媣條偱偡丅
仜嶳嶈乮榓乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔恀壠宐媣巕條偱偡丅
仜恀壠埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔媑揷榓峕條偱偡丅
仜媑揷埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰廂擖栶丄壨栰廏梇條偱偡丅
仜壨栰埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂杒塝挰嫵堢挿丄妟夑岹條偱偡丅
仜妟夑埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰媍夛媍挿丄崅栰娧堦條偱偡丅
仜崅栰埾堳丂傛傠偟偔偳偆偧偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰媍夛暃媍挿丄惉浉忢徏條偱偡丅
仜惉浉埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰媍夛媍堳丄敺恗條偱偡丅
仜敺埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰媍夛媍堳丄嫶媗朏柧條偱偡丅
仜嫶媗埾堳丂嫶媗偱偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰丄楅栘拤朏條偱偡丅
仜楅栘埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔嶁杮悙晇條偱偡丅
仜嶁杮埾堳丂嶁杮偱偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔戝慮崻婸峕條偱偡丅
仜戝慮崻埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔垻晹孨巕條偱偡丅
仜垻晹乮孨乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰廂擖栶丄孖枖晀帯條偱偡丅
仜孖枖埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂嬍憿挰嫵堢挿丄戝嶈攷擵條偱偡丅
仜戝嶈埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂堬忛導憤柋晹巗挰懞壽挿丄摗嶇峃擇條偱偡丅
仜摗嶇埾堳丂偳偆偧傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂堬忛導婇夋晹抧堟寁夋壽挿丄妢旜戩楴條偱偡丅
仜妢旜埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂堬忛導幁峴抧曽憤崌帠柋強挿丄垻晹孫條偱偡丅
仜垻晹乮孫乯埾堳丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂懕偒傑偟偰丄摉嫤媍夛偺屭栤偺愭惗曽傪偛徯夘偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂堬忛導媍夛媍堳丄崄庢塹條偱偡丅
仜崄庢屭栤丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔堬忛導媍夛媍堳丄摗搰惓岶條偱偡丅
仜摗搰屭栤丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿
偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅埲忋偱徯夘偺曽傪廔傢傜偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄摉嫤媍夛偺帠柋嬊偺怑堳偺徯夘傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂奆偝傫偐傜岦偐偭偰塃庤偵側傝傑偡偑丄塇惗帠柋嬊挿偱偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂堦瀶帠柋嬊師挿偱偡丅
仜堦瀶帠柋嬊師挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂峕帥帠柋嬊師挿偱偡丅
仜峕帥帠柋嬊師挿丂傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂塱曯憤柋斍挿偱偡丅
仜塱曯憤柋斍挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂怷嶁寁夋斍挿偱偡丅
仜怷嶁寁夋斍挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂堥嶳挷惍斍挿偱偡丅
仜堥嶳挷惍斍挿丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂垻晹彂婰偱偡丅
仜垻晹彂婰丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔敀捁彂婰偱偡丅
仜敀捁彂婰丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂摨偠偔徏怣彂婰偱偡丅
仜徏怣彂婰丂傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿
巹偼愭傎偳偍榖偟偟傑偟偨偗傟偳傕丄帠柋嬊師挿傪偟偰偍傝傑偡悰扟偱偛偞偄傑偡丅
丂埲忋偑帠柋嬊偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
丂偦傟偱偼丄懕偒傑偟偰墶嶳夛挿傛傝偛偁偄偝偮傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偙偺偨傃峴曽孲崌暪嫤媍夛偺夛挿傪嬄偣偮偐傝傑偟偨杻惗挰挿偺墶嶳偱偛偞偄傑偡丅戞侾夞峴曽孲崌暪嫤媍夛偺奐嵜偵摉偨傝傑偟偰丄堦尵偛偁偄偝偮傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂埾堳偺奆條曽丄偦偟偰屭栤傪偍堷偒庴偗偄偨偩偒傑偟偨導媍夛媍堳偺崄庢愭惗丄偦偟偰摗搰愭惗偵偼丄戝曄偛懡朲拞偺偲偙傠偛椪惾傪帓傝傑偟偰丄傑偙偲偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅傑偨丄奆條曽偵偼暯慺傛傝摉抧堟偺敪揥偺偨傔偵偄傠偄傠側棫応偐傜偛巟墖偲偛嫤椡傪偄偨偩偄偰偍傝傑偡偙偲偵偮偒傑偟偰傕丄夵傔偰岤偔屼楃傪怽偟忋偘傞師戞偱偛偞偄傑偡丅
丂偝偰丄擮婅偱偁傝傑偟偨峴曽孲俁挰偵傛傞朄掕崌暪嫤媍夛偑偙偺俁寧15擔偵敪懌傪偄偨偟傑偟偨丅偒傚偆偙偙偵戞侾夞栚偺崌暪嫤媍夛傪奐嵜偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅堦偮偺僴乕僪儖傪墇偊傞偙偲偑偱偒偨偺偐側偲偄偆埨揼姶偲丄崱屻偺抧堟偺敪揥偺偨傔丄崌暪傪側偟悑偘側偗傟偽側傜側偄偲偄偆丄壥偨偡傋偒栶妱偺廳偝偵怴偨側嬞挘姶傪妎偊偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂彮巕崅楊壔偺恑揥傗挿堷偔宨婥掅柪偺拞偱丄抧曽嵿惌偑婋婡揑忬嫷偵偁傞側偳丄変乆抧曽帺帯懱傪庢傝姫偔娐嫬偼崱傑偱偲偼斾妑偵側傜側偄傎偳嬌傔偰尩偟偄忬嫷偲側偭偰偄傞偲偙傠偱偁傝傑偡丅傑偨丄抧曽暘尃偺悇恑偵傛傝傑偟偰丄偙傟傑偱偵傕傑偟偰岠棪揑側岠壥揑側峴嵿惌塣塩偺妋棫偑媫柋偲偄偆偙偲偵側偭偰偍傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅偙傟傜偵懳張偡傞桳岠側庤抜偺堦偮偑巗挰懞崌暪偱偁傝丄変乆偵偲偭偰嬞媫偺壽戣偲偄偆偙偲偵側偭偰偍傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂摉抧堟偺崌暪傪峫偊傑偡偲偒丄杒塝傪娷傔偨夃儢塝偵戙昞偝傟傑偡悈偲椢偵宐傑傟丄嶻嬈摍偺宱嵪妶摦傕椶帡偄偨偟偰偍傝丄傑偨偛傒張棟側偳偵偮偒傑偟偰傕丄堦晹帠柋慻崌傪摨偠偔偟偰偄傞偙偺俁挰偵傛傞崌暪偑怴偟偄抧堟偯偔傝傪恑傔傞忋偱嵟椙偺宍偱偁傞偲巹偼妋怣傪偄偨偟偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅偙偺抧偵廧傫偱傛偐偭偨偲巚偊傞傛偆側怴偟偄傑偪偯偔傝傪恑傔傞偨傔偺巗挰懞崌暪偲埵抲偯偗丄奆條曽偲嫤媍傪偟偰傑偄傝偨偄偲峫偊偰偍傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂傑偨丄崌暪偼抧堟偺奆偝傫偺偨傔偺傕偺偱側偔偰偼側傝傑偣傫丅忣曬採嫙摍偵搘傔丄奐偐傟偨嫤媍夛偺塣塩傪恾傞偙偲偵傛傝傑偟偰丄廧柉偺曽乆偺崌暪偵懳偡傞棟夝傪怺傔偰傑偄傝偨偄偲峫偊偰偍傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂巗挰懞偺崌暪偺摿椺偵娭偡傞朄棩偵偮偒傑偟偰偼丄偦偺宱夁慬抲偑崱崙夛偱媍寛偝傟傞尒捠偟偲暦偒媦傫偱偍傝傑偡偗傟偳傕丄偄偢傟偵偄偨偟傑偟偰傕婜尷偑愝偗傜傟偰偁傝傑偡丅尷傜傟偨帪娫偺拞偱俁挰偺榞慻傒偵傛傝敀巻偺忬懺偐傜嫤媍傪恑傔偰偄偔傢偗偱偛偞偄傑偡偺偱丄埾堳偺奆條曽偵偍偐傟傑偟偰偼婖溳偺側偄偛堄尒傪偄偨偩偒偨偄偲丄偦偟偰墌妸偵嫤媍偑恑傔傜傟傑偡傛偆丄偛棟夝偲偛嫤椡傪傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偨丄崄庢愭惗丄摗搰愭惗偵偍偐傟傑偟偰偼丄偙偺俁挰偺崌暪偑偤傂偲傕幚尰偱偒傑偡傛偆丄堷偒懕偒偛巜摫偲偛巟墖傪帓傝偨偔丄傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偟偰丄巹偺偁偄偝偮偵偐偊傞師戞偱偁傝傑偡丅
丂杮擔偼戝曄偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂懕偒傑偟偰丄埳摗暃夛挿傛傝偛偁偄偝偮傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜埳摗暃夛挿
偙偺偨傃峴曽孲崌暪嫤媍夛偺暃夛挿傪嬄偣偮偐傝傑偟偨杒塝挰挿偺埳摗偱偛偞偄傑偡丅戞侾夞嫤媍夛偺奐嵜偵摉偨傝丄堦尵偛偁偄偝偮怽偟忋偘傑偡丅
丂偨偩偄傑墶嶳夛挿偝傫偐傜偍榖偑偁傝傑偟偨傛偆偵丄擮婅偺峴曽孲俁挰偵傛傞崌暪嫤媍夛偑敪懌偄偨偟傑偟偨丅嬍憿挰偝傫偺嶲壛傪怱偐傜娊寎偟丄偦偟偰杮擔丄戞侾夞偺夛媍偑奐嵜偱偒傑偟偨偙偲傪戝曄偆傟偟偔姶偠偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂杻惗挰丄嬍憿挰丄杒塝挰偺俁挰偼丄偙傟傑偱偦傟偧傟偺屄惈傪敪婗偟側偑傜傑偪偯偔傝傪恑傔偰傑偄傝傑偟偨丅堦曽偱恖揑側岎棳傕偁傝丄摨偠傛偆側晽搚丄悈曈傪嫟桳偡傞側偳丄懡偔偺嫟捠揰傪帩偮俁挰偱偛偞偄傑偡丅偙偺俁挰偑21悽婭偲偄偆怴偟偄帪戙偵擖傝丄偝傜偵旘桇偡傞偨傔丄崌暪傪堦偮偺宊婡偲偟偰怴偟偄傑偪偯偔傝傪恑傔傞偙偲偼丄戝曄堄媊怺偄傕偺偲峫偊偰偍傝傑偡丅傑偨丄抧曽傪庢傝姫偔娐嫬偑擭乆尩偟偔側偭偰偍傝丄抧堟廧柉偺曽乆偵懳偡傞偝傑偞傑側僒乕價僗傪堐帩丒岦忋偡傞偨傔偵傕丄崌暪偼旔偗偰捠傟側偄傕偺偲峫偊偰偍傝傑偡丅
丂埾堳偺奆條曽偵偍偐傟傑偟偰偼丄抧堟偺彨棃傪嵍塃偡傞廳梫側嫤媍偱偛偞偄傑偡偺偱丄廧柉偺栚慄傪廳帇偡傞偲偲傕偵丄峀堟揑側帇揰偵棫偭偨偛堄尒傪偪傚偆偩偄偟丄僗儉乕僘側嫤媍傪恑傔偰偄偨偩偒偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅
丂傑偨丄導媍夛媍堳偺崄庢愭惗丄摗搰愭惗偵偍偐傟傑偟偰偼丄戝強崅強偐傜堷偒懕偒偛巜摫傪帓傝偨偄偲巚偄傑偡丅
丂墶嶳夛挿偝傫偲丄傑偨嶁杮暃夛挿偝傫偺俀恖偲偲傕偵丄変乆傕崌暪偵岦偗偰嵟戝尷偺搘椡傪偟偰傑偄傞強懚偱偛偞偄傑偡偺偱丄廳偹偰埾堳偺奆條曽偺偝傜側傞偛巟墖傪傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偟偰丄偁偄偝偮偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅杮擔偼傑偙偲偵偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂懕偒傑偟偰丄嶁杮暃夛挿傛傝偛偁偄偝偮傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜嶁杮暃夛挿
偙偺偨傃峴曽孲崌暪嫤媍夛偺暃夛挿傪嬄偣偮偐傝傑偟偨嬍憿挰挿偺嶁杮偱偛偞偄傑偡丅戞侾夞嫤媍夛偺奐夛偵摉偨傝丄堦尵偛偁偄偝偮怽偟忋偘傑偡丅
丂杻惗挰丄杒塝挰丄椉挰偺奆條曽偵偼丄婛偵嫤媍夛偑敪懌偟丄帠柋偺偡傝崌傢偣摍偑恑傓拞丄嬍憿挰偼帠忣偵傛傝崌暪嫤媍夛傊偺嶲壛偑偍偔傟偰偍傝傑偟偨偑丄崱夞丄摉挰偑怴偨偵嶲壛偡傞偙偲偵偛棟夝傪偄偨偩偒丄俀挰偵懳偟傑偟偰夵傔偰岤偔屼楃怽偟忋偘傞師戞偱偛偞偄傑偡丅傑偨丄杮擔偛弌惾傪偄偨偩偄偰偍傝傑偡導媍夛偺崄庢愭惗丄摗搰愭惗傪巒傔丄堬忛導幁峴抧曽憤崌帠柋強丄奺娭學婡娭偺奆條偵偼丄偛巜摫丄偛曏潱傪帓傝丄夵傔偰怺偔姶幱怽偟忋偘傞師戞偱偁傝傑偡丅
丂偍偐偘傪傕偪傑偟偰峴曽俁挰崌暪嫤媍夛傊偺嶲壛偵偮偒傑偟偰偺媍埬偑壜寛偝傟丄擮婅偱偁傝傑偟偨峴曽俁挰偺崌暪嫤媍夛偑敪懌偝傟傞塣傃偲側傝丄戝曄偆傟偟偔巚偭偰偄傞偲偙傠偱偁傝傑偡丅嬍憿挰偑壛傢傝丄怴偨偵峴曽俁挰偺嫤媍夛偑敪懌偡傞偙偲偲側傝丄婜尷撪崌暪偵岦偗偰壗偐偲偍朲偟偔側傞偐偲懚偠傑偡偑丄傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲懚偠傑偡丅
丂愭傎偳偍榖偑偁傝傑偟偨傛偆偵丄杻惗挰丄杒塝挰丄嬍憿挰偺俁挰偼丄摨偠峴曽孲撪丄偦偟偰嬤椬挰偲偄偆偙偲傕偁傝丄屆偔偐傜偝傑偞傑側岎棳偑偁傝丄傑偨峀堟帠柋慻崌偱偺奺庬帠嬈偵摨偠偔偟偰偍傝傑偡丅傑偨丄夃儢塝丄杒塝偵柺偟偰偺擾嶻嬈傪婎姴嶻嬈偲偡傞抧堟偱偁傝傑偡丅
丂挿堷偔晄嫷偺拞丄抧曽帺帯懱傪庢傝姫偔娐嫬偼傑偩傑偩尩偟偄忬嫷壓偵偁傝丄廧柉偺惗妶埨掕丄暉巸偺岦忋偵岦偗偰丄崌暪偼旔偗偰捠傟側偄帪戙偲側偭偰偍傝傑偡丅慡崙揑偵崌暪栤戣偼拝乆偲恑傫偱偄傞偲偙傠偱偁傝傑偡偑丄峴曽俁挰偺抧堟廧柉偺奆條偑崌暪偟偰傛偐偭偨偲尵傢傟傞傛偆丄柸枾側懪偪崌傢偣偑昁梫偱偁傝傑偡丅
丂杮擔偺嫤媍夛傪弌敪揰偲偟偰丄壗搙偲側偔嫤媍夛偑奐嵜偝傟傞偙偲偵側傝傑偡偑丄埾堳偺奆條偵偼壗偐偲偍朲偟偄拞偱偼偁傝傑偡偑丄峴曽俁挰偺枹棃偺偨傔丄偍椡揧偊傪帓傟傟偽岾偄偲懚偠傑偡丅傑偨丄崄庢愭惗丄摗搰愭惗偵偍偐傟傑偟偰偼丄偝傑偞傑側妏搙偐傜偛巜摫傪帓傝偨偄偲懚偠傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
丂巹傕丄墶嶳夛挿丄埳摗暃夛挿偲偲傕偵丄崌暪偵岦偗偰嵟戝尷偺搘椡傪偟偰傑偄傝傑偡偺偱丄埾堳偺奆條偵傕偛巟墖丄偛嫤椡傪偍婅偄怽偟忋偘傑偟偰丄偁偄偝偮偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅杮擔偼傑偙偲偵偛嬯楯偝傑偱偡丅傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂師偵丄偦傟偧傟岞巹偲傕偵戝曄偍朲偟偄偲偙傠傪摉嫤媍夛偺屭栤傪偍堷偒庴偗偄偨偩偒傑偟偨峴曽孲慖弌偺導媍夛媍堳偱偛偞偄傑偡崄庢塹愭惗傛傝偛偁偄偝偮傪偍婅偄偟偨偄偲懚偠傑偡丅
仜崄庢屭栤
偨偩偄傑偛徯夘傪偄偨偩偒傑偟偨屭栤傪嬄偣偮偐傝傑偟偨抧尦偺導媍夛媍堳偺崄庢塹偱偛偞偄傑偡丅杮擔偼戞侾夞偺峴曽孲崌暪嫤媍夛丄杮摉偵偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偡丅
丂偛彸抦偺偲偍傝丄峴曽孲偺崌暪偵偮偒傑偟偰偼丄杻惗挰丄杒塝挰偱愭偵朄掕嫤媍夛傪愝偗傜傟丄偄傠偄傠偲嫤媍偑恑傫偱偍偭偨偲偙傠偱偛偞偄傑偡偑丄偙偺偨傃愭擔丄嬍憿挰偑嶲壛傪偝傟傑偟偰丄杮擔偙偙偵戞侾夞偺俁挰偱偺崌暪嫤媍夛偑奐嵜偱偒傑偡偙偲偵丄怱偐傜偍婌傃傪怽偟忋偘傑偡丅
丂崌暪偵偮偒傑偟偰偼丄愭傎偳墶嶳夛挿偝傫丄埳摗暃夛挿偝傫丄嶁杮暃夛挿偝傫偐傜傞傞偛偁偄偝偮偑偁偭偨偲偍傝偱偛偞偄傑偡丅崱丄変偑崙偱偼慡崙奺抧偱崌暪偵恑傫偱偍傞傢偗偱偛偞偄傑偡丅慡崙偱
3,200梋偺巗挰懞偑偁傞傢偗偱偛偞偄傑偟偰丄挭棃巗偲媿杧挰偑崌暪傪偄偨偟傑偟偰丄偙偆偄偆崌暪傪偟偨巗挰懞傕偛偞偄傑偟偰丄尰嵼慡崙偱偼 3,100梋偺巗挰懞偺俈妱埲忋偑朄掕嫤媍夛傪偮偔偭偰丄崌暪偵岦偗偰摦偒弌偟偰偄傞傢偗偱偁傝傑偡丅堬忛導偱偼83巗挰懞偑偁傞傢偗偱偡偑丄偦偺俈妱嬤偄58偺巗挰懞偑朄掕嫤媍夛傪偮偔偭偰崌暪偵岦偗偰摦偄偰偍傞傢偗偱偛偞偄傑偡丅偟偨偑偭偰丄83偺巗挰懞偑朄掕婜尷撪偵嫲傜偔50傪愗偭偰40婔偮偐偺巗挰懞偵側傞偱偁傠偆偲尵傢傟偰偍傞偲偙傠偱傕偛偞偄傑偡丅
丂偙偆偄偆拞偱丄巹丄摗搰愭惗偲傕偳傕屭栤偵悇嫇偝傟偨偲偄偆偙偲偼丄嵟廔揑偵偼導媍夛偵偍偒傑偟偰挰懞崌暪偼媍寛偡傞偙偲偵側偭偰偍傝傑偡丅彮偟偱傕導媍夛媍堳偑偙偺嫤媍夛偵嶲壛偟偰偄傠偄傠偲曌嫮偟側偝偄丄偙偆偄偆偙偲偱傕偁傠偆偐偲巚偭偰偍傝傑偡丅
丂導媍夛偱偼丄暯惉16擭搙偵摿暿埾堳夛傪愝抲偄偨偟傑偟偰丄偙傟偑巗挰懞崌暪偵敽偆怴惗妶寳偯偔傝挷嵏摿暿埾堳夛偲偄偆偺傪怴偟偔杮擭搙偼偮偔傝傑偟偰丄偦偟偰崌暪偵傛偭偰怴偟偄惗妶寳偑偱偒傞傢偗偱偛偞偄傑偟偰丄偦傟傜偵偮偄偰偄傠偄傠媍榑偟偰偄偙偆偲偄偆摿暿埾堳夛傕導媍夛偱愝抲傪尒偨偲偙傠偱傕偛偞偄傑偡丅巹偳傕偼屭栤偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡偐傜丄奆偝傫偲堦弿偵曌嫮偝偣偰偄偨偩偒偨偄丄偙偆巚偭偰偄傞傢偗偱偛偞偄傑偡丅偳偆偧傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅
丂偦偟偰丄朄掕婜尷撪偵俁挰偑尒帠偵崌暪偑払惉偝傟傑偡傛偆偵怱偐傜偛婜懸傪怽偟忋偘傑偟偰丄偛偁偄偝偮偵偐偊偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅杮擔偼傑偙偲偵偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂懕偒傑偟偰丄摨偠偔岞巹偲傕偵懡朲側偲偙傠屭栤傪偍堷偒庴偗偄偨偩偒傑偟偨峴曽孲慖弌偺導媍夛媍堳偱偁傝傑偡摗搰惓岶愭惗傛傝偛偁偄偝偮傪偍婅偄偟傑偡丅
仜摗搰屭栤
屭栤偵偛悇嫇傪偄偨偩偒傑偟偨摗搰偱偛偞偄傑偡丅峴曽俁挰偺怴偟偄榞慻傒偵傛傞崌暪嫤媍偑奐巒偝傟傞傢偗偱偁傝傑偡丅埾堳奺埵偵偼廫暘媍榑傪偝傟傑偟偰丄怴偟偄傑偪偯偔傝偑偱偒傞傛偆偛搘椡傪偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅巹傕崄庢愭惗偺偛巜摫傪偄偨偩偒側偑傜惛偄偭傁偄偛巟墖傪偟偰傑偄傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偡丅崌暪嫤媍偑弴挷偵恑傒丄怴偟偄巗偑抋惗偡傞偙偲傪偛婜懸傪怽偟忋偘傑偡丅偛嬯楯偝傑偱偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂偦傟偱偼丄攝晅偄偨偟傑偟偨夛媍師戞偵栠傝傑偟偰丄媍帠偵堏傜偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂崌暪嫤媍夛婯栺戞10忦戞俀崁偺婯掕偵傛傝丄墶嶳夛挿偵媍挿傪偍婅偄偟丄媍帠傪恑傔偰偄偨偩偒偨偄偲懚偠傑偡丅墶嶳夛挿丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄婯栺偵廬偄傑偟偰巄帪偺娫媍挿傪柋傔偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅偛嫤椡偺傎偳傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂杮擔偺弌惾埾堳偝傫偼36柤慡堳偱偛偞偄傑偡丅嫤媍夛婯栺戞10忦戞侾崁偵婯掕偄偨偟傑偡掕懌悢偵払偟偰偄傞偙偲傪偛曬崘怽偟忋偘傑偡丅
丂偦傟偱偼丄師戞偵廬偄傑偟偰媍帠傪恑傔偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄乮侾乯偺曬崘帠崁偱偛偞偄傑偡偑丄娭楢偑偁傝傑偡偺偱丄侾乯峴曽孲崌暪嫤媍夛婯栺偵偮偄偰丄俀乯姴帠夛婯掱偵偮偄偰丄俁乯帠柋嬊婯掱偵偮偄偰丄係乯嵿柋婯掱偵偮偄偰丄俆乯愱栧晹夛婯掱偵偮偄偰丄俇乯暘壢夛婯掱偵偮偄偰丄埲忋侾乯偐傜俇乯傑偱傪媍戣偲偄偨偟傑偡丅
丂帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜堦瀶帠柋嬊師挿
帠柋嬊偺堦瀶偱偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂崱丄媍挿偺採埬偑偁傝傑偟偨傛偆偵丄曬崘帠崁偲偄偆偙偲偱奆偝傫偺偍庤尦偵帒椏傪攝晅偟偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄侾乯偐傜俇乯偲偄偆偙偲偱丄偦偺奿岲偺傑傑彸擣帠崁側傝嫤媍帠崁偲偄偆偙偲偱戝曄惙傝偩偔偝傫側帠崁偑偛偞偄傑偡偺偱丄巹偺曽偼嬌傔偰帠柋揑偵側傞偐偲巚偄傑偡偗傟偳傕丄娙寜偵侾乯偐傜俇乯傑偱偛曬崘怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄侾儁乕僕偺峴曽孲崌暪嫤媍夛婯栺偲偄偆偙偲偱偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂愝抲偺戞侾忦偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄杻惗挰丒杒塝挰丒嬍憿挰乮埲壓乽俁挰乿偲偄偆丅乯偼丄抧曽帺帯朄戞 252忦偺俀戞侾崁媦傃巗挰懞偺崌暪偺摿椺偵娭偡傞朄棩戞俁忦戞侾崁偺婯掕偵婎偯偒丄崌暪嫤媍夛傪抲偔偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂柤徧偱偁傝傑偡偑丄峴曽孲崌暪嫤媍夛丄埲壓嫤媍夛偲偄偆偙偲偱偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂扴擟帠柋偱偁傝傑偡偑丄俁忦偵俁崁栚偁傝傑偡偑丄傑偢俁挰偺崌暪偵娭偡傞嫤媍丄俀崁偲偄偨偟傑偟偰巗挰懞寶愝寁夋偺嶌惉丄俁揰栚偵崌暪偵娭偟偰昁梫側帠崁偲偄偆偙偲偱丄偙偺俁揰傪廳揰偵偙傟偐傜恑傔偰偄偔傢偗偱偁傝傑偡丅
丂帠柋強偱偁傝傑偡偑丄戞係忦丄俁挰偺挿偑嫤媍偟偰掕傔偨応強偵抲偔偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂慻怐偱偁傝傑偡偑丄戞俆忦埲壓丄傑偢嫤媍夛偼夛挿丄暃夛挿媦傃埾堳傪傕偭偰慻怐偡傞偲丅
丂夛挿媦傃暃夛挿偱偁傝傑偡偑丄夛挿媦傃暃夛挿偼丄俁挰偺嫤媍偑嫤媍偟丄師忦戞侾崁偺婯掕偵傛傝埾堳偲側傞傋偒幰偺拞偐傜偙傟傪慖擟偡傞偲偄偆偲偙傠偱偁傝傑偡丅
丂俈忦偺埾堳偱偁傝傑偡偑丄埾堳偵偮偒傑偟偰偼愭傎偳奆條偺曽偵埾忷忬偑岎晅偝傟傑偟偨偗傟偳傕丄侾揰偐傜俆揰栚偲偄偆偙偲偱俁挰偺挿丄俁挰偺媍夛偺媍挿媦傃暃媍挿丄媍挿偑偦傟偧傟巜柤偡傞媍堳俇柤丄挿偑嫤媍偟偰掕傔偨妛幆宱尡傪桳偡傞幰15柤丄俁挰偺挿偑偦傟偧傟巜柤偡傞俁挰偺怑堳俇柤偲偄偆偙偲偱峔惉傪偟偰偛偞偄傑偡丅
丂俀儁乕僕偵堏傝偨偄偲巚偄傑偡丅
丂夛媍偱偁傝傑偡偑丄嫤媍夛偺夛媍偵偮偒傑偟偰偼夛挿偑彽廤傪偡傞丅埾堳偺俁暘偺侾埲忋偺幰偐傜夛媍偺彽廤偺惪媮偑偁傞偲偒偼丄偙傟傪彽廤偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂夛媍偺奐嵜応強媦傃擔帪偼丄夛媍偵晅偡傋偒帠崁偲偲傕偵夛挿偑偁傜偐偠傔埾堳偝傫偵捠抦傪偡傞偙偲偵側偭偰偛偞偄傑偡丅
丂夛媍偺塣塩偱偛偞偄傑偡偑丄戞10忦偺拞偱丄嵼擟埾堳偺敿悢埲忋偑弌惾偟側偗傟偽丄偙傟傪奐偔偙偲偑偱偒側偄偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅夛媍偺媍挿偵偼丄夛挿偑偙傟偵摉偨傝傑偡丅
丂屭栤偱偁傝傑偡偑丄11忦偺拞偱愭傎偳偁傝傑偟偨傛偆偵丄俁挰偺挿偑嫤媍偟偰掕傔偨屭栤傪抲偔偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂彫埾堳夛偱偁傝傑偡偑丄嫤媍夛傪峴偆偲傕傠傕傠偺帠柋偑擖偭偰偔傞傢偗偱偁傝傑偡偑丄堦晹偺帠柋偵偮偒傑偟偰偼挷嵏丄怰媍摍傪峴偆偨傔偵彫埾堳夛傪抲偔偙偲偑偱偒傞偲丅彫埾堳夛偺拞偱偼丄夛挿偑偦傟偧傟巜帵偟側偑傜帎栤傪偟偰塣塩傪偡傞傛偆偵側偭偰偛偞偄傑偡丅
丂姴帠夛偱偛偞偄傑偡偑丄嫤媍夛偑採埬偡傞帠崁偵偮偒傑偟偰偼丄偙偺姴帠夛偺拞偱嫤媍傪偟側偑傜恑傔傞傛偆偵側傝傑偡偺偱丄嫤媍夛傪抲偄偰幚巤傪偟偰傑偄傝傑偡丅
丂帠柋嬊偱偁傝傑偡偑丄戞14忦偺拞偵嫤媍夛偵帠柋嬊傪抲偔偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂怑堳偵偮偒傑偟偰偼丄戞15忦偺拞偱俁挰偺挿偑嫤媍偟偰掕傔偨幰傪傕偭偰廩偰傞偲丅
丂宱旓偵偮偒傑偟偰偼丄16忦偺俁挰偑晧扴傪偟傑偡偲丅
丂娔嵏偱偁傝傑偡偑丄戞17忦丄弌擺偺娔嵏偼丄夛挿偑俁挰偺娔嵏埾堳偺偆偪偐傜嫤媍夛偺摨堄傪摼偰俁柤傪埾忷偟傑偡偲丅
丂師儁乕僕傪偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂俁儁乕僕偵側傝傑偡偑丄嵿柋偵娭偡傞帠崁偲偄偨偟傑偟偰丄梊嶼偺曇惉丄尰嬥偺弌擺偦偺懠嵿柋偵娭偟傑偟偰偼丄夛挿偺懏偡傞挰偺椺偵傛偭偰夛挿偑暿偵掕傔傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂曬廣媦傃旓梡曎彏偵偮偒傑偟偰偼丄戞19忦偵夛挿丄暃夛挿丄埾堳媦傃娔嵏埾堳偼丄曬廣媦傃偦偺怑柋傪峴偆偨傔偵梫偡傞旓梡曎彏傪庴偗庢傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂嫤媍夛偺攑巭婯掱偱偁傝傑偡偑丄戞20忦丄嫤媍夛傪攑巭偟偨応崌偵偍偄偰偼丄嫤媍夛偺廂巟偼攑巭偺擔傪傕偭偰懪偪愗傝丄夛挿偱偁偭偨傕偺偑偙傟傪寛嶼偡傞丅
丂偲偄偆偙偲偱丄偙偺婯栺偵偮偒傑偟偰偼俁寧15擔偐傜偺巤峴偵側偭偰偛偞偄傑偡丅
丂係儁乕僕偵峴曽孲崌暪嫤媍夛偺慻怐恾丅崱怽偟忋偘傑偟偨婯栺偺拞偱偺慻怐偑恾幃偟偰偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傞偲巚偄傑偡丅峴曽孲崌暪嫤媍夛偺埾堳偝傫36柤埲壓丄偙偺壓偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄姴帠夛丄嫤媍夛偵懳偡傞晅媍媍埬偺埬審媦傃娭學帒椏偺採弌摍傪怰媍偡傞姴帠夛偱偛偞偄傑偡丅
丂偝傜偵丄偦偺壓偵俈晹夛偲偄偆偙偲偱丄偙偺屻弌偰偒傑偡偗傟偳傕丄俁挰偺扴摉壽挿偝傫傪拞怱偵偟傑偡愱栧晹夛丄偝傜偵偼偦偺壓偵暘壢夛30偲偄偆偙偲偱丄俁挰偺扴摉壽挿傪拞怱偵幚嵺偺慻怐偺撪晹挷惍摍偺撪晹帠柋偺挷嵏傪偡傞傕偺偱偛偞偄傑偡丅
丂塃偺忋偺曽偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄嫤媍夛偺晅戸偵傛傝傑偟偰偦傟偧傟傪嫤媍偡傞彫埾堳夛偑偛偞偄傑偡丅
丂嵍偺曽偱偁傝傑偡偑丄姴帠夛偺嵍偱偁傝傑偡偑丄寭柋怑堳俁恖丄愱擟怑堳俈柤偲偄偆偙偲偱丄10柤帠柋嬊懱惂傪偲偭偰偛偞偄傑偡丅
丂偙傟偑戝傑偐側慻怐恾偱偁傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂師儁乕僕傪偍奐偒婅偄偨偄偲巚偄傑偡丅
丂峴曽孲崌暪嫤媍夛姴帠夛婯掱偲偄偆偙偲偱丄戞侾忦偺拞偵峴曽孲崌暪嫤媍夛偺姴帠夛偺慻怐媦傃塣塩偵娭偟偰昁梫側帠崁傪掕傔傞偲偄偆偙偲偱丄戞俀忦埲壓婰嵹偟偰偛偞偄傑偡丅姴帠夛偼丄嫤媍夛偺夛挿偺巜帵傪庴偗丄嫤媍夛偺夛媍偵採埬偡傞帠崁偵偮偄偰嫤媍傑偨偼挷惍傪偡傞傫偩偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂慻怐偵偮偒傑偟偰偼丄姴帠傪傕偭偰慻怐偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂戞係忦丄暿昞偺拞丄塃偺曽偵偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄杻惗挰丄杒塝挰丄嬍憿挰丄偦傟偵導偲偄偆偙偲偱丄偦傟偧傟扴摉壽挿丄導偺偦傟偧傟怑柋偺曽乆傪婰嵹偟偰偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傞偲巚偄傑偡丅
丂姴帠夛偵偮偒傑偟偰偼丄戞俆忦偵堏傝傑偡偗傟偳傕丄姴帠挿媦傃暃姴帠挿傪屳慖偱慖弌偟側偑傜崱屻偺嫤媍傪恑傔偰偄偔偙偲偵側偭偰偛偞偄傑偡丅徻嵶偵偮偒傑偟偰偼徣偐偣偰偄偨偩偄偰偍傝傑偡丅
丂晬懃偱偁傝傑偡偑丄偙偺婯掱偼暯惉16擭俁寧15擔偐傜巤峴偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂師儁乕僕丄俈儁乕僕偺曽傪偍奐偒偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂俈儁乕僕偵偮偒傑偟偰偼丄峴曽孲崌暪嫤媍夛帠柋嬊婯掱偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅偙傟偵偮偒傑偟偰偼丄戞侾忦偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄帠柋嬊偵娭偟偰昁梫側帠崁傪掕傔傞偲丅
丂戞俀忦偵強彾帠柋偲偄偨偟傑偟偰侾揰偐傜俆揰傎偳彂偄偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄夛媍偵娭偡傞偙偲丄嫤媍帒椏偺嶌惉偵娭偡傞偙偲丄峀曬媦傃岞挳偵娭偡傞偙偲丄弾柋偵娭偡傞偙偲傪捠偠側偑傜丄帠柋嬊偺拞偱帠柋傪強彾偟偰傑偄傝偨偄偲巚偄傑偡丅
丂戞俁忦偺拞偱慻怐偱偁傝傑偡偑丄偙偺拞偵憤柋斍丄寁夋斍丄挷惍斍傪抲偄偰恑傔傞傛偆偵側偭偰偛偞偄傑偡丅暿昞偵偮偒傑偟偰偼丄俋儁乕僕埲壓彂偄偰偛偞偄傑偡偺偱丄嶲峫偵尒偰偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅
丂怑堳摍偺怑柋偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄帠柋嬊偺帠柋傪憤妵偡傞偲偄偆偙偲偱丄偙傟偵偮偒傑偟偰傕帠柋嬊撪晹偺婯掱丄嵶偐偔彂偄偰偛偞偄傑偡偑丄戞係忦丄俆忦偺拞偱偛偞偄傑偡丅
丂寛嵸偵偮偒傑偟偰偼丄夛挿偑寛嵸偡傞帠崁偲偄偨偟傑偟偰戞俇忦偺拞偱嫤媍夛偺塣塩偵娭偡傞婎杮曽恓偺寛掕丄嫤媍夛偵採埬偡傞媍戣偺寛掕丄嫤媍夛偺梊嶼媦傃寛嶼丄係揰栚偵婯掱媦傃梫椞摍偺惂掕夵攑偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂帠柋嬊偺拞恎偺愱寛帠崁偱偛偞偄傑偡偑丄帠柋嬊偵偮偒傑偟偰偼侾揰偐傜俈揰傎偳偛偞偄傑偡帠崁偵偮偒傑偟偰偼愱寛傪偡傞偙偲偑偱偒傞丅偄偢傟偵偟傑偟偰傕撪晹帠柋揑側侾揰偐傜俈揰傎偳彂偄偰偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傞偲巚偄傑偡丅
丂戞俉忦偵偮偒傑偟偰偼丄暥彂偺埖偄偱偛偞偄傑偡丅
丂戞俋忦丄偙傟偵偮偒傑偟偰偼嫤媍夛偺岞報偼夛挿報丄夛挿怑柋戙棟幰報偲偡傞偲偄偆偙偲偱丄偙傟傕師儁乕僕埲崀丄暿昞俀偺曽偵偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅偙傟傜偵偮偒傑偟偰傕晬懃偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄暯惉16擭俁寧15擔偐傜巤峴偲偄偆偙偲偱丄帠柋嬊婯掱偑婯掕偟偰偛偞偄傑偡丅
丂師儁乕僕傪偍奐偒偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅俋儁乕僕偵偮偒傑偟偰偼丄暿昞侾丄暿昞俀丄暿昞條幃俁偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅
丂11儁乕僕傪偍奐偒婅偄偨偄偲巚偄傑偡丅峴曽孲崌暪嫤媍夛嵿柋婯掱偱偛偞偄傑偡丅嵿柋偵昁梫側晹暘偵偮偄偰婯掕傪偟偰偛偞偄傑偡丅
丂傑偢丄嵨擖嵨弌梊嶼偱偁傝傑偡偑丄戞俀忦偺拞偵嫤媍夛偺梊嶼偼杻惗挰丒杒塝挰丒嬍憿挰偐傜偺晧扴嬥媦傃偦偺懠偺廂擖傪傕偭偰廩偰傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅夛挿偼丄枅夛寁擭搙偵梊嶼傪挷惢偟偰嫤媍夛偵帎傞偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傑偡丅俁揰栚偵夛寁擭搙偱偁傝傑偡偑丄偙傟偵偮偒傑偟偰偼抧曽岞嫟抍懱偺夛寁擭搙傪揔梡偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂俁忦埲崀偵偮偒傑偟偰偼曗惓梊嶼丄偝傜偵偼條幃摍偱偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅
丂戞俆忦丄嫤媍夛偺弌擺偼夛挿偑峴偆偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅俀崁偵丄夛挿偑掕傔傞嬧峴偦偺懠偺嬥梈婡娭偵偙傟傪梐偗傞偲偄偆偙偲偱丄偙傟偼14儁乕僕偵偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄忢梲嬧峴杻惗巟揦傪嬥梈婡娭偲巜掕偟偰偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂嫤媍夛偺弌擺堳偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄戞俇忦偺拞偱夛挿偼嫤媍夛偺帠柋嬊怑堳偺拞偐傜嫤媍夛弌擺堳傪柦偢傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂12儁乕僕偵堏傝傑偟偰丄梊嶼偺棳梡側傝廩梡偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄偙傟傜偵偮偒傑偟偰偼夛挿偑懏偡傞挰偺椺偵傛偭偰嶌嬈傪偟傑偡偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
丂寛嶼偱偁傝傑偡偑丄夛挿偼丄枅夛寁擭搙廔椆屻俁僇寧埲撪偵嫤媍夛偺寛嶼傪挷惢偟丄娔嵏埾堳偺娔嵏偵晅偟偨屻丄嫤媍夛偺彸擣傪摼側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅偙傟傜偵偮偒傑偟偰傕丄暯惉16擭俁寧19擔偐傜巤峴偵側偭偰偛偞偄傑偡丅
丂晬懃偺俀崁栚偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄暯惉15擭搙偺嵨擖嵨弌梊嶼偵偮偒傑偟偰偼丄嫤媍夛偺夛挿偑偙傟傪挷惢偟丄嫤媍夛愝棫屻嵟弶偺夛媍偵偍偄偰曬崘偟丄彸擣傪摼傞傕偺偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偙偺屻丄採埬傪偝傟偰偍傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂13儁乕僕丄14儁乕僕偵偮偒傑偟偰偼丄帠柋揑側撪梕偱偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂15儁乕僕偺曽偵堏傝偨偄偲巚偄傑偡丅峴曽孲崌暪嫤媍夛愱栧晹夛婯掱偱偛偞偄傑偡丅偙傟傜偵偮偒傑偟偰偼丄愱栧晹夛偺慻怐側傝塣塩偵娭偟偰昁梫側帠崁傪掕傔傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂婯栺偺俀崁偵偛偞偄傑偟偨傛偆偵丄姴帠挿偺巜帵偵傛傝傑偟偰姴帠夛偱嫤媍傑偨偼挷惍偡傞帠崁偵偮偄偰丄愱栧揑偵嫤媍側傝挷惍傪偟傑偡偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅偙傟偵偮偒傑偟偰偼丄慻怐偵偮偒傑偟偰偼暿昞偵偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅
丂係忦偺拞偵丄愱栧晹夛偵偼晹夛挿丄暃晹夛挿傪抲偔偲偄偆偙偲偱嶌嬈傪恑傔傞傛偆偵側偭偰偍傝傑偡丅
丂夛媍偵偮偒傑偟偰偼丄姴帠挿偺梫惪偵傛偭偰丄傑偨偼晹夛挿偑昁梫偵墳偠偰悘帪奐嵜傪偟傑偡偲偛偞偄傑偡丅
丂戞俇忦偵偼暘壢夛偱偁傝傑偡丅偝傜偵愱栧晹夛偱嫤媍傑偨偼挷惍帠崁偵偮偄偰嬶懱揑帒椏偺嶌惉傪峴偆偨傔丄愱栧晹夛偵暘壢夛傪抲偔偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱丄愱栧晹夛丄暘壢夛偲偄偆俀抜宍幃偺拞偱偙偺嶌嬈偑恑傔傜傟傞傛偆偵側偭偰偍傝傑偡丅偙偺曈偵偮偒傑偟偰偼晬懃偺拞偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄婯掱偵偮偒傑偟偰偼暯惉16擭偺係寧俉擔偐傜巤峴偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂師儁乕僕傪偍奐偒婅偄偨偄偲巚偄傑偡丅16儁乕僕偵崱怽偟忋偘傑偟偨愱栧晹夛偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄偺憤柋丄廧柉丄暉巸埲壓丄僩乕僞儖俈偮偺愱栧晹夛偲偄偆偙偲偱丄峔惉偵偮偒傑偟偰偼丄杻惗挰丄杒塝挰丄嬍憿挰偺偦傟偧傟愱栧晹夛偵懏偡傞壽挿怑摍傪拞怱偵峔惉傪偟偰偍傝傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偙偆偲巚偄傑偡丅
丂17儁乕僕偵堏傝偨偄偲巚偄傑偡丅峴曽孲崌暪嫤媍夛暘壢夛婯掱偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅暘壢夛偺婯掱傪偙偺拞偱婯掕偟偰偛偞偄傑偡丅強彾帠柋偲偄偨偟傑偟偰偼丄愭傎偳愱栧晹夛偺拞偱偁傝傑偟偨傛偆偵丄愱栧晹夛偱嫤媍傑偨偼挷惍偡傞帠崁偵偮偄偰嬶懱揑帒椏偺挷惢傪峴偆偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂戞係忦偺拞偵丄暘壢夛偵偼暘壢夛挿媦傃暃暘壢夛挿傪抲偒傑偡偲丅
丂戞俆忦丄夛媍偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄夛媍偼暃夛挿偺梫惪偵傛傝丄傑偨偼暘壢夛挿偑昁梫偵墳偠偰奐嵜傪偟偰偄偒傑偡偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅偙傟偵偮偒傑偟偰傕愱栧晹夛偲摨偠傛偆偵丄晬懃偺拞偱偙偺婯掱偼暯惉16擭係寧俉擔偐傜巤峴傪偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂18儁乕僕偺曽傪偍奐偒婅偄偨偄偲巚偄傑偡丅18儁乕僕丄19儁乕僕偵偮偒傑偟偰偼丄崱怽偟忋偘傑偟偨暘壢夛丄30偺暘壢夛偑偁傞傢偗偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄憤柋偱怽偟忋偘傟偽丄憤柋偺拞偵偼暘壢夛偲偟傑偟偰婇夋丄峀曬丄嵿惌偲偄偆偙偲偱丄偦傟偧傟偙傟傜偺峔惉偵偮偒傑偟偰偼丄杻惗挰丄杒塝挰丄嬍憿挰偺偦傟偧傟學挿怑偵憡摉偡傞怑堳偑摥偔偙偲偵側偭偰偄傑偡丅偙偺傛偆側偙偲偱30偺暘壢夛偑偛偞偄傑偡偺偱丄偛傜傫傪偄偨偩偗偗傟偽偲巚偄傑偡丅
丂戝曄嶨敐偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄埲忋偛愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偼偄丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅偨偩偄傑曬崘帠崁偵偮偒傑偟偰愢柧偑偛偞偄傑偟偨丅撪梕摍偵偮偒傑偟偰丄偛幙栤摍偑偛偞偄傑偟偨傜丄偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅側偍丄偛敪尵偵摉偨傝傑偟偰偼儅僀僋傪偍帩偪偄偨偟傑偡偺偱丄嫇庤傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅傑偨丄夛媍榐嶌惉偺搒崌忋丄挰柤傑偨偼強懏丄偛帺暘偺偍柤慜傪偍偭偟傖偭偰偐傜敪尵傪偝傟傞傛偆丄偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偦傟偱偼丄偍婅偄偄偨偟傑偡丅壗偐偛幙栤摍偛偞偄傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄曬崘帠崁偵偮偒傑偟偰偼埲忋偺偲偍傝偲偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偱偼丄庰堜埾堳丄偍婅偄偟傑偡丅偪傚偭偲懸偭偰丄儅僀僋傪帩偭偰偒傑偡丅
仜庰堜埾堳
杻惗挰偺庰堜偱偡偑丄俉儁乕僕偺峴曽孲崌暪嫤媍夛帠柋嬊婯掱偺戞俈忦偱偡偐丄愱寛帠崁丄偙偺晹暘偺乽帠柋嬊挿偼丄師偵宖偘傞帠崁傪愱寛偡傞偙偲偑偱偒傞丅乿偲偁傝傑偡偑丄偙偺侾斣偲俀斣偼偦偺屻
500枩墌枹枮丄偁傞偄偼 300枩墌枹枮偺挷掕傗巟弌偵娭偡傞偙偲傪愱寛偡傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆傆偆偵偁傝傑偡偑丄偙傟偼偄偐偑側傕偺偐偲巹偼巚偆傫偱偡偑丄偦偺曈傪偍帎傝偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
崱丄庰堜埾堳偝傫偺曽偐傜偛幙栤偑偛偞偄傑偟偨丅帠柋嬊傛傝摎偊偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿丂偦傟偱偼丄偍摎偊傪偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偄傢備傞帠柋嬊挿偺戙棟寛嵸尃偲偱傕怽偟傑偟傚偆偐丄杮棃偱偁傟偽廂擖傕巟弌傕偡傋偰夛挿偺寛嵸偑昁梫偐偲巚傢傟傑偡偗傟偳傕丄愭傎偳採埬偑偛偞偄傑偟偨傛偆偵丄尰幚揑偵偼帠柋嬊偺埵抲偑杒塝挰栶応偱偛偞偄傑偡丅偦偟偰丄夛挿偺強嵼抧偑杻惗挰偱偛偞偄傑偡丅偦偆偄偭偨抧棟揑側忦審摍傕偛偞偄傑偟偰丄偙偺嵺丄帠柋嬊挿偵戙棟寛嵸尃傪梌偊偨偄偲偄偆偙偲偱偛採埬傪偟偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂庰堜埾堳偝傫丅
仜庰堜埾堳
偙偺婯栺偵傛傝傑偡偲丄夛挿偲帠柋嬊挿偼摨偠杻惗挰偺傛偆側婥偑偡傞傫偱偡偑丄偦傟偱楢棈偑偲傟側偄偲偐丄偦偆偄偆傛偆側偙偲偼嫲傜偔側偄偲巚偆丅偦傟偲丄彮側偔偲傕岞嬥偺偙偲偱偛偞偄傑偡偺偱丄夛挿偺椆夝傪偲偭偰愱寛偲偄偆傛偆側宍偺傕偺偼偄偐偑側傕偺偐偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡偺偱丄偱偒摼傟偽偦偺曈偺偲偙傠偼偒偪偭偲偟偰偄偨偩偒偨偄偲丄巹偺曽偐傜偛梫朷傪怽偟忋偘傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂偱偼丄帠柋嬊挿丄偍婅偄偟傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿丂偍摎偊偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂挰懞偺嵿柋婯掱摍偵傕戙棟寛嵸尃偑偛偞偄傑偟偰丄嬥妟偼懡彮偺偢傟偼偁傠偆偐偲巚偄傑偡偗傟偳傕丄偄偢傟偺挰懞偵偍偄偰傕廂擖偵偮偄偰偼 500枩墌丄偁傞偄偼巟弌偵偮偄偰偼挰懞偵傛偭偰偼
100枩墌丄偁傞偄偼壗廫枩偲偄偆傆偆側扨埵偱掕傔傜傟偰偍傞偲巚偄傑偡偗傟偳傕丄偄偢傟偵偟偰傕偦偆偄偭偨偙偲偱戙棟寛嵸尃偑梌偊傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偛偞偄傑偡偺偱丄偦偺揰偼傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂偄偄偱偡偐丅
仜庰堜埾堳丂偦傟埲忋偼尵傢側偄丅
仜墶嶳夛挿丂奆偝傫偼偳偆偱偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄帠柋嬊埬偱傂偲偮傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偱偼丄師偵堏傝偨偄偲巚偄傑偡丅乮俀乯偺彸擣帠崁丄暯惉15擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼偵偮偄偰傪媍戣偲偄偨偟傑偡丅帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜塱曯憤柋斍挿
帠柋嬊偺塱曯偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
丂偦傟偱偼丄乮俀乯偺彸擣帠崁偺匑偵偮偄偰偛愢柧傪偄偨偟傑偡丅
丂暯惉15擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛偺梊嶼偱偛偞偄傑偡丅偙偺梊嶼偵偮偒傑偟偰偼丄愭傎偳偺曬崘帠崁偺拞偺係斣栚偵偛偞偄傑偟偨傛偆偵丄嵿柋婯掱丄偦偪傜偺晬懃偺戞俀崁偺婯掱丄乽暯惉15擭搙偺嵨擖嵨弌偺梊嶼偵偮偄偰偼丄嫤媍夛偺夛挿偑偙傟傪挷惢偟丄嫤媍夛愝棫屻嵟弶偺夛媍偵偍偄偰曬崘偟丄彸擣傪摼傞傕偺偲偡傞丅乿偲偄偆偲偙傠偱偛採埬傪偡傞傕偺偱偛偞偄傑偡丅
丂傑偢丄嵨擖偵偮偒傑偟偰偼丄奺挰丄俁挰偺晧扴嬥偲偟偰 600枩墌丄奺挰偵 200枩墌偢偮偺晧扴嬥偲偄偆偙偲偺寁忋偱偛偞偄傑偡丅
丂嵨弌偵偮偒傑偟偰偼丄嫤媍夛偺弨旛宱旓偲偟偰帠柋旓傪20枩墌傎偳寁忋偟偰偛偞偄傑偡丅偦偺懠丄梊旛旓偲偟偰巆妟偵摉偨傝傑偡 580枩偺寁忋偱偛偞偄傑偡丅
丂幚巤偵偍偒傑偟偰偼丄杮擭偺俁寧15擔丄嫤媍夛愝抲偺擔偐傜枛擔傑偱偺17擔娫偺梊掕偲偄偆偙偲偱丄偛棟夝傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂側偍丄寛嶼偵偮偄偰偼丄偙偺屻丄杮擔丄娔嵏埾堳偝傫偺慖擟偑側偝傟偨屻偵丄夛寁娔嵏傪庴偗丄懍傗偐偵偙偺嫤媍夛偺曽偵偛採埬傪偟丄彸擣傪婅偄偨偄偲偄偆偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂埲忋偱偛偞偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偨偩偄傑帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅偦傟偱偼丄偛堄尒丄偛幙栤摍傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅壗偐偛偞偄傑偡偐丅
丂偼偄丄偳偆偧丅偪傚偭偲偍懸偪偵側偭偰偔偩偝偄丅
仜壨栰埾堳
杒塝偺壨栰偱偡丅偪傚偭偲崱丄偙偺屻丄娔嵏埾堳傪慖弌偟偰娔嵏傪庴偗傞偲崱愢柧偑偁偭偨偐偲巚偆傫偱偡偑丄娔嵏埾堳偼奺挰偺娔嵏埾堳偐傜慖弌偑偱偒傞傫偱偡傛偹丄婯栺偐傜偄偆偲丅偦傟偱丄娔嵏埾堳偼偒傚偆慖掕偟偰偒傚偆娔嵏傪庴偗傜傟傞偺偐偳偆偐丅傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂帠柋嬊偐傜愢柧丄傕偆堦夞偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
仜塱曯憤柋斍挿
怽偟傢偗偛偞偄傑偣傫丅愢柧偺巇曽偑偪傚偭偲埆偐偭偨偺偐側偲巚偄傑偡丅
丂杮擔慖擟偝傟傑偟偨娔嵏埾堳偺曽偵丄柧擔埲崀娔嵏傪偍庴偗偟偰偲偄偆偙偲偱丄偦偆偄偆堄枴崌偄偱偺偛愢柧偵偐偊偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂傛傠偟偄偱偡偐丅
仜壨栰埾堳丂偼偄丅
仜墶嶳夛挿丂傎偐偵偛偞偄傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄暯惉15擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼偵偮偒傑偟偰偼丄曬崘偺偲偍傝偛彸擣傪偄偨偩偗傑偡偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄偛曬崘偺偲偍傝偛彸擣傪偄偨偩偄偨傕偺偲偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄乮俁乯偺嫤媍帠崁偵堏傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄婯栺娭學偱偛偞偄傑偡偑丄峴曽孲崌暪嫤媍夛埾堳摍偺曬廣媦傃旓梡曎彏偵娭偡傞婯掱乮埬乯丄俀乯峴曽孲崌暪嫤媍夛夛媍塣塩婯掱乮埬乯丄俁乯峴曽孲崌暪嫤媍夛夛媍朤挳婯掱乮埬乯丄係乯峴曽孲崌暪嫤媍夛彫埾堳夛婯掱乮埬乯傑偱傪媍戣偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂帠柋嬊偐傜愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜峕帥帠柋嬊師挿
偦傟偱偼丄帠柋嬊偺峕帥偱偛偞偄傑偡丅偛愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅
丂帒椏偵偮偒傑偟偰偼丄21儁乕僕埲崀傪偛傜傫偄偨偩偒偨偄偲懚偠傑偡丅
丂21儁乕僕偵峴曽孲崌暪嫤媍夛埾堳摍偺曬廣媦傃旓梡曎彏偵娭偡傞婯掱偺埬偑嵹偭偰偛偞偄傑偡丅俀忦埲壓偵嬶懱偺撪梕偱偛偞偄傑偡偑丄戞俀忦丄曬廣偺妟偵偮偒傑偟偰偼丄嫤媍夛偺夛挿丄暃夛挿丄埾堳媦傃娔嵏埾堳偺曬廣偼丄擔妟
8,000墌偲偡傞丅偨偩偟丄抧曽岞嫟抍懱偺忢嬑偺摿暿怑丄堦斒怑偺怑堳偵偮偄偰偼偙傟傪巟媼偟側偄偲偄偆偺偑曬廣偺妟偺庢傝埖偄偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰俁忦偱偛偞偄傑偡偑丄旓梡曎彏偵偮偄偰偙偪傜偺曽偱婯掱傪偟偰偛偞偄傑偡丅嫤媍夛偺埾堳偺奆條曽偑嫤媍夛偺怑柋偺偨傔偵杻惗挰丒杒塝挰丒嬍憿挰埲奜偺嬫堟偵弌挘偟偨応崌偵偮偄偰丄偦偺旓梡曎彏傪怽偟忋偘傞偲偄偆偙偲偱丄偙偪傜偼21儁乕僕偺堦斣壓偵側傝傑偡偑丄偦傟偧傟揝摴捓丄慏捓丄峲嬻捓丄幵捓丄擔摉丄廻攽椏偲偄偆宍偱妟傪婯掕偟偰偍傝傑偡丅偨偩偟彂偒偑偛偞偄傑偟偰丄堬忛導偺忢嬑怑堳偵偮偄偰偼偙偺傎偐偱偡偲偄偆傛偆側宍偱庢傝埖傢偣偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆撪梕偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄係忦偺曽偵巟媼曽朄偵偮偄偰偺婯掱偱偛偞偄傑偡偑丄偙偪傜偺椃旓偵偮偒傑偟偰偼夛挿偺懏偡傞挰偺椃旓偵娭偡傞忦椺偺婯掕偲偄偆傕偺傪弨梡偝偣偰偄偨偩偔偲偄偆傛偆側撪梕偱偛採埬傪怽偟忋偘傞傕偺偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄22儁乕僕傪偛傜傫偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂峴曽孲崌暪嫤媍夛夛媍塣塩婯掱偺埬偱偛偞偄傑偡丅俀忦埲壓偑嬶懱偺撪梕偵側偭偰偛偞偄傑偡偑丄傑偢俀忦偵偍偒傑偟偰丄夛媍偵偮偒傑偟偰偼尨懃岞奐偲偡傞偲偄偆偙偲丄偦傟偐傜偨偩偟彂偒偱偛偞偄傑偟偰丄弌惾埾堳偺係暘偺俁埲忋偺巀惉偑偁傞偲偒偼岞奐偟側偄偙偲偑偱偒傞偲偄偆婯掕傪惙傝崬傫偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄夛媍偺奐夛丄暵夛偵偮偒傑偟偰偼丄媍挿偺愰崘丄偦傟偵埾堳偝傫曽偺敪尵偵偮偒傑偟偰偼媍挿偝傫偺嫋壜傪摼偨屻偲偄偆偙偲偑婯掕偝傟偰偍傝傑偟偰丄偦偺傎偐戞俁崁偵偍偒傑偟偰媍挿偑昁梫偲擣傔偨偲偒偵偼夛媍偵帎偭偰妛幆宱尡傪桳偡傞幰摍偺弌惾傪媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡傛偲偄偆偙偲偱丄埾堳偝傫埲奜偵摿偵偄傠偄傠側忣曬偱偁傞偲偐丄偦偆偄偆傕偺傪偛採嫙偄偨偩偔偲偄偆偙偲偱丄偙偪傜偺曽丄埾堳埲奜偺曽偺弌惾傪媮傔傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆婯掕偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞係忦偑昞寛偺忦崁偵側偭偰偛偞偄傑偡丅夛媍偺媍帠偵偮偄偰偼丄摉慠側偑傜慡夛堦抳傪傕偭偰寛偡傞偙偲傪尨懃偲偡傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡偑丄偨偩偟堄尒偑暘偐傟偨応崌偵偍偄偰偼弌惾埾堳悢偺係暘偺俁埲忋偺巀惉傪傕偭偰寛偡傞傕偺偲偡傞偲偄偆偙偲偱丄昞寛偺忦崁傪惍旛偝偣偰偄偨偩偄偰偍傝傑偡丅偙偺係暘偺俁偵偮偒傑偟偰偼丄崱夞俁挰偵傛傞嫤媍夛偱偛偞偄傑偡偺偱丄偄偢傟偐偺巗挰懞偺曽偱傑傞偭偒傝埾堳偝傫曽偡傋偰偑斀懳偲偄偆偙偲偑偁傝傑偟偨傜偽丄偙偺婯掱偵傛傟偽寛偡傞偙偲偑偱偒側偄偲偄偆偙偲偵側傠偆偐偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞俆忦偱朤挳偵娭偡傞婯掱偱偛偞偄傑偡偑丄偙傟偼夛挿偑夛媍偵帎傝暿偵掕傔傞偲偄偆偙偲偱丄師偺嫤媍帠崁偺俁乯偱夵傔偰偛愢柧傪怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偦偺傎偐戞俇忦偵夛媍榐傪嶌惉偡傞偲偄偆偙偲偱丄偙偺乮侾乯偐傜乮係乯傑偱傪摿偵偙偪傜偺夛媍榐偵婰嵹偡傞傫偩偲偄偆撪梕偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄戞俈忦偺夛媍榐偵偮偒傑偟偰偼丄摉慠偺偙偲側偑傜尨懃岞奐偲偄偆宍傪偲傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆撪梕偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄23儁乕僕丄嫤媍帠崁偺匓峴曽孲崌暪嫤媍夛夛媍朤挳婯掱偺埬偱偛偞偄傑偡丅
丂戞俀忦埲壓偱偛偞偄傑偡偑丄朤挳恖偺掕堳傪20恖偲偄偆宍偱掕傔偰偍傝傑偡丅
丂俁忦偵偮偄偰偱偡偑丄朤挳偺庤懕偵側傝傑偡丅朤挳傪偟傛偆偲偡傞幰丄婓朷偡傞幰偼丄朤挳恖庴晅曤偵廧強丄巵柤丄擭楊傪婰擖偟丄朤挳徹偺岎晅傪庴偗側偗傟偽側傜側偄偲偄偆婯掕偵側偭偰偛偞偄傑偡丅偨偩偟丄夛媍奐嵜梊掕帪崗偺30暘慜偺帪揰偱朤挳偺梊掕恖悢傪挻偊傞応崌偵偮偄偰偼丄偔偠堷偒偵傛偭偰朤挳恖傪寛掕偡傞偲偄偆偺偑偙偪傜偺戞俀崁偺婯掕偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞係忦偵朤挳偡傞偙偲偑偱偒側偄幰偲偄偆偙偲偱丄偄偢傟偐偵奩摉偡傞応崌丄朤挳偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫偲偄偆偙偲偱丄俋偮婯掕傪偟偰偛偞偄傑偡丅撪梕摍偵偮偄偰偼偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞俆忦偵朤挳恖偺庣傞傋偒帠崁傪偙偪傜偺曽偵嵹偣偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅捠忢偺媍夛摍偲摨偠傛偆側側偄傛偆偐偲巚偄傑偡偗傟偳傕丄屻傎偳偙偪傜偺曽傕偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄24儁乕僕偺曽傊偍恑傒偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅戞俇忦偵幨恀丄榐壒偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙傟偼夛挿偺嫋壜傪摼側偄尷傝偟偰偼側傜側偄偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞俈忦偵朤挳恖偵懳偡傞怑堳偺巜帵偵廬傢側偗傟偽側傜側偄偲偄偆傛偆側婯掕丄偦傟偐傜朤挳恖偺戅応偲偄偆偙偲偱丄戞俉忦偵岞奐偟側偄寛掕偑偁偭偨偲偒偼懍傗偐偵戅応偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偑惙傝崬傑傟偰偍傝傑偡丅
丂偦偺傎偐丄俋忦偵偼朤挳恖偑偙偺婯掱偵堘斀偡傞偲偒偼丄夛挿偼偙傟傪惂巭偟丄偦偺柦椷偵廬傢側偄偲偒偼偙傟傪戅応偝偣傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆婯掕傪惙傝崬傫偱偛偞偄傑偡丅
丂師丄25儁乕僕丄26儁乕僕偼庴晅曤丄朤挳徹偱偛偞偄傑偡偺偱丄屻傎偳偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡丅
丂27儁乕僕偺曽偵偮偒傑偟偰偛傜傫偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅峴曽孲崌暪嫤媍夛彫埾堳夛偺婯掱偱偛偞偄傑偡丅
丂戞俀忦偺擟柋偱偛偞偄傑偡偑丄嫤媍夛偐傜晅戸偝傟偨帠崁偵偮偄偰挷嵏丄怰媍摍傪峴偆偲偄偆偺偑彫埾堳夛偺擟柋偱偛偞偄傑偡丅愭恑帠椺偵偍偒傑偟偰偼丄柤徧偺庢傝埖偄摍偵偍偒傑偟偰丄岞曞屻偺柤徧偺峣傝崬傒傪峴偆偱偁傞偲偐丄怴巗偺帠柋強偺埵抲偵偐偐傢傝傑偟偰偄傠偄傠側専摙傪峴偆偲偐丄偦偆偄偆宍偱彫埾堳夛傪愝偗傞偲偄偆崌暪嫤媍夛偑偛偞偄傑偡丅偦偆偄偆傛偆側屄暿偺埬審偵偮偒傑偟偰丄挷嵏丄怰媍摍傪峴偭偰偄偨偩偔偲偄偆偺偑擟柋偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄埾堳偵偮偒傑偟偰偼戞俁忦偵婯掕偑偛偞偄傑偟偰丄嫤媍夛偺夛挿偑夛媍偵帎傝丄偙偙偵偛弌惾偄偨偩偄偰偍傝傑偡埾堳偝傫偺拞偐傜巜柤傪偡傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂戞係忦偑埾堳挿丄暃埾堳挿偺婯掕偱偛偞偄傑偟偰丄埾堳挿媦傃暃埾堳挿傪抲偔偲偄偆偙偲丄偦傟偐傜埾堳挿丄暃埾堳挿偵偮偄偰偼埾堳偺屳慖偵傛傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偺傎偐丄戞俆忦偵偮偒傑偟偰夛媍偺彽廤偺婯掕偑偛偞偄傑偡丅埾堳挿偑偦偺夛媍傪彽廤偟丄媍挿偲側傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦傟偐傜丄戞俈忦丄埾堳挿偼晅戸偝傟偨帠崁偺挷嵏丄怰媍摍偺寢壥偵偮偄偰丄嫤媍夛偵曬崘偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偑婯掕傪偝傟偰偛偞偄傑偡丅
丂偦偺傎偐丄俉忦偵弾柋偺庢傝埖偄丄偦傟偐傜俋忦偺娭學幰偑彫埾堳夛偺弌惾偟偨応崌偺旓梡曎彏偺庢傝埖偄偑偙偪傜偺曽偵婯掕傪偝傟偰偛偞偄傑偡丅
丂嫤媍帠崁偺侾乯偐傜係乯偵偮偒傑偟偰丄偛愢柧埲忋偺偲偍傝偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偛怰媍偺傎偳傪偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅偙傟偐傜偛堄尒偲偛幙栤傪偄偨偩偔傢偗偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄巹偺曽偐傜俀揰傎偳偁傢偣偰偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂侾揰栚偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄夛媍塣塩婯掱戞係忦偺昞寛偺愢柧偑偛偞偄傑偟偨丅導婡娭偺埾堳偝傫偐傜帠慜偵偛憡択偑偛偞偄傑偟偰丄怴巗偺柤徧傗帠柋強偺埵抲側偳丄抧尦偺戙昞偑寛掕偡傋偒廳梫帠崁偵偮偄偰丄壖偵昞寛偲偄偆偙偲偵側偭偨応崌偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄導婡娭偺埾堳偝傫偼昞寛偵偼壛傢傜側偄偲偄偆偙偲傪奆偝傫偵偛椆夝偄偨偩偒偨偄偲偄偆偙偲偑戞侾揰偱偛偞偄傑偡丅
丂俀揰栚偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙傟傕導婡娭偺埾堳偝傫偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄戝強崅強偺尒抧偐傜巜摫揑側棫応偱嫤媍夛偵嶲壛偟偰偄偨偩偄偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偟偰丄崱屻岞柋偺搒崌忋丄偳偆偟偰傕偙偺嫤媍夛偵弌惾偑偱偒側偄応崌傕偁傠偆偐偲巚偄傑偡丅偦偺嵺偵偼戙棟弌惾傪擣傔傞偲偄偆偙偲傪奆偝傫偵偛椆夝偟偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡偺偱丄埲忋俀揰偵偮偄偰偍帎傝傪偟偨偄偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡丅
丂偦傟偱偼丄帠柋嬊偐傜愢柧偑偛偞偄傑偟偨嫤媍帠崁侾乯偐傜係乯傑偱丄偦偟偰巹偺曽偐傜偍帎傝偄偨偟傑偟偨偨偩偄傑偺俀揰偺帠崁偵偮偄偰丄偛堄尒丄偛幙栤傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅偳偆偧傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅壗偐偛偞偄傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
堎媍側偟偲偄偆傛偆側偍惡偑偁傝傑偟偨偺偱丄尨埬偺偲偍傝寛掕傪偟偰傛傠偟偄偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偱偼丄寛掕傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄戙棟弌惾摍偺審偵偮偄偰傕傛傠偟偄偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄採埬偺偲偍傝偛椆夝傪摼偨傕偺偲偄偆傆偆偵峫偊傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄俆乯暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛帠嬈寁夋乮埬乯丄偁傢偣偰娭楢偑偁傝傑偡俇乯偱偛偞偄傑偡暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼乮埬乯偵偮偄偰傪媍戣偲偄偨偟傑偡丅
丂帠柋嬊偐傜愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜塱曯憤柋斍挿
偦傟偱偼丄嫤媍帠崁偺俆乯偲俇乯偲偄偆偙偲偱偛愢柧傪偝偟偁偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄嫤媍帠崁偺俆乯偲偄偨偟傑偟偰丄暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛帠嬈寁夋乮埬乯偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂傑偢丄崁栚偲偟偰侾斣偐傜俆斣傑偱戝偒偔偛偞偄傑偟偰丄侾斣偲偄偨偟傑偟偰嫤媍夛偺奐嵜偵偮偄偰丄乮侾乯偲偄偨偟傑偟偰嫤媍夛偺奐嵜丄偍偍傓偹俀廡娫偵侾夞掱搙偺奐嵜偲偄偆偙偲偱梊掕傪偟偰偍傝傑偡丅偙偺屻丄31儁乕僕偺曽偵偍偍傓偹偺栚埨偺寧擔偑婰偟偰偛偞偄傑偡偺偱丄堦墳嶲峫偲偟偰偄偨偩偄偰傛傠偟偄偺偐偲偄偆傆偆偵巚偄傑偡丅敿婜偱栺13夞偺奐嵜梊掕偲偄偆偙偲偱峫偊偰偍傝傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄乮俀乯偺彫埾堳夛偺奐嵜偲偄偆偙偲偱丄愭傎偳偺嫤媍帠崁偺係斣偱彫埾堳夛偺婯掱偺埬偑偛偞偄傑偟偨偺偱丄偦偪傜偺彫埾堳夛傪愝抲偟偨応崌偵悘帪奐嵜偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偄偰丄挷嵏尋媶帠嬈偲偄偨偟傑偟偰丄乮侾乯偺帠柋帠嬈偺堦尦壔帠嬈丅愭傎偳傕埾堳偺奆條曽偵偼攝晅傪偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨尰嫷挷彂丄偙傟偑俁挰偺偦傟偧傟尰嫷傪婰偟偨傕偺偱偛偞偄傑偟偰丄偙偺曈偺傕偺傪拞怱偵偄傠偄傠嫤媍傪偟側偑傜帠柋帠嬈偺堦尦壔傪恾偭偰偄偔偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂乮俀乯偲偟傑偟偰寶愝寁夋偺嶌惉丄偙傟偼怴巗抋惗屻偺傑偪偯偔傝偺巜恓偲側傞寁夋偲偄偆偙偲偱偛棟夝傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂俁斣栚偺峀曬丒岞挳妶摦偲偟傑偟偰丄乮侾乯乽崌暪嫤媍夛偩傛傝乿偺敪峴丅偙傟偼丄嫤媍偺撪梕傪抧堟偺廧柉偺奆條曽偵偍抦傜偣偡傞偲偄偆傛偆側丄峀曬巻偲偄偆埵抲偯偗偱丄尰帪揰偱俁挰偺奺悽懷慡屗偵偍攝傝偡傞梊掕偱丄栺寧侾夞掱搙偺敪峴傪峫偊偰偛偞偄傑偡丅
丂懕偄偰丄乮俀乯偲偟傑偟偰嫤媍夛偺儂乕儉儁乕僕偺奐愝丒塣塩偲偄偆偙偲偱丄儂乕儉儁乕僕傪奐愝偟偰偛偞偄傑偡丅尰帪揰偱偼昞巻偺儁乕僕偲婯栺摍傪庒姳儂乕儉儁乕僕偺忋偱岞奐偟偰偛偞偄傑偡偑丄杮擔埲崀丄偙偺傛偆側嫤媍夛偑嵪傒師戞丄偦傟偧傟偺寢壥偵偮偄偰傕悘帪儂乕儉儁乕僕偺曽偱忣曬傪岞奐偟偰偄偔偲偄偆傛偆側峫偊偱偛偞偄傑偡丅傑偨丄偁傢偣偰揹巕儊乕儖偱偦傟偧傟奆條曽偐傜偛堄尒傪庴偗傞偲偄偆傛偆側丄岞挳揑側婡擻傕偙偪傜偱偼峫偊偰偛偞偄傑偡丅
丂係斣栚偲偟傑偟偰丄帠柋嬊娭學丅乮侾乯偺姴帠夛偺奐嵜丄嫤媍夛偺奐嵜摍偵偁傢偣偰悘帪奐嵜偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅偦傟偲丄乮俀乯乮俁乯偵偮偒傑偟偰偼俁挰偺偦傟偧傟偺壽挿怑丄學挿怑偱峔惉偟傑偡愱栧晹夛暲傃偵暘壢夛偺奐嵜偲偄偆偙偲偱丄悘帪奐嵜傪偟偰偄偔偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄嵟屻偲側傝傑偡偑丄俆偺偦偺懠偲偄偆偙偲偱丄偦偺懠崌暪偵昁梫側弨旛嶌嬈傪峴偆偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂帠嬈寁夋偺埬偵偮偄偰偼埲忋偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄嫤媍帠崁偺匛暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛偺梊嶼乮埬乯偵偮偄偰偛愢柧傪偄偨偟傑偡丅
丂傑偢嵨擖偲偄偨偟傑偟偰偼丄晧扴嬥偲偟偰 1,500枩墌丄偙偪傜偼俁挰偺偦傟偧傟 500枩墌偢偮偺晧扴偲偄偆偙偲偱 1,500枩墌偺晧扴嬥偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂孞墇嬥偵偮偒傑偟偰偼 582枩 3,000墌偲偄偆偙偲偱丄偙偪傜偵偮偄偰偼15擭搙偺夛寁傛傝偺孞墇嬥偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偄偰丄彅廂擖偵偮偒傑偟偰偼 1,000墌偺寁忋偱偛偞偄傑偡偑丄偙偪傜偼梐嬥棙巕傪尒崬傫偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偄偰丄嵨弌偵堏傝傑偡丅
丂傑偢丄塣塩旓偺拞偱偺夛媍旓偲偄偨偟傑偟偰 461枩 4,000墌偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅偙偪傜偵偮偒傑偟偰偼丄埾堳偝傫曽偺曬廣側傝奺徚栒昳丄夛媍榐傪嶌惉偡傞偲偒偺埾戸椏丄傑偨夛応偺巊梡椏偲偄偆偙偲偱寁忋偱偛偞偄傑偡丅
丂懕偄偰丄塣塩旓偺帠柋旓偲偄偆偙偲偱 454枩 5,000墌傪寁忋偟偰偛偞偄傑偡丅偙偪傜偵偮偒傑偟偰偼丄埾堳偺曬廣偲偛偞偄傑偡偺偼丄娔嵏埾堳偝傫偺曬廣傪尒崬傫偱偛偞偄傑偡丅怑堳庤摉丄曬彏旓偲偟偰偼帇嶡娭學偺幱楃丄椃旓丄廀梡旓偲偟傑偟偰偼偦傟偧傟嫤媍夛偺拞偱偺徚栒昳摍丄偁傞偄偼岝擬旓丄擱椏戙偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅栶柋旓偲偟傑偟偰偼捠怣塣斃旓丄偁傞偄偼幵専偺旓梡偲偄偆傛偆側偙偲偱偛偞偄傑偡丅巊梡椏媦傃捓庁椏偵偮偄偰偼丄僐僺乕婡摍偺巊梡椏摍偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅傑偨丄旛昳峸擖旓丄岞壽旓傪庒姳寁忋偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅
丂懕偄偰丄帠嬈旓偺拞偱偺帠嬈悇恑旓偲偄偆偙偲偱丄曬彏旓丄偙偪傜偵偮偄偰偼怴巗柤傪曞廤偟偨嵺偺墳曞偺幱楃偲偄偆偙偲偱峫偊偰偛偞偄傑偡丅懕偄偰廀梡旓丄徚栒昳旓丄報嶞惢杮旓丄怘椘旓偲偄偆偙偲偱丄偙偪傜偵偮偄偰偼愭傎偳偺嫤媍夛偩傛傝偺峀曬巻傗丄偦偺曈偺報嶞側傝悢乆偺徚栒昳側偳傪峫偊偰偛偞偄傑偡丅傑偨丄栶柋旓偵偮偄偰偼捠怣塣斃旓偲偄偆偙偲偱丄梄憲椏傪峫偊偰偛偞偄傑偡丅埾戸椏偲偟傑偟偰丄俁挰偑怴偟偄巗傪宍惉偟偨応崌偵椺婯廤偺惍旛傪偡傞偲偄偆傛偆側偙偲偑偛偞偄傑偟偰丄椺婯偺惍旛丄偁傞偄偼愭傎偳偺帠嬈寁夋偵偛偞偄傑偟偨寶愝寁夋丄儂乕儉儁乕僕偺嶌惉丒峏怴偺埾戸側傝挷報幃偺娭學偺旓梡傪尒崬傫偱偛偞偄傑偡丅傑偨丄巊梡椏媦傃捓庁椏偲偟偰夛応巊梡椏丄庁忋椏傪峫偊偰偛偞偄傑偡丅
丂偦偺懠丄梊旛旓偲偟傑偟偰俀枩 1,000墌偺寁忋偲偄偆偙偲偱丄嵨弌偺梊嶼妟寁偲偟傑偟偰 2,082枩 4,000墌丄嵨擖嵨弌妟偲傕摨妟偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂埲忋偱偛偞偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅偛堄尒丄偛幙栤摍傪偍庴偗偄偨偡慜偵丄戝暘帪娫傕偨偪傑偟偨丅係帪傑偱巄帪媥宔傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅係帪偵嵞奐偄偨偟傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮媥宔乯
仜墶嶳夛挿
夛媍傪嵞奐偄偨偟傑偡丅偝偒傎偳帠柋嬊偺曽偐傜愢柧偑偛偞偄傑偟偨暯惉侾俇擭搙梊嶼埬偵偮偒傑偟偰丄壗偐偛堄尒摍偛偞偄傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛帠嬈寁夋媦傃暯惉16擭搙峴曽孲崌暪嫤媍夛梊嶼偵偮偒傑偟偰偼丄尨埬偺偲偍傝寛掕偟偰傛傠偟偄偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄尨埬偺偲偍傝寛掕傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂師偵丄俈乯偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄峴曽孲崌暪嫤媍夛偺僗働僕儏乕儖乮埬乯偵偮偄偰傪媍戣偲偄偨偟傑偡丅
丂帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜峕帥帠柋嬊師挿
帒椏偺曽丄30儁乕僕傪偛傜傫偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅帒椏偵偮偒傑偟偰偼丄摉柺偺僗働僕儏乕儖偲偄偆偙偲偲丄偦傟偐傜偦偺屻偺僗働僕儏乕儖偲偄偆偙偲偱丄係寧偺14擔丄杮擔戞侾夞偺嫤媍夛偲偄偆偙偲偱丄奺庬偺婯掱摍偵偮偒傑偟偰偛嫤媍傪偄偨偩偄偰偄傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅戞俀夞偑係寧27擔丄偦偟偰戞俁夞偑俆寧12擔偲偄偆偙偲偱梊掕傪偟偰偛偞偄傑偟偰丄偦傟偧傟偙偪傜偺嫤媍帠崁傪梊掕偟偰偍傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄俀偺偲偙傠偵戞俁夞屻偺僗働僕儏乕儖偲偄偆偙偲傪彂偄偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄愭傎偳偺帠嬈寁夋偺拞偱傕偛愢柧怽偟忋偘傑偟偨丄偍偍傓偹俀廡娫偵侾夞偺奐嵜偵側傝傑偡傛偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偟偰丄偦偺奐嵜偺梊掕偺16擭搙忋敿婜暘偺寁夋偑31儁乕僕偺曽偵嵹偭偰偛偞偄傑偡丅奐嵜梊掕応強偵偮偒傑偟偰偼丄杻惗挰偑儗僀僋僄僐乕丄杒塝挰丄嬍憿挰偵偍偒傑偟偰偼栶応偺戝夛媍幒偲偄偆偙偲傪婎杮偵丄偙傟偐傜奐嵜傪梊掕偟偰傑偄傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄暷報偺偲偙傠偵彂偄偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄挰挿丄媍挿丄偦傟偧傟岞柋偺搒崌偵傛傝傑偟偰丄嫤媍夛偺奐嵜梊掕擔偵偮偒傑偟偰偼曄峏傪梋媀側偔偝傟傞偲偄偆応崌傕偁傠偆偐偲巚偄傑偡偺偱丄偦偺揰偵偮偒傑偟偰偼偁傜偐偠傔偛椆彸傪偄偨偩偄偰丄崱夞偺奐嵜梊掕擔偺帒椏偲偄偆宍偱偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偙傟偐傜俀廡娫偵侾搙偲偄偆偙偲偱丄旕忢偵昿斏偵夛媍傪奐嵜偡傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡偺偱丄偁偊偰偙偪傜偺傑偩晄妋掕側晹暘偑偁傝傑偟偨偗傟偳傕丄帒椏偲偟偰弌偝偣偰偄偨偩偄偨偲偄偆偙偲傪偛椆夝偄偨偩偒偨偄偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂帒椏偺曽丄30儁乕僕偵偍栠傝偄偨偩偒傑偟偰丄偦傟偧傟崱怽偟忋偘傑偟偨傛偆偵丄嫤掕崁栚偺嫤媍傪峴偭偰偄偨偩偒傑偡偑丄偦偺屻偺棳傟偲偄偨偟傑偟偰偼丄嫤掕彂偺挷報丄偦偟偰朄掕偺崌暪偺庤懕偲偄偆偙偲偵恑傑偣偰偄偨偩偔偲偄偆偙偲丄偦傟偐傜偁傢偣偰怴巗偺崌暪弨旛偲偄偆偙偲偱丄堏峴嶌嬈偑峴傢傟傞偲偄偆傛偆側撪梕偵側傠偆偐偲巚偄傑偡丅
丂峴曽孲崌暪嫤媍夛偺僗働僕儏乕儖乮埬乯偵偮偒傑偟偰偼丄埲忋偺偲偍傝偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜墶嶳夛挿
帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅偛堄尒丄偛幙栤偑偁傝傑偟偨傜丄偛敪尵傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂嫶媗埾堳偝傫丄偍婅偄偟傑偡丅
仜嫶媗埾堳丂嬍憿挰偺嫶媗朏柧偱偡丅
丂侾偮偩偗幙栤側傫偱偡偑丄崌暪嫤媍夛偺奐嵜梊掕擔偼傢偐傝傑偟偨偑丄愭傎偳偺梊嶼偺拞偱愭恑抧帇嶡偲偄偆崁栚偑偁傞傫偱偡偑丄偙傟偼偙偺拞偵庢傝崬傔傞擔側傫偱偟傚偆偐丄偳偆側傫偱偟傚偆偐丅
仜墶嶳夛挿丂帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜峕帥帠柋嬊師挿丂偛愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅
丂偨偩偄傑偺愭恑抧偺帇嶡摍偵偮偒傑偟偰偼丄偙偺昞偵偼擖偭偰偛偞偄傑偣傫丅偁偔傑偱傕偙傟偼嫤媍夛偺奐嵜梊掕偲偄偆偙偲偱偛棟夝傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂愭恑抧偵偮偒傑偟偰偼丄偙傟偐傜崌暪嫤媍傪偡傞忋偱偄傠偄傠壽戣偑弌偰偒偨応崌偵丄偦傟傜偵偮偄偰挷嵏傪峴偆昁梫偑惗偠偨偲偄偆応崌偵丄偦偆偄偆傕偺傪幚巤偝偣偰偄偨偩偔偲偄偆偙偲偱丄偛椆夝傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
仜嫶媗埾堳丂偼偄丄椆夝丅
仜墶嶳夛挿丂傎偐偵偛偞偄傑偡偐丅
丂崄庢屭栤丅
仜崄庢屭栤
導偺巗挰懞壽挿偝傫丄30儁乕僕偺堦斣壓偵朄掕庤懕偲偄偆偺偑偁傝傑偡偹丅偦偙偱導媍夛偵偍偗傞媍寛偲偄偆偺偑偁傞傫偱偡偗傟偳傕丄導偺掕椺媍夛丄偙傟偼媍寛偡傞偺偼12寧媍夛偱偡偐丄偁傞偄偼俁寧媍夛丅
仜摗嶇埾堳
導偺巗挰懞壽挿偺摗嶇偱偛偞偄傑偡偑丄崱30儁乕僕偺導媍夛偵偍偗傞媍寛偲偄偆偙傠偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙偺僗働僕儏乕儖偑椺偊偽17擭偺俁寧傪栚昗偲偟偰偄傞傕偺側傜偽丄導媍夛偵偍偗傞媍寛偲偄偆偺偼16擭偺12寧偲偄偆偙偲偵側傞偐偲巚偄傑偡丅傕偟傕17擭偺俁寧偺崌暪偲偄偆偙偲側傜偽偱偡丅偨偩丄崌暪偺婜擔偼偪傚偭偲傑偩傛偔傢偐傝傑偣傫偐傜偹丅
尰帪揰偱偼丄偦傫側姶偠偱偡丅
仜墶嶳夛挿丂傛傠偟偄偱偟傚偆偐丄愭惗丅
仜崄庢屭栤丂偼偄丅
仜墶嶳夛挿丂傎偐偵偁傝傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿丂側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄峴曽孲崌暪嫤媍夛偺僗働僕儏乕儖偵偮偄偰偼尨埬偺偲偍傝寛掕偟偰傛傠偟偄偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿丂偦傟偱偼丄尨埬偺偲偍傝寛掕傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂師偵俉乯偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄峴曽孲崌暪嫤媍夛娔嵏埾堳偺慖擟偵偮偄偰傪媍戣偲偄偨偟傑偡丅
丂帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜帠柋嬊丂偦傟偱偼丄愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅
丂偨偩偄傑偺嫤媍夛偺弌擺偺娔嵏傪峴偆娔嵏埾堳偵偮偒傑偟偰偼丄朻摢愢柧傪怽偟忋偘傑偟偨崌暪嫤媍夛婯栺偺17忦偵傛傝傑偟偰丄夛挿偑俁挰偺娔嵏埾堳偺偆偪偐傜嫤媍夛偺摨堄傪摼偰俁柤傪埾忷偡傞偲偄偆偙偲偱巉偭偰偛偞偄傑偡丅偦傟偵敽偄傑偟偰丄崱夞偙偪傜偺曽偵埬偲偄偆偙偲偱丄杻惗挰偺娭惤條丄偦傟偐傜杒塝挰偺彫郪復條丄嬍憿挰偺愇嫶惷抝條偲偄偆偙偲偱丄偙偺嫤媍夛偺摙媍傪傑偲傔偨偄偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅傛傠偟偔偛怰媍偺傎偳傪偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅
仜墶嶳夛挿
帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅偨偩偄傑帠柋嬊傛傝採埬傪偄偨偟傑偟偨曽偱丄偛堄尒丄偛幙栤偑偁傝傑偟偨傜偽丄傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿丂偄偄偱偡偐丅
丂偦傟偱偼丄娔嵏埾堳偵偮偒傑偟偰偼尨埬偺偲偍傝摨堄傪偟偰偄偨偩偗傑偡偱偟傚偆偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮堎媍側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄尨埬偺偲偍傝偲偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄採埬帠崁偵堏傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂崱屻丄嫤媍偡傞帠崁偵偮偒傑偟偰偼丄傑偢採埬丒愢柧傪偝偣偰偄偨偩偒傑偟偰丄師夞偺嫤媍夛偵偍偄偰嫤媍傪偟丄尨懃偦偙偱寛掕傪偡傞偲偄偆宍傪偲傝偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅埾堳偺奆條曽偵偼丄採埬偐傜嫤媍傑偱丄昁偢偟傕挿偄帪娫偱偼側偄偐傕偟傟傑偣傫偗傟偳傕丄専摙丄偦偟偰弨旛傪偟偰丄嫤媍夛偵弌惾傪偟偰偄偨偩偒偨偄偲懚偠偰偍傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偛嫤椡偺傎偳傪偍婅偄怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偦傟偱偼丄傑偢侾乯偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄崌暪偺曽幃偵偮偄偰丄俀乯崌暪偺婜擔偵偮偄偰傪帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿
偦傟偱偼丄帠柋嬊偺塇惗偱偛偞偄傑偡丅巹偺曽偐傜崌暪偺曽幃媦傃崌暪偺婜擔偵偮偄偰愢柧傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂33儁乕僕偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄傑偢崌暪偺曽幃偐傜偛愢柧怽偟忋偘傑偡丅
丂崌暪偺曽幃偵偮偄偰偼偛懚偠偺偲偍傝丄慖戰巿偑俀偮偛偞偄傑偡丅侾偮偼怴愝崌暪丄俀偮栚偑曇擖崌暪偱偛偞偄傑偡丅偦傟偵偮偄偰丄崌暪偺曽幃偵偮偄偰奊偑偐偄偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄怴愝崌暪偺応崌偵偼偙偺奊偺嵍懁偵偛偞偄傑偡傛偆偵丄俙挰丄俛挰丄俠挰偑崌暪傪偟丄怴偨偵俢挰乮巗乯傪愝抲偡傞傛偆側応崌偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙偺応崌偵偼俙丄俛丄俠偺挰偺偦傟偧傟偺朄恖奿偼偄偢傟傕徚柵偡傞傫偩偲丄偱偡偐傜怴偟偔俢挰乮巗乯偑抋惗偡傫偩偲偄偆傛偆側偺偑怴愝崌暪丅偦偟偰丄偦傟偵懳偟傑偟偰曇擖崌暪偑塃懁偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄俙巗偑俛挰丄俠挰傪曇擖偡傞偲偄偭偨傛偆側応崌偱偛偞偄傑偡丅偙偺応崌偵偼俙巗偼懚懕偟傑偡偗傟偳傕丄俛挰丄俠挰偺朄恖奿偼徚柵偡傞傫偩偲偄偆傛偆側偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偺俀偮偺崌暪曽幃偵偮偄偰偺憡堘揰偑34儁乕僕偺曽偵宖偘偰偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄廳棫偭偨偲偙傠傪廍偄撉傒偟偰傑偄傝傑偡偲丄偨偩偄傑怽偟忋偘傑偟偨傛偆偵丄朄恖奿偵偮偒傑偟偰偼怴愝崌暪偺応崌偵偼怴偨偵朄恖奿偑敪惗偡傞傫偩偲丄偙傟偵懳偟偰曇擖崌暪偺応崌偵偼曇擖偡傞巗挰懞偺朄恖奿偑宲懕偡傞傫偩偲偄偆傛偆側憡堘偑偛偞偄傑偡丅
丂師偵丄巗挰懞偺柤徧偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄怴愝崌暪偺応崌偵偼怴偨偵惂掕偡傞丄偙傟偵懳偟傑偟偰曇擖崌暪偺応崌偵偼曇擖偡傞巗挰懞偺柤徧偲偡傞偙偲偑懡偄傫偩偲丅偨偩丄怴偨偵惂掕偡傞偙偲傕偱偒傞傫偩偲偄偆傛偆側憡堘偑偛偞偄傑偡丅
丂師偵丄帠柋強偺埵抲偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄怴愝崌暪偺応崌偵偼怴偨偵惂掕偡傞丄曇擖偺応崌偵偼捠忢偼曇擖偡傞巗挰懞偺帠柋強偺埵抲傪帠柋強偺埵抲偲偡傞傫偩偲偄偆傛偆側憡堘偑偛偞偄傑偡丅
丂巗挰懞偺挿偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄怴愝崌暪偺応崌偵偼徚柵偡傞娭學巗挰懞偺挿偼幐怑偡傞丄偙傟偵懳偟傑偟偰曇擖崌暪偺応崌偵偼曇擖偡傞巗挰懞偺挿偼曄傢傝傑偣傫丅曇擖偝傟傞丄偄傢備傞徚柵偡傞巗挰懞偺挿偼幐怑偡傞傫偩偲偄偆傛偆側偲偙傠偑戝偒側憡堘揰偐側偲偄偆傆偆偵峫偊偰偛偞偄傑偡丅
丂師偵丄35儁乕僕偵側傝傑偡偗傟偳傕丄巗惂巤峴偺梫審偱偛偞偄傑偡丅
丂抧曽帺帯朄偱偼恖岥傪俆枩恖埲忋桳偡傞偙偲丄偁傞偄偼偦偺傎偐傕傠傕傠偺婯掕偑偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄崌暪摿椺朄偵傛傞崌暪傪偟丄17擭俁寧31擔傑偱偵崌暪偡傞応崌偵偼丄恖岥俁枩恖埲忋偱偁傟偽巗惂偺巤峴偑壜擻偱偁傞偲偄偆偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂側偍丄巗偲巗挰懞偺庡側憡堘揰偑偦偺師偵帵偝傟偰偍傝傑偡偗傟偳傕丄戝偒偔曄傢傞傕偺偑偙偺拞偱偼暉巸偺棑偺暉巸帠柋強偺愝抲媊柋偐側偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅巗偺応崌偵偼暉巸帠柋強傪抲偐側偔偰偼側傜側偄丅偙傟偵懳偟偰丄挰懞偺応崌偵偼導偺帠柋偱偁傞偲偄偆傛偆側偙偲偱偛偞偄傑偡丅
丂埲忋偑崌暪偺曽幃偱偛偞偄傑偡丅侾偮偑怴愝崌暪丄俀偮栚偑曇擖崌暪偩偲丅偦偟偰挷惍曽恓丄帠柋嬊偲偟偰偼偙偆偄偆埬傪偛採帵傪偟偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅33儁乕僕偺堦斣忋抜偵彂偄偰偁傝傑偡偗傟偳傕丄峴曽孲杻惗挰丄杒塝挰丄嬍憿挰傪攑偟丄偦偺嬫堟傪傕偭偰怴偟偄巗傪愝抲偡傞怴愝乮懳摍乯崌暪偲偡傞偲偄偆偙偲偱丄偛採埬傪偄偨偟偨偄偲懚偠傑偡丅
丂師偵丄崌暪偺婜擔偵偮偄偰偛愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅39儁乕僕傪偍奐偒偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄崌暪偺婜擔偲掕傔傞応崌偵棷堄偟側偗傟偽側傜側偄帠崁偑偁傠偆偐側偲偄偆傆偆偵峫偊傑偡丅侾偮偼偙偙偵彂偄偰偁傝傑偡傛偆偵丄摿椺慬抲丄偁傞偄偼嵿惌慬抲摍偑庴偗傜傟傞傛偆偵崌暪偺婜擔傪掕傔傞偙偲偑廳梫偲峫偊傜傟傞偲丅偦偟偰丄偦偺応崌偵偨偩偄傑怽偟忋偘傑偟偨摿椺慬抲丄偁傞偄偼嵿惌巟墖慬抲摍傪婯掕偟偨丄偄傢備傞崌暪摿椺朄偑17擭俁寧31擔傪婜尷傪偟偰偄傞傫偩偲丅偨偩丄偙傟偵偮偄偰偼俀乯偺曽偵偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄崱奐偐傟偰偍傝傑偡捠忢崙夛偵偍偄偰宱夁慬抲摍偑媍寛傪偝傟傞尒捠偟偲側偭偰偄傞偲偄偆傛偆側偙偲偑偛偞偄傑偡丅
丂偦偟偰丄俁斣栚偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄嵿惌巟墖慬抲偵偮偄偰偼俀偮峫偊傜傟傞偺偐側偲偄偆傆偆偵巚傢傟傑偡丅梫偡傞偵丄侾偮偼崌暪摿椺朄偵婎偯偔巟墖慬抲偲崌暪摿椺朄偵婎偯偐側偄巟墖慬抲丄暘偗偰峫偊側偗傟偽側傜側偄偺偐側偲偄偆傆偆偵峫偊傜傟傑偡丅偦偟偰丄偙傟傜偺崌暪摿椺朄偵婎偯偔巟墖慬抲丄偁傞偄偼婎偯偐側偄巟墖慬抲偑40儁乕僕偺曽偵嵶偐偔宖嵹偝傟偰偍傝傑偡偺偱丄偍栚捠偟傪偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊傑偡丅
丂偦傟偐傜丄棷堄帠崁偺俀偮栚偱偡偗傟偳傕丄崌暪偡傞傑偱偵偼丄挰媍夛偵偍偗傞媍寛偺屻丄導抦帠傊偺崌暪偺怽惪丄偦傟偐傜導媍夛偱偺媍寛丄偁傞偄偼抦帠偺崌暪寛掕丄憤柋戝恇傊偺撏偗弌丄偦傟偐傜姱曬偺岞帵摍乆偺庤懕偑掕傔傜傟偰偄傑偡偺偱丄偙傟傜偺婜娫傪偁傜偐偠傔憐掕偟偰崌暪偺婜擔傪掕傔傞昁梫偑偁傞偲偄偆傆偆偵峫偊傑偡丅
丂偦傟偐傜丄俁偮栚偵偼廧柉僒乕價僗偺揰偺栤戣偱偡偗傟偳傕丄偱偒傞尷傝巟忈偺側偄帪婜傪憐掕偟偰崌暪偺婜擔傪掕傔傞偙偲偑朷傑偟偄偲偄偆傆偆偵巚傢傟傑偡丅
丂係斣栚偱偡偗傟偳傕丄嵟嬤偺愭恑帠椺偱偼摿掕偺擔偵尷傜傟偨傕偺偱側偔偰丄偦傟偧傟偺抍懱偑嫤媍傪偟偰丄偦傟偧傟偺帠忣偵傛偭偰婜擔傪掕傔偰偄傞偲偄偆偙偲偑尵傢傟偰偄傞傛偆偱偛偞偄傑偡丅偦偆偄偭偨偙偲傪棷堄偟側偑傜丄崌暪偺婜擔傪掕傔偰偄偐側偔偰偼側傜側偄偺偐側偲偄偆傆偆偵峫偊偰偄傑偡丅
丂偦偟偰丄41儁乕僕偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偨偩偄傑怽偟忋偘傑偟偨傕傠傕傠偺僗働僕儏乕儖傪憐掕偟傑偡偲丄偙偆偄偭偨昞偵傑偲傔偨傕偺偑嵹偣偰偛偞偄傑偡丅愭傎偳屭栤偺愭惗偐傜傕偍恞偹偑偁偭偨傛偆偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄崌暪嫤媍夛偑16擭俁寧15擔偵愝抲傪偝傟丄杮擔峴曽孲偺崌暪嫤媍夛偑奐嵜偝傟偰偄傞傢偗偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙偺屻丄嫤媍夛傪寧俀夞掱搙奐嵜傪偟丄帠柋帠嬈偺堦尦壔偵學傞嫤媍丄偁傞偄偼傕偆堦曽寶愝寁夋嶔掕偵學傞嫤媍摍傪恑傔偰傑偄傝傑偟偰丄廧柉愢柧夛丄偁傞偄偼寶愝寁夋偺導傊偺嫤媍丄崌暪嫤掕彂偺挷報丄挰媍夛偺媍寛丄偦偟偰導抦帠偺怽惪摍乆偺庤懕偑偁偭偰丄崌暪偑巤峴偝傟傞傫偩偲偄偆傆偆偵巚傢傟傞偺偱偛偞偄傑偡丅
丂偨偩偄傑偛愢柧怽偟忋偘傑偟偨傛偆側忬嫷傪摜傑偊偰丄挷惍曽恓偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄39儁乕僕偺曽偵偍栠傝偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂妋擣帠崁偺侾偮偲偟偰丄尰帪揰偱偼妋幚偵奺庬摿椺慬抲傗嵿惌巟墖慬抲偑庴偗傜傟傑偡暯惉17擭俁寧31擔傑偱偺崌暪傪栚昗偲偡傞丄俀偮栚偑丄偨偩偟崌暪偺嬶懱揑婜擔偵偮偒傑偟偰偼丄崱屻偺嫤媍偺恑捇忬嫷傗奺庬巟墖慬抲偵學傞宱夁慬抲偺忬嫷摍傪摜傑偊偰丄夵傔偰嫤媍傪偡傞傕偺偲偡傞偲偄偆傛偆側挷惍曽恓偱丄偛採埬傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂埲忋偱偛偞偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偨偩偄傑帠柋嬊偐傜愢柧傪偄偨偟傑偟偨丅偛幙栤摍偑偛偞偄傑偟偨側傜偽丄敪尵傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偼偄丄偳偆偧丅偪傚偭偲懸偭偰偔偩偝偄丅崱儅僀僋丄僥乕僾偵偐偐偭偰偄傑偡偐傜丅
仜嶳嶈埾堳
幙栤偡傞慜偵偪傚偭偲妋擣偟偨偄傫偱偡偗傟偳傕丄崌暪婜擔丄擔偵偪偵偮偄偰偺採埬傕偟偰偄偄傫偱偡偐丅
仜塇惗帠柋嬊挿
崱夞偼丄愭傎偳夛挿偺曽偐傜傕偛偞偄傑偟偨傛偆偵丄採埬丒愢柧傪偝偣偰偄偨偩偒傑偟偰丄師夞偺嫤媍夛偵偍偄偰嫤媍傪偟偰丄偦偙偱寛掕傪偡傞偲丄偦偆偄偆棳傟偱偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿丂傛傠偟偄偱偡偐丅
仜嶳嶈埾堳丂偼偄丅
仜墶嶳夛挿丂傎偐偵偁傝傑偡偐丅
丂嫶媗埾堳偝傫丄偍婅偄偟傑偡丅
仜嫶媗埾堳
嬍憿偺嫶媗側傫偱偡偑丄巗偲側傞傋偒傕偺偺梫審側傫偱偡偑丄摿椺朄偱暯惉10擭偺朄棩偵偍偄偰偼係枩埲忋偲偄偆偙偲偩偲巚偆傫偱偡偑丄崱偺偛愢柧偱偼俁枩恖埲忋偲偄偆傆偆偵側偭偨傕偺偱偡偐傜丄偄偮俁枩埲忋偲偄偆傆偆側朄夵惓偼嵟嬤側傫偱偟傚偆偐丅
仜墶嶳夛挿丂帠柋嬊傛傝偍摎偊傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿
崌暪摿椺朄偺拞偱偼丄摉弶16擭偺俁寧31擔偲偄偆婯掕偑偛偞偄傑偟偨丅偦傟偺夵惓偑偨偟偐15擭搙拞偵偛偞偄傑偟偰丄17擭俁寧31擔傑偱偵崌暪偡傟偽俁枩恖偲偄偆傆偆偵婯掕偑夵惓傪偝傟偰偄傞偲偄偆傆偆偵婰壇偟偰偍傝傑偡丅嵶偐偄擔偵偪偵偮偄偰偼偪傚偭偲崱挷傋傑偡偺偱丅
仜墶嶳夛挿丂偪傚偭偲偍懸偪偔偩偝偄丅
仜嫶媗埾堳
挭棃偺応崌偼摿椺拞偺摿椺偱偁偭偰丄暯惉10擭偺朄偱偼暯惉17擭俁寧31擔傑偱偵偼岞嫟抍懱偼係枩恖埲忋偲丄偙偆偄偆掕媊偑偁傞傢偗偱偡偹丅
仜塇惗帠柋嬊挿丂偡傒傑偣傫丄偍摎偊傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂15擭偺俈寧偵朄偺夵惓偑偝傟偨傛偆偱偛偞偄傑偡丅
仜嫶媗埾堳丂15擭俈寧丅
仜塇惗帠柋嬊挿丂偼偄丅
仜墶嶳夛挿丂傛傠偟偄偱偡偐丅傎偐偵偁傝傑偡偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄師偵堏傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅壠傊婣偭偰傛偔専摙傪偟偰曌嫮傪偟偰偔偩偝偄丅偍婅偄偟傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄俁乯偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄怴巗偺柤徧偵偮偄偰帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿
偦傟偱偼丄42儁乕僕偵側傝傑偡偗傟偳傕丄怴巗偺柤徧偵偮偄偰採埬偺愢柧傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂愭傎偳崌暪偺曽幃偵偮偄偰採埬傪偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨偗傟偳傕丄傑偩崌暪偺曽幃偑寛傑偭偰偍傝傑偣傫偺偱丄柤徧偺庢傝埖偄偵偮偄偰傕怴愝崌暪偺応崌偲曇擖崌暪偺応崌偲俀捠傝峫偊傜傟傞傢偗偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄偙偙偱偼怴愝崌暪偲偄偆傛偆側偙偲傪慜採偵愢柧傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅
丂怴愝崌暪偺応崌偵偼丄娭學巗挰懞偑偡傋偰攑巭傪偝傟傞偨傔偵丄怴偟偄柤徧傪掕傔側偗傟偽側傜側偄偲偄偆傆偆偵丄愭傎偳偛愢柧怽偟忋偘傑偟偨丅偦偺屻怴偟偔柤慜傪掕傔傞応崌偵丄愭恑帠椺偐傜偳偆偄偭偨傕偺偑偁傞偺偐側偲偄偆偲偙傠偱尒偰傒傑偡偲丄係偮偺曽幃偑捠忢峫偊傜傟傞傛偆偱偛偞偄傑偡丅偮傑傝丄侾偮偼岞曞曽幃丄俀偮栚偑奺挰偺帩偪婑傝曽幃丄俁斣栚偑傾儞働乕僩曽幃丄係斣栚偑彫埾堳夛曽幃偱偛偞偄傑偡丅
丂堦偮堦偮偙偙偱偍栚捠偟傪偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡偑丄岞曞曽幃偵偮偄偰偼廧柉偐傜岞曞傪偟丄彫埾堳夛摍偱岓曗傪峣傝崬傒丄崌暪嫤媍夛偱寛掕傪偟偰偄偔丅俀偮栚偺帩偪婑傝曽幃偲偄偆偺偼丄奺挰偱柤徧埬傪帩偪婑傝傑偟偰丄崌暪嫤媍夛偱嫤媍傪偟丄寛掕傪偟偰偄偔丅俁偮栚偺傾儞働乕僩曽幃偵偮偒傑偟偰偼丄彫埾堳夛傪愝抲偟傑偟偰丄柤徧偺岓曗傪慖傃丄廧柉傾儞働乕僩挷嵏摍傪幚巤傪偟偰丄忋埵偺柤徧偐傜嫤媍夛偱嫤媍傪偟偰寛掕偟偰偄偔傾儞働乕僩曽幃偱偡丅係斣栚偺彫埾堳夛曽幃偲偄偆偺偼丄彫埾堳夛偑柤徧偺岓曗傪専摙丒慖掕傪偟偰丄崌暪嫤媍夛偱寛掕偟偰偄偔丅偙偺係偮偑捠忢峫偊傜傟傞傛偆偱偛偞偄傑偡丅
丂偦偙偱丄帠柋嬊偲偟傑偟偰偼挷惍曽恓偲偟偰俀偮偺偙偲偱妋擣傪偍婅偄偟偰偄傞偲偙傠偱偁傝傑偡丅侾偮偼丄怴巗偺柤徧偺寛掕曽朄偵偮偄偰偼丄愭傎偳怽偟忋偘傑偟偨岞曞曽幃丄奺挰帩偪婑傝曽幃丄傾儞働乕僩曽幃丄彫埾堳夛曽幃偺偆偪偺仜仜曽幃偲偡傞偲丅俀偮栚偼婛懚偺柤徧丄偮傑傝杻惗丄杒塝丄嬍憿偺婛懚偺柤徧偵偮偄偰偼丄怴巗柤徧偺岓曗偲偟偰巊梡偱偒傞偙偲側偺偐丄偱偒側偄偙偲側偺偐丅偙偺俀偮傪採埬傪怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂埲忋偱偛偞偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
帠柋嬊偐傜偺愢柧偑廔傢傝傑偟偨丅幙栤摍偑偁傝傑偟偨傜偽丄偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅壗偐偛偞偄傑偣傫偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄側偄傛偆偱偛偞偄傑偡偺偱丄師偵堏傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂懕偒傑偟偰丄係乯崌暪嫤掕崁栚乮埬乯偵偮偄偰丄俆乯峴惌惂搙偺挷惍曽恓乮埬乯偵偮偄偰丄帠柋嬊傛傝愢柧傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
仜塇惗帠柋嬊挿
偦傟偱偼丄44儁乕僕偱偡偗傟偳傕丄採埬帠崁偺匔崌暪嫤掕崁栚乮埬乯偵偮偄偰偛愢柧傪怽偟忋偘傑偡丅
丂傑偢丄嬫暘偱偡偗傟偳傕丄婎杮揑側嫤掕崁栚偵偼俆偮傎偳嫤掕崁栚傪峫偊偰偛偞偄傑偡丅侾偮偑崌暪偺曽幃丄俀丄崌暪偺婜擔丄俁丄怴巗偺柤徧丄係丄怴巗偺帠柋強偺埵抲丄俆丄嵿嶻偺庢傝埖偄丅
丂崌暪摿椺朄偺庢傝埖偄傪挷惍偡傞崁栚偲偟偰偼丄傗偼傝俆揰宖偘偰偛偞偄傑偡丅媍夛媍堳偺掕悢媦傃擟婜偺庢傝埖偄丄擾嬈埾堳夛埾堳偺掕悢媦傃擟婜偺庢傝埖偄丄抧堟怰媍夛偺庢傝埖偄丄抧曽惻偺庢傝埖偄丄堦斒怑偺怑堳偺恎暘偺庢傝埖偄偵偮偄偰嫤掕崁栚偲偟偰採埬傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂師偵丄偦偺懠昁梫側挷惍崁栚偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄摿暿怑偺怑堳偺恎暘偺庢傝埖偄丄忦椺丄婯懃摍偺庢傝埖偄丄帠柋慻怐媦傃婡峔偺庢傝埖偄丄堦晹帠柋慻崌摍偺庢傝埖偄丄巊梡椏丄庤悢椏摍偺庢傝埖偄丄岞嫟揑抍懱摍偺庢傝埖偄丄曗彆嬥丄岎晅嬥摍偺庢傝埖偄丄挰柤丒帤柤偺庢傝埖偄丄姷峴偺庢傝埖偄丄崙柉寬峃曐尟帠嬈偺庢傝埖偄丄夘岇曐尟帠嬈偺庢傝埖偄丄峴惌嬫偺庢傝埖偄丄揹嶼僔僗僥儉偺庢傝埖偄丄偦偟偰奺庬帠柋帠嬈偺庢傝埖偄偺拞偵偼乮侾乯偐傜乮13乯傑偱宖偘偨傕偺傪嫤掕崁栚偲偟偰採埬傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂偝傜偵丄怴巗偺寶愝寁夋偱偼丄偄傢備傞怴巗偺崌暪寶愝寁夋丅埲忋丄嫤掕崁栚偲偟偰採埬傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂45儁乕僕丄46儁乕僕偺曽偵偨偩偄傑怽偟忋偘傑偟偨嫤掕崁栚偺撪梕偵偮偄偰愢柧彂偒偑偛偞偄傑偡偺偱丄屻傎偳偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲懚偠傑偡丅
丂師偵丄48儁乕僕偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄採埬帠崁偺匘偱峴惌惂搙摍偺挷惍曽恓乮埬乯偵偮偄偰偛愢柧傪怽偟忋偘偨偄偲懚偠傑偡丅
丂杻惗挰丒杒塝挰丒嬍憿挰乮埲壓乽俁挰乿偲偄偆丅乯偑崌暪偟偨嵺偵丄廧柉偑峴惌惂搙摍偺堘偄偵傛偭偰崿棎傪偟偨傝丄晄棙塿傪庴偗偨傝偡傞偙偲偺側偄傛偆偵丄偡傝崌傢偣偑昁梫側奺庬峴惌惂搙摍偵偮偄偰帠慜偵挷惍傪峴偭偰偍偔昁梫偑偛偞偄傑偡丅偙偺挷惍傪摑堦揑偐偮懱宯揑偵峴偆偨傔偵丄師偺偲偍傝婎杮尨懃偲婎杮揑側峫偊曽傪惍棟偟偰偍偒偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅
丂傑偢丄婎杮尨懃偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄俁挰偑曕傫偱偒偨偙傟傑偱偺楌巎傗暥壔丄抧堟摿惈傪憡屳偵懜廳偟丄怴巗偺嬒峵偁傞敪揥偲憤崌揑側帠柋暉巸偺岦忋偵搘傔傞偙偲傪婎杮偲偟偰丄師偺俆偮偺尨懃偵棷堄偟偰挷惍傪偟偰傑偄傝偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅乮侾乯堦懱惈妋曐偺尨懃丄乮俀乯偵廧柉暉巸岦忋偺尨懃丄乮俁乯偲偟偰晧扴岞暯偺尨懃丄乮係乯寬慡側嵿惌塣塩偺尨懃丄乮俆乯峴惌夵妚悇恑偺尨懃丄偙偺俆揰傪婎杮尨懃偲偟偰挷惍傪偟偰傑偄傝偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅
丂師偵丄嫤媍偺峫偊曽偱偛偞偄傑偡偗傟偳傕丄俇偮宖偘偰偛偞偄傑偡丅偙傟偵偮偄偰偼偛傜傫傪偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偍傝傑偡丅
丂偦偟偰丄49儁乕僕偵偙偺帠柋帠嬈偺挷惍曽恓丄婎杮揑側嬫暘偑帵偟偰偛偞偄傑偡偺偱丄偙傟偵偮偄偰傕偛傜傫偄偨偩偒偨偄偲偄偆傆偆偵峫偊偰偛偞偄傑偡丅
丂埲忋丄採埬傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偡丅
仜墶嶳夛挿
偨偩偄傑偺愢柧偵偮偒傑偟偰丄偛幙栤摍偑偛偞偄傑偟偨傜丄敪尵傪偍婅偄偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅壗偐偛偞偄傑偣傫偐丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮敪尵幰側偟乯
仜墶嶳夛挿
偦傟偱偼丄側偄傛偆偱偁傝傑偡偺偱丄採埬帠崁偵偮偒傑偟偰偼埲忋偲偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅師夞傑偱偵傛偔専摙傪偟偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂師偵丄媍戣偺乮係乯偦偺懠偱偛偞偄傑偡丅帠柋嬊偐傜壗偐偛偞偄傑偡偐丅
仜峕帥帠柋嬊挿
偦傟偱偼丄師夞偺戞俀夞偺嫤媍夛偺奐嵜偺擔掱偵偮偒傑偟偰偛愢柧傪怽偟忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂愭傎偳僗働僕儏乕儖偺拞偱傕偛愢柧傪偪傚偭偲怽偟忋偘偨偲偙傠偱偛偞偄傑偡偑丄係寧偺27擔丄13帪30暘偐傜杒塝挰栶応偱戞俀夞偺崌暪嫤媍夛傪奐嵜偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲懚偠傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偡丅屻傎偳師夞偺奐嵜捠抦偺曽丄偍攝傝傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅偁傢偣偰傛傠偟偔偍婅偄傪怽偟忋偘傑偡丅
丂埲忋偱偛偞偄傑偡丅
仜墶嶳夛挿
師夞丄戞俀夞栚偱偁傝傑偡偗傟偳傕丄係寧偺27擔丄杒塝挰栶応偱屵屻侾帪敿偐傜奐嵜傪偟偨偄偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡偺偱丄傛傠偟偔偍婅偄傪偄偨偟偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偦傟偱偼丄屭栤偺愭惗曽丄壗偐偦偺懠偱偛偞偄傑偡偐丅
仜崄庢屭栤丂偁傝傑偣傫丅
仜摗搰屭栤丂偁傝傑偣傫丅
仜墶嶳夛挿
側偄偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡偺偱丄埾堳偺奆條曽偵偼戝曄挿帪娫偵傢偨傝傑偟偰偛嫤椡傪偄偨偩偒傑偟偰丄傑偨偛怰媍傪偄偨偩偒傑偟偰丄傑偙偲偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂偦傟偱偼丄帠柋嬊偵儅僀僋傪僶僩儞僞僢僠偟偨偄偲巚偄傑偡丅傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
仜悰扟帠柋嬊師挿
墶嶳夛挿傪巒傔奆條曽偵偼丄挿帪娫偵傢偨傝傑偟偰偛怰媍丄専摙摍丄杮摉偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
丂埲忋傪傕偪傑偟偰戞侾夞偺峴曽孲崌暪嫤媍夛偺夛崌傪暵偠偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅師夞傕傂偲偮慡堳弌惾偱傛傠偟偔嫤媍偺傎偳傪偍婅偄偟傑偡丅偳偆傕偛嬯楯偝傑偱偛偞偄傑偟偨丅