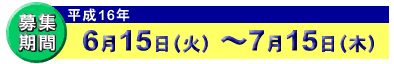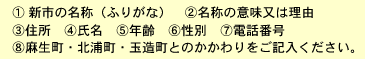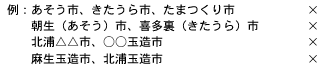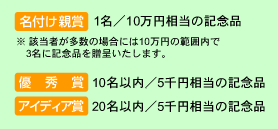|
 |
|
(第4回行方郡合併協議会:玉造町大会議室)
|
●新設(対等)合併、市制施行をめざします!(第2回協議会で決定)
●新市名称(候補)を公募いたします。ふるってご応募ください。
● 第3回、第4回合併協議会が開催されました。
5月12日(水)午後2時から麻生町宇崎のレイクエコー「大研修室」において、第3回合併協議会が開催されました。委員32名の出席(欠席4名)と顧問1名の出席により会議が行われました。
4件の協議事項のうち、「新市の事務所の位置」、「議会議員の定数及び任期の取扱い」については、議論の後、継続協議となり、「財産の取扱い」「新市建設計画の策定方針(案)」については、原案どおり決定いたしました。
協議された事項
1.新市の事務所の位置について
事務所の位置については、住民サービスや行財政改革を推進できる組織機構であることなどを踏まえ、新市のまちづくりを見据えて議論する必要があります。会議では、事務所の位置を決定するにあたって、ポイントとなる新庁舎建設の有無についての議論がなされました。
「現在の三町の庁舎に本庁機能を持たせることは、難しい」「それぞれの庁舎の建築年数が経過している」「庁舎建設あるいは増改築する際の財源は、合併特例債が唯一有利である」「現在の庁舎は、新市において地理的に端である」などを前提に議論がなされました。
次回さらに継続で協議することになりました。
(主な意見)
・効率的な行政を進めるためには、新庁舎の建設が必要である。
・住民サービスの観点から、現在の三庁舎を使用した総合支所方式が望ましい。庁舎間の連絡は、情報技術の進展により問題はない。
・新庁舎建設の方針とし、それまでは、現在の庁舎を使用する。
・現在の庁舎を利用し、機能を分散させる方式(分庁方式)が良い。
2.財産の取扱いについて
三町が所有する財産及び債務についての取扱いが協議されました。調整方針(案)のとおり決定いたしました。
|
調整方針 |
(主な意見)
・「調整方針の2なお以下の部分」については、各町で目的を持った施設整備の基金であれば、当該町の施設整備に充てることと理解して良いのか。(質問のとおりの解釈と確認された。)
3.議会議員の定数及び任期の取扱いについて
議会議員の任期の取扱いについては、在任特例を適用し、任期については、合併の期日とあわせて決定することが確認されました。定数については、継続して協議することになりました。
(主な意見)
・新市へスムーズに引き継ぐためには、在任特例により現在の議会議員が一定期間在任したほうが良い。
4.新市建設計画の策定方針(案)について
新市のマスタープランとなる建設計画の策定方針について協議され、原案どおり決定いたしました。
| 新市建設計画の策定方針(要旨) ○三町の新しいまちづくりを進めるための基本方針を定め、その実現により、速やかな一体化、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図る。 ○「基本方針」、基本方針を実現するための「まちづくり計画」、「公共的施設の統合整備」及び「財政計画を中心とし構成する。 ○「基本方針」は、長期的視点に立ち、その他「まちづくり計画」等は10年の期間について定める。 ○財政計画は、依存財源を過大に見積もることなく、健全に財政を運営するよう留意する。 |
事務所(市役所)の組織形態は、
新市において、本庁舎を建設する方針が確認されました。(第4回合併協議会)これにより、行政組織をスリム化してさらに行財政改革を進めることが可能となります。
新庁舎建設までの期間については、行財政改革の視点や住民サービスの低下を招かないよう充分配慮することなどを視点に、その組織形態を決めていく必要があります。
先進事例を参考にすると、合併後の庁舎の設置パターンは、大きく分けると次の3つが考えられます。
【パターン1】 本庁方式の例
|
本庁舎(新設)
|
A支所
|
B支所
|
C支所
|
||||
|
|
|
|
【パターン2】 分庁方式の例
|
A庁舎
|
B庁舎
|
C庁舎
|
||||||
|
|
|
【パターン3】 総合支所方式の例
|
A総合支所
|
B総合支所
|
C総合支所
|
||||
|
|
|
これらのパターンは、それぞれにメリット、デメリットが考えられます。また、本庁方式をとる場合には、現在の3町庁舎では、いずれも収容能力等において限界もあることや行政運営の効率化等の観点から、今回の新庁舎建設の方針が示されました。実際には、新庁舎建設までの期間について、例示のどの方式で行政運営をしていくのかということが議論されています。選択肢としては、上記のパターン2あるいは3、そしてこれらの混在型が現実的です。
市建設計画とは、
合併特例法に規定された計画で、新市誕生の際のマスタープラン(基本計画)として策定するものです。また、合併協議の判断材料として本計画を示す必要もあります。そして、この計画に基づいた事業が合併特例債事業など支援措置の対象となります。
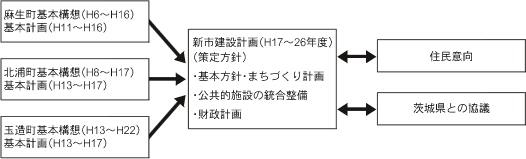 |
5月27日(木)午後2時から玉造町役場「大会議室」において、第4回合併協議会が開催されました。委員35名の出席(欠席1名)と顧問2名の出席により会議が行われました。
7件の協議事項のうち、「新市の事務所の位置」、「議会議員の定数及び任期の取扱い」については、議論の後、継続協議となりました。新市名称の募集を行うことや建設計画のアンケートを実施することなどが決定いたしました。
詳細は次のとおりです。
協議された事項
1.新市の事務所の位置について(継続)
事務所の位置については、新庁舎を建設するか否かの議論を行い、新市において新庁舎を建設する方針が確認されました。それまでの間の庁舎の形態については、分庁方式、総合支所方式、それらの混在型のパターンを基に議論をしていくことになり、その後に、事務所の位置を決定していく
ことが確認されました。
(主な意見)
・新庁舎建設までの事務所の設置形態は、分庁方式と総合支所方式の混在型が良い。
・(新庁舎建設までは)総合支所方式が良い。庁舎間の連絡や決裁等は、電子決裁などを活用することで合理化を図ることも可能である。
・(新庁舎建設までは)分庁方式が効率的である。
2.議会議員の定数及び任期の取扱いについて(継続)
議会議員の任期については、在任特例を適用し、新市誕生後一定の期間在任することが確認されています。在任特例経過後の定数については、24人とすることが確認されました。なお、在任期間については、合併の期日とあわせて、決定していくことを確認いたしました。
(主な意見)
・24人を定数とすべきである。
3.一般職の職員の身分の取扱いについて
協議がなされ、次の調整方針のとおり決定しました。
| 1.三町の一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐものとする。 2.職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 3.職員の職名及び職務の級、給与制度等については、他の自治体の例などを参考に調整し、統一を図るものとする。 |
4.特別職の職員の身分の取扱いについて
協議がなされ、次の調整方針のとおり決定しました。
| 特別職の職員等については、その設置、人数、任期等について、法令の定めるところに従い調整する。法令等に定めがない場合には、新市において必要に応じて新たに設置する。 |
5.公共的団体等の取扱いについて
協議がなされ、次の調整方針のとおり決定しました。
| 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 1.三町に共通している団体は、できる限り合併時に統合するよう調整に努める。 2.三町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。 3.三町に共通している団体で、統合に時間を要する団体には、将来統合するよう調整に努める。 4.その他の団体については、個別に検討し必要な調整に努める。 |
6.新市の名称について(継続)
協議がなされ、次のように確認されました。これにより、6月15日より新市名称(候補)の公募を開始します。
| ○新市名称候補選定基準(要旨) ・既存の麻生、北浦、玉造は使用しない。 ・応募作品の中から小委員会で概ね5点を選定し、協議会において新市名称を決定する。 ○募集要項 ・公募の目的や方法などの要項を定めたものです。 ○新市名称候補の選定に係る小委員会の設置について ・7月16日に協議会委員のうち学識経験者12名の構成により設置することになりました。 |
(主な意見)
・名付け親賞の対象者を1名ではなく、各町1名ずつの3名としてはどうか。記念品を3名で分ける扱い)
7.新市建設計画に係る住民アンケートの実施について
麻生町、北浦町においては、同内容のアンケートをすでに実施していることから、玉造町の全世帯を対象に実施することになりました。
|
「古きをたず温ねて・・・ 三町の指定文化財を紹介します!」
|
| 【県指定】 | ◇小高のカヤ(麻生町小高) | ◇熊野神社本殿(島並) |
| 【町指定】 | ・常光院山門(小高) ・阿弥陀如来及両脇侍像(根小屋) ・地蔵菩薩座像(根小屋) ・日光・月光菩薩立像(小牧) ・千手観音座像(矢幡) ・御頭勤番帳(宇崎) ・獅子頭(麻生) ・麻生祇園馬だし祭(麻生) ・モッコク(粗毛) ・息栖神社樹叢(矢幡) |
・麻生藩家老屋敷記念館(麻生) ・不動明王立像(根小屋) ・薬師如来立像(小牧) ・十一面観世音菩薩立像(小高) ・六十六部納経受納証(白浜) ・麻生御殿向表御間取(麻生) ・どぶろく祭(青沼) ・古塚の碑(富田) ・ナギ (麻生:常安寺) ・スギ (青沼:春日神社) |
北浦町
| 【県指定】 | ◇如意輪観音座像(銅像)(北浦町小幡) | |
| 【町指定】 | ・観音寺境内の大椎(小幡) ・鷲峯の槇(吉川) ・香取神社境内のシイ(成田) ・成田平のモチノキ(成田) ・観音寺仁王門(小幡) ・山越阿弥陀物3点(小幡) ・木崎城跡(内宿) |
・自性寺境内のカヤ(内宿) ・化蘇沼稲荷神社境内のモミ(内宿) ・香取神社のモミ(長野江) ・化蘇沼稲荷神社(内宿) ・八幡神社本殿(中根) ・早川貝塚(成田) ・木造虚空蔵菩薩座像(行戸) |
玉造町
| 【国指定】 | □西蓮寺仁王門(玉造町西蓮寺) | □西蓮寺相輪棠 (西蓮寺) |
| 【県指定】 | ◇万福寺阿弥陀堂(羽生) ◇大山守大場家住宅(甲) ◇阿弥陀如来立像及両脇侍像(羽生) ◇銅鐘(乙) ◇鳥名木家文書(手賀) |
◇万福寺仁王門(羽生) ◇木造薬師如来坐像(西蓮寺) ◇木造不動明王坐像(芹沢) ◇西蓮寺の大イチョウ(西蓮寺) |
| 【町指定】 | ・常福寺山門(沖洲) ・橘郷造神社本殿(羽生) ・井上神社本殿(井上) ・常福寺随身立像(沖洲) ・玉造大宮神社鰐口(乙) ・銅鋺(浜) ・西蓮寺常行三昧会(西蓮寺) ・三味塚古墳(沖洲) ・スダジイ(若海) ・スギ(乙) ・カキの化石床(浜) |
・円勝寺山門(八木蒔) ・八幡神社本殿(八木蒔) ・持福院釈迦如来坐像(手賀) ・万福寺木造阿弥陀如来立像(羽生) ・銅独鈷杵(芹沢) ・羽生ばやし(羽生) ・石神遺跡(沖洲) ・イヌマキ(甲) ・カヤノキ(1号〜3号)(八木蒔) ・クスノキ(井上) ・旧象(トロゴンティリー)歯の化石(甲) |